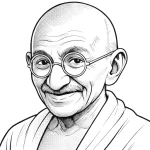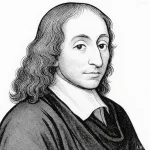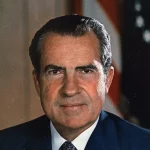「道徳は万物の基礎であり、真理はすべての道徳の本質である」
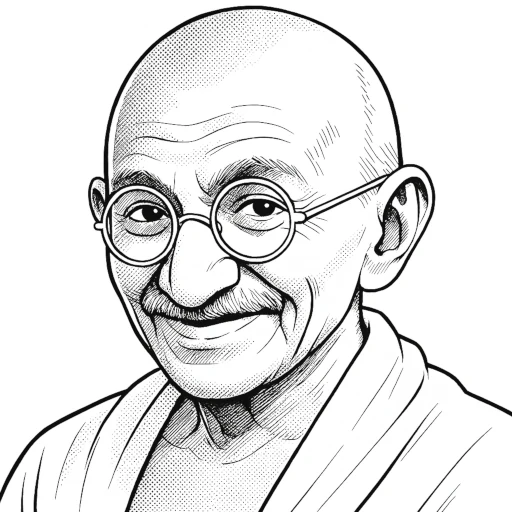
- 1869年10月2日~1948年1月30日
- イギリス領インド帝国出身
- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者
英文
”Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality.”
日本語訳
「道徳は万物の基礎であり、真理はすべての道徳の本質である」
解説
この名言は、人間社会やあらゆる価値体系の根底には道徳が存在し、そしてその道徳の核にあるのが真理であるという、ガンディーの哲学的信念を簡潔に表している。彼にとって「真理(Truth)」とは単なる事実ではなく、宇宙的な秩序や神の意志ともいえる普遍的な原理であり、それに従うことが道徳の核心であると考えられていた。
ガンディーは「神は真理である(God is Truth)」という表現を、「真理こそが神である(Truth is God)」と進化させるほどに、真理を究極の宗教的・倫理的原則とみなしていた。つまり、道徳は相対的な社会規範ではなく、真理という絶対的価値に根ざすことで初めて正当性を持つ。そのため、道徳とは慣習や文化ではなく、真理への誠実な態度によって構成されるべきものとされた。
現代においてもこの名言は、モラルや価値観が多様化し、相対化される風潮の中で、倫理のよりどころをどこに置くべきかという問いに対する深い示唆を与えてくれる。形式的なルールや流行的な正義ではなく、真理に根ざした誠実な生き方こそが、持続可能な道徳の基盤であるというこの言葉は、現代社会の倫理的再生にも通じる普遍的なメッセージである。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
申し込む
0 Comments
最も古い