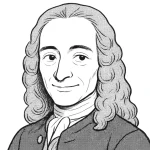ヴォルテール

- 1694年11月21日~1778年5月30日(83歳没)
- フランス出身
- 哲学者、文学者、歴史家
人物像と評価
ヴォルテール(Voltaire、本名:フランソワ=マリー・アルエ)は、18世紀フランスの啓蒙思想家・作家・哲学者であり、宗教的寛容・言論の自由・理性主義を擁護したヨーロッパ啓蒙時代の中心的存在である。
鋭い機知と皮肉を武器に、旧制度(アンシャン・レジーム)やカトリック教会の権威主義を批判し、代表作『カンディード』では、楽観主義への風刺を通じて人間社会の不条理を描いた。
政治的迫害や検閲にたびたび直面しながらも、国外亡命や偽名出版を活用して活動を続け、啓蒙思想の国際的広がりに寄与した。
自由と理性の擁護者として、現代にまで通じる思想的遺産を残した。
「いいね」
引用
- 「支配者は己の気まぐれ以外に法を知らない者を暴君と呼ぶ」
- 「詩の美点の一つは、多くの人が否定しないだろう。それは、散文よりも少ない言葉で多くを語るということだ」
- 「天使がどこに住んでいるのか、空なのか、虚空なのか、あるいは惑星なのかは正確には分からない。それについて知ることは神の御意にかなっていないのだ」
- 「一般に、政府の術とは、ある階級の市民からできる限り多くの金を取り、それを別の階級に与えることにある」
- 「迷信が宗教に対する関係は、占星術が天文学に対する関係に似ている。それは賢母が生んだ狂気の娘である。この娘たちはあまりにも長く地上を支配してきた」
- 「世に踏み出す最初の一歩こそが、残りの人生を左右するものなのだよ」
- 「華やかな言葉遣いは、祝辞や挨拶のような褒め言葉にとどまる場面ではふさわしい。しかし、もっと堅実な内容を求められる説教や教訓的な作品、弁論の中では、華やかさは排除されるべきである」
- 「大衆は凶暴な獣であり、鎖でつなぐか逃げるしかない」
- 「楽観主義とは、我々が惨めなときにすべてが良いと言い張る狂気である」
- 「人は望んだ瞬間に自由である」
- 「感謝とは素晴らしいものである。他者の優れたものが、自分のものにもなるのだから」
- 「人を評価する際は、その人の答えではなく、問いかけによって判断せよ」
- 「人は独りのときには、めったに誇りを感じないものだ」
- 「涙は悲しみの静かな言葉である」
- 「すべての人に、またすべての時代に通用する真実があるわけではない」
- 「独創性とは、賢明な模倣に過ぎない。最も独創的な作家たちも互いから影響を受けたのだ」
- 「人間の弱さと歪みゆえに、もし命を奪うものでない限り、あらゆる迷信に従っている方が、宗教なしで生きるよりも良いのかもしれない」
- 「感謝することで、他者の優れたものを自分のものにすることができる」
- 「人は舌と同様にペンを使う自然権を持っており、それには危険とリスク、そして覚悟が伴う」
- 「人は思考を不正を正当化するための権威として利用し、言葉を自らの考えを隠すために使う」
- 「自然は常に教育よりも強い力を持っている」
- 「友情は魂の結婚であり、この結婚も離婚の可能性がある」
- 「妻を驚かせようとする夫は、しばしば自分が驚く結果になることが多い」
- 「祖先を誇りにする必要がないのは、祖国に尽くした者である」
- 「臆病者が逃げるのは無意味だ。死はすぐ背後に迫っているからだ。勇敢な者だけが、死に立ち向かうことで逃れるのだ」
- 「もし神が食べることや飲むことを必要なだけでなく喜びにもしてくれなかったら、それほど退屈なことはないだろう」
- 「この世界には戸惑いを覚える。私は、この時計が存在しているのに、それを作った時計職人がいないとは想像できない」
- 「この時代の精神を持たない者は、その時代の悲哀をすべて背負うことになる」
- 「人生は棘に覆われているが、それを早く通り抜けるほかに救いの道はない。不運に長く執着すればするほど、それは我々に大きな害を与える」
- 「最良の政府とは、時折の暗殺によって調整される慈悲深い独裁である」
- 「我々は皆、弱さと過ちに満ちている。互いの愚かさを赦し合おう――それこそが自然の第一の法則である」
- 「愚か者を、彼らが崇拝する鎖から解放するのは難しい」
- 「荒唐無稽なことを信じさせる者は、残虐行為をも行わせることができる」
- 「人は、自らがしなかったすべての善に対して罪を負っている」
- 「悪事を働く機会は一日に百回もあるが、善行を行う機会は一年に一度しかない」
- 「寛容とは何か? それは人間性の結果である。我々は皆、弱さと過ちでできているのだから、互いの愚かさを赦し合おう――それこそが自然の第一の法則である」
- 「すべての作家において、その人と作品を区別しよう」
- 「では、あなたは自分の魂を何と呼ぶのか? 魂についてどのような考えを持っているのか? 啓示がない限り、自分自身の中に、感情や思考の未知なる力以外の何かが存在すると認めることはできないだろう」
- 「他人の経験から学ぶほど賢明な人がいるだろうか?」
- 「欺くために話すことと、控えめであるために沈黙することを区別しなければならない」
- 「私たちは決して今を生きていない。常に生きることを期待しているだけだ」
- 「最善は、善の敵である」
- 「完璧はゆっくりとした歩みの中で達成される。それには時の手が必要である」
- 「逐語訳をする者たちには災いあれ。すべての言葉をそのまま訳すことで、意味を弱めてしまうのだから!まさにこうして、『文字は殺し、精神は生かす』と言えるのだ」
- 「金の話となれば、誰もが同じ宗教になる」
- 「彼は偉大な愛国者であり、人道主義者であり、忠実な友人だった。もちろん、彼が本当に死んでいるならばの話だが」
- 「理論にとらわれずに働こう。それが人生を耐えうるものにする唯一の方法だ」
- 「極めて小さき者ほど、極めて大きな誇りを持つ」
- 「自分で考え、他人にもそうする権利を楽しませよう」
- 「古代ローマ人は建築の最高傑作である円形闘技場を、野獣が戦うための場として築いた」
- 「神聖ローマ帝国は、神聖でもなく、ローマ的でもなく、帝国でもない」
- 「偏見とは、愚か者が理性の代わりに用いるものである」
- 「第一の地位で埋もれている者も、第二の地位では輝く」
- 「私は真実がとても好きだが、殉教は全く望んでいない」
- 「有罪の者を救うリスクを負っても、無実の者を有罪にするよりは良い」
- 「暴君には常にわずかな美徳の影がある。法律を破壊する前に、それを支持するからだ」
- 「今日がすべて順調だというのは、我々の幻想に過ぎない」
- 「人々が吝嗇(けち)と呼ぶ人物を嫌うのは、彼から何も得られないからに過ぎない」
- 「作品の美しさを見て知るだけでは十分ではない。それを感じ、心を動かされなければならない」
- 「良き愛国者であるためには、人類の他の部分の敵とならなければならないというのは嘆かわしいことだ」
- 「私の人生は闘いである」
- 「彼はよほど無知なのだろう。なぜなら、尋ねられた質問すべてに答えているからだ」
- 「退屈な人間になる秘訣は……すべてを話し尽くすことだ」
- 「無駄なもの、それはとても必要なものだ」
- 「神を崇拝し、友を愛し、敵を憎まず、迷信を嫌悪しながら死ぬ」
- 「生者には敬意を、死者にはただ真実を」
- 「離婚はおそらく結婚とほぼ同じくらい古い制度だろう。しかし、結婚のほうが数週間ばかり先に始まったのではないかと思う」
- 「現在は未来を孕んでいると言われる」
- 「最も安全な道は、良心に反することをしないことだ。この秘訣を知れば、人生を楽しみ、死を恐れることもなくなる」
- 「しばしば、どんなに何を言おうとも、悪党はただの愚か者に過ぎない」
- 「既存の権威が間違っている事柄で正しい立場を取ることは、危険である」
- 「まず閃光が現れ、雷が続く」
- 「悪人にとっては、すべてが口実となる」
- 「理性の真の勝利とは、それを持たない人たちともうまくやっていけることである」
- 「学識のある女性は、女戦士と同じように存在するが、発明家であることは稀である」
- 「征服するだけでは十分ではない。人を惹きつける術を学ばねばならない」
- 「ペンを持つことは、戦いに臨むことだ」
- 「読者を退屈させた本はたくさん知っているが、本当の悪をもたらした本は一つも知らない」
- 「心がささやいているとき、口はうまく従わない」
- 「すべての人間は鼻と五本の指を持って生まれてくるが、神の知識を持って生まれてくる者はいない」
- 「もし神が私たちを自分の姿に似せて創造したのなら、私たちもそれ以上に神を似せて創り上げた」
- 「私は80年を生きてきたが、ただ、諦めてこう言うことを知ったに過ぎない。ハエはクモに食べられるために生まれ、人間は悲しみに飲み込まれるために生まれるのだと」
- 「人々が神について健全な概念を持たないとき、誤った考えがそれに取って代わる。それはちょうど、良い貨幣がないときに偽貨が使われるのと同じだ」
- 「情熱を抑えるのではなく破壊しようとする者は、天使を演じようとしているに過ぎない」
- 「適度に使い、濫用せず…禁欲も過剰も人を幸福にはしない」
- 「恐怖は犯罪の後に訪れ、それ自体が罰である」
- 「犯罪者への罰は有益なものであるべきだ。絞首刑にされた者は何の役にも立たないが、公共労働を課せられた者は国に奉仕し、生きた教訓となる」
- 「ニュースに関しては、必ず確証という聖礼を待つべきである」
- 「幻想こそが、すべての快楽の始まりである」
- 「信仰とは、理性では信じられないときに信じることにある」
- 「退屈でなければ、どんなスタイルも良い」
- 「愛はすべての心を貫く特徴を持ち、愛する人の欠点を隠す包帯を身に着けている。愛には翼があり、素早く訪れ、同じように飛び去っていく」
- 「ゆえに、社会は世界と同じくらい古い」
- 「殺人は禁じられている。ゆえに、すべての殺人者は罰せられる…ただし、大勢を殺し、ラッパの音に乗せて行われる場合は別だ」
- 「知らないものを願うことはできない」
- 「神を信じることは不可能であり、神を信じないことは不条理である」
- 「人の名声を築くのは時であり、時はやがてその人の欠点さえも尊敬に値するものにしてしまう」
- 「話し手が理解しておらず、聞き手も理解しない時、それが形而上学だ」
- 「楽園は優しい心のために、地獄は愛のない心のために作られた」
- 「川が海にたどり着く速さよりも、人が過ちへと進む速さのほうが早い」
- 「男性のあらゆる理論も、女性の一つの感情には及ばない」
- 「神は大軍の側にいるのではなく、最も正確に撃つ者の側にいる」
- 「医学の技術とは、自然が病気を治す間、患者を楽しませることにある」
- 「有名になりすぎた名前は、なんと重い重荷であることか」
- 「耳は心への通り道である」
- 「この自己愛は私たちの生存を守る手段であり、人類の存続を支える備えに似ている。それは必要であり、私たちにとって愛おしく、喜びを与えてくれるものであり、私たちはそれを隠さねばならない」
- 「本から得る教えは火のようなものだ。他人から得て自分の家で灯し、他者に伝えることで、やがてそれは皆の財産となる」
- 「政府には羊飼いと肉屋の両方が必要だ」
- 「祖国とは、私たちの心が結びつく場所である」
- 「私たちは自分自身の庭を耕さなければならない。エデンの園に置かれたとき、人間はそこで働くためにそこに置かれた。それは人間が安息のために生まれたのではないことを証明している」
- 「持続的な思考の攻撃に耐えられる問題は存在しない」
- 「本の多さが私たちを無知にしている」
- 「言葉の大きな役割のひとつは、私たちの考えを隠すことにある」
- 「疑念は心地よい状態ではないが、確信は不条理である」
- 「不正は最終的に独立を生み出す」
- 「すべての宗教の中で、キリスト教は当然ながら最も寛容さを促すべきものであるが、これまでのところ、キリスト教徒は最も不寛容である人々だった」
- 「もし神が存在しなければ、人間は神を創造する必要があるだろう」
- 「歴史とは、犯罪と不幸の記録に過ぎない」
- 「誰もが道を踏み外すが、最も賢明な者は早く悔い改める者である」
- 「風刺は作家が生きている間に嘘をつき、賛辞は彼らが死んだ後に嘘をつく」
- 「常識はそれほど常識的ではない」
- 「安定した社会があるところにはどこでも宗教が必要である。法律は表立った犯罪を取り締まり、宗教は隠れた犯罪を取り締まる」
- 「私たちはいつも相手の願いを叶えることはできないが、いつでも丁寧な言葉をかけることはできる」
- 「歴史は哲学として書かれるべきである」
- 「双方の弱さがすべての争いの合言葉であることは、よく知られている」
- 「偶然とは意味を持たない言葉であり、何事も原因なしに存在することはできない」
- 「機知に富んだ言葉は何も証明しない」
- 「上には泡、下には澱、だが中ほどは素晴らしい」
- 「多くの人が美徳とみなすものも、40歳を過ぎると単にエネルギーの喪失に過ぎない」
- 「私はこれまでただ一度だけ、しかもとても短い祈りを神に捧げた。『主よ、どうか私の敵を愚かにしてください』と。そして、神はその願いを叶えてくださった」
- 「絵画において、小さなものと大きなものは対比されるが、それが互いに相反するとは言えない。色の対立も対比を生むが、色には互いに相反するものもあり、それは近くに並べられると目に不快な印象を与える」
- 「ただ公正であるだけの人は冷酷であり、ただ賢明であるだけの人は悲しい人である」
- 「盲目と描かれるべきは愛ではなく、自己愛である」
- 「賢明な暴君は決して罰せられない」
- 「神は私たちに命という贈り物を与えたが、豊かに生きるという贈り物を与えるのは私たち自身の責任である」
- 「愛とは、自然が用意したキャンバスに想像力が刺繍を施すものである」
- 「宗教の真実は、理性を失った者によって最もよく理解される」
- 「意見は、この小さな地球において、疫病や地震よりも多くの混乱を引き起こしてきた」
- 「人生が配るカードを誰もが受け入れなければならない。しかし、一度手にしたカードをどう使って勝利を目指すかは、その人自身が決めるべきことである」
- 「公正でない者は厳格であり、賢明でない者は悲しい」
- 「宗教は私たちがこの世とあの世で幸福になるために設けられた。来世で幸福になるために私たちがすべきことは何か?それは公正であることだ」
- 「古代の人々は私たちに美の女神への捧げ物を勧めたが、ミルトンは悪魔に捧げた」
- 「読書をしよう、踊ろう――これら二つの娯楽は、決して世界に害をもたらすことはない」
- 「処女性が美徳であると考えたことは、人間の心の迷信の一つである」
- 「あなたの足元に横たわり、あなたの腕の中で死にたい」
- 「世の中で成功するためには、愚かであるだけでは足りない。礼儀正しさも必要だ」