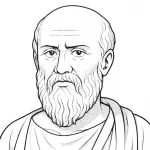「人を欺くものは、魔法のような魅惑を生み出すようだ」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
”Whatever deceives men seems to produce a magical enchantment”
日本語訳
「人を欺くものは、魔法のような魅惑を生み出すようだ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、人を欺くものが持つ魅惑的な力についてのプラトンの洞察を示している。プラトンは、人々が錯覚や欺瞞に引き込まれる理由を哲学的に考察しており、欺瞞がしばしば人間の感覚を魅了し、現実と幻想の境界を曖昧にする力を持つことを指摘している。欺瞞が現実よりも魅力的に感じられるのは、それが人々の欲望や恐れを巧妙に利用し、心を引きつけるからである。人間は真実を知ることを望みながらも、しばしば幻想の方が心地よく、魅力的であるため、欺瞞に囚われてしまうという心理的な要素がここに反映されている。
プラトンは、人間の知覚がいかに簡単に欺かれるかをよく理解していた。彼は『国家』の中で「洞窟の比喩」を用いて、人々が目に見える現実を真実と信じ込む傾向にあることを説明している。洞窟の壁に映し出される影を真実だと思い込む囚人たちと同様に、私たちはしばしば幻想や虚構を現実だと信じてしまう。これらの幻想は、感覚や感情を強く刺激することで、私たちを魅了し、理性を曇らせる。欺瞞が魔法のように人々を引きつけるのは、それが感覚的で魅惑的な要素を備えているからである。
現代社会においても、この名言は深い意味を持つ。私たちは、広告やメディア、ソーシャルメディアの情報に日々接し、それらが現実をどのように操作し、美化するかを目の当たりにしている。たとえば、理想的な生活を映し出す広告や、フィルターがかけられた完璧な写真は、人々に夢のような幻想を抱かせるが、実際には現実とかけ離れていることが多い。それでも、これらの幻想に引き込まれるのは、感覚が魅了され、理性が一時的に麻痺するからである。人間は、自分が見たいものを信じ、都合の良い幻想に魅了されやすい。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?