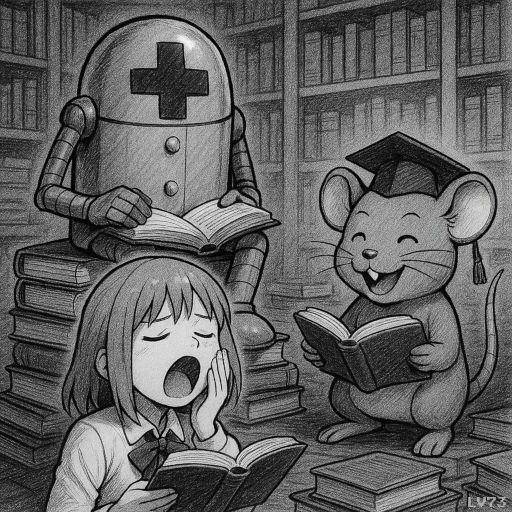「和を尊び、争わないことを基本とせよ」

- 574年2月7日頃~622年4月8日
- 日本(飛鳥時代)出身
- 皇族、政治家、思想家
原文
「和ぐを以て貴しとし、忤ふること無きを宗とす」
現代語訳
「和を尊び、争わないことを基本とせよ」
出典
十七条憲法
解説
この言葉は聖徳太子の「十七条憲法」の第一条にあたるものであり、日本文化に深く根付いた「和」の精神を初めて明文化した歴史的な一節である。太子は、国家や社会をまとめるためには個々の対立を抑え、協調と一致を第一に考えるべきであると説いたのである。飛鳥時代は豪族同士の権力争いが絶えず、国を安定させるためには何よりも和を重んじる必要があった。
この思想は現代日本にも色濃く受け継がれている。企業の会議や学校の教育現場においても、個人の主張以上に全体の調和が尊ばれる風土が見られる。もちろん、現代では建設的な意見対立も重要視されるが、それでもなお、最終的には協力と合意を目指すことが理想とされる。この「和を以て貴しとす」という教えは、平和的共存と共同体意識を築くための普遍的な原則である。
具体例として、国際関係において日本が「対話による解決」を重視する姿勢や、企業内でのコンセンサス重視の文化が挙げられる。対立を乗り越え、皆で力を合わせることが最も尊い道であるというこの名言は、現代社会においてもなお生き続けているのである。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「聖徳太子」の前後の名言へ
関連するタグのコンテンツ
【厳選】
申し込む
0 Comments
最も古い