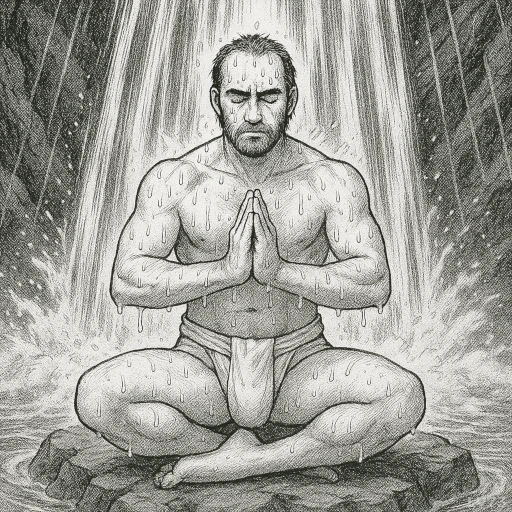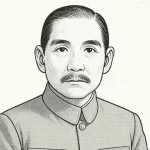「天下に大事を成し遂げる者は、たとえ傷ができても、十分に腫れなければ針で膿を受けることもふさがることもない」

- 1836年1月3日~1867年12月10日
- 日本(江戸時代・土佐藩)出身
- 志士、政治活動家、実業家
原文
「天下に事をなすものは、ねぶともよくよく腫れずては、針へは膿をうけもふさず候」
現代語訳
「天下に大事を成し遂げる者は、たとえ傷ができても、十分に腫れなければ針で膿を受けることもふさがることもない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、大きな事業を成し遂げるためには、困難や痛みを十分に経なければならないという考えを表している。坂本龍馬が生きた幕末は、日本全体が大きな変革期にあり、小手先の努力では乗り越えられない深刻な問題に直面していた。龍馬は、痛みや苦しみを恐れず、物事を徹底的に膨らませ、成熟させた上で初めて成果が得られることを、この膿と傷の比喩で語っているのである。
現代でも、大きな改革や成功には一時的な犠牲や困難を耐え抜く覚悟が必要である。例えば、起業家がビジネスを軌道に乗せるまでには、失敗や資金難といった数多くの試練を乗り越えなければならない。中途半端な努力では成果に至らず、逆により深刻な問題を引き起こすこともある点で、この龍馬の言葉は今なお示唆に富んでいる。
この名言は、痛みや膨張を嫌がらずに受け入れることで、初めて本格的な治癒や成功が訪れるという教訓を与えている。坂本龍馬自身も、何度も挫折と危機を乗り越えながら、時代の大きな流れを変えようと行動した。その生き様が、この言葉の背後に重く響いている。
「坂本龍馬」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!