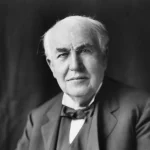「ある日、科学の頭脳から生まれるであろう機械や力は、その潜在的な恐ろしさがあまりにも凄まじく、人間、すなわち戦士さえも恐怖を感じ、戦争を永遠に放棄することになるだろう。それは、苦痛や死を与えるために自らもそれを覚悟する者ですら、その威力に震え上がるほどのものである」
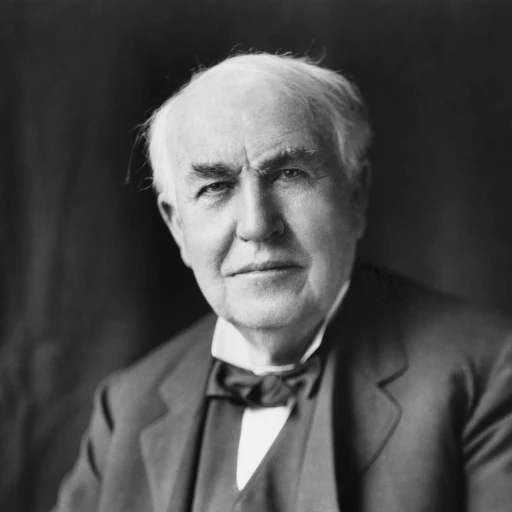
- 1847年2月11日~1931年10月18日
- アメリカ出身
- 発明家および実業家
- 白熱電球の実用化をはじめ、1,000以上の特許を取得した「発明王」
英文
“There will one day spring from the brain of science a machine or force so fearful in its potentialities, so absolutely terrifying, that even man, the fighter, who will dare torture and death in order to inflict torture and death, will be appalled, and so abandon war forever.”
日本語訳
「ある日、科学の頭脳から生まれるであろう機械や力は、その潜在的な恐ろしさがあまりにも凄まじく、人間、すなわち戦士さえも恐怖を感じ、戦争を永遠に放棄することになるだろう。それは、苦痛や死を与えるために自らもそれを覚悟する者ですら、その威力に震え上がるほどのものである」
解説
エジソンのこの言葉は、科学技術がもたらす恐るべき破壊力が、最終的に人類に戦争の愚かさを気づかせるだろうという予見を示している。彼は、科学が進歩することで人間がこれまで想像もできなかったほどの破壊的な力を生み出す可能性に気づいていた。そんな恐怖の力を目の当たりにすることで、戦争の無意味さと恐ろしさに気づき、人類が戦争を放棄するきっかけになるのではないかという考えが込められている。この言葉には、科学の進歩が人類に平和をもたらすという希望と、それに伴う危険への警告が含まれている。
この名言は、核兵器や化学兵器のような現代の大量破壊兵器の誕生を予見しているようにも感じられる。第二次世界大戦における原子爆弾の使用は、人類がどれほどの破壊力を持つ力を手にしてしまったかを実感させた。エジソンが言う「恐るべき力」は、科学が善悪の両方の可能性を持つことを示している。科学は人類の生活を改善する素晴らしい力を持つ一方で、その力を誤用すれば取り返しのつかない破壊をもたらすこともある。この言葉は、科学技術の進歩に対する責任を考えさせるものだ。
また、人間の本能的な戦闘性についての洞察も示している。人類は歴史を通じて戦争を繰り返してきたが、エジソンは、その戦闘本能ですら圧倒されるほどの力を目にすれば、人々は戦争の継続を考え直すかもしれないと述べている。戦士が恐怖を感じ、戦いを放棄するには、非常に強烈な経験が必要だという考えだ。たとえば、第一次世界大戦後のヨーロッパでは、戦争の悲惨さを目の当たりにした人々が平和主義に傾いた。しかし、エジソンの言葉は、さらに破壊的な力が必要になることを示唆している。それほどの恐怖が、戦争を終わらせる唯一の手段になるかもしれないという悲観的な見解を含んでいる。
この名言は、科学技術の倫理的な利用と、平和の追求についての議論を喚起する。現代社会では、AI兵器や生物兵器など、新たな破壊的技術の開発が続いており、それに伴う倫理的な課題がますます重要視されている。科学の発展がもたらす利点を享受しながらも、その潜在的な危険性に対して慎重な姿勢が求められる。エジソンの言葉は、科学技術がいかに人類の未来を左右するかを考えさせ、進歩に伴う責任を再認識させる。科学者や政策立案者は、技術がどのように使われるかを常に意識し、平和を促進するための手段として利用するべきである。
エジソンの名言は、戦争の無意味さと科学技術の力に対する警鐘を鳴らしている。彼は、人類が自ら生み出した破壊的な力に直面することで、ようやく戦争の愚かさに気づくかもしれないと考えた。この言葉は、科学の進歩を慎重に見守りながら、平和のためにそれをどう利用するかを考える重要性を示している。エジソンの予見は、今も私たちに問いかける:「科学技術の力をどのように使えば、より平和な世界を築けるのか?」と。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?