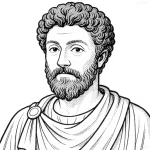マルクス・アウレリウス

- 121年4月26日~180年3月17日
- ローマ帝国
- ローマ皇帝
人物像と評価
マルクス・アウレリウスは、ローマ帝国五賢帝の最後の皇帝であり、哲人皇帝として知られる。
180年までの在位中、帝国の安定と防衛に尽力し、特に北方のゲルマン民族との戦争において軍を率いて戦った。
その内省的な精神は著書『自省録』に表れ、ストア哲学の実践者として自己鍛錬と理性の重視を説いた。
現代でも哲学的洞察と道徳的模範として高く評価される。
一方で、息子コンモドゥスへの帝位継承は失政とされ、後の混乱の原因とも批判される。
この点が理想的統治者像に影を落としている。
「いいね」
引用
- 「人生の幸福はあなたの思考の質に依存している。ゆえに、それを慎重に守り、美徳や理性に適さない考えを抱かないよう注意せよ」
- 「自分を現在に制限せよ」
- 「私たちは、複数の原因による結果を単一の原因に帰することに慣れすぎており、そのために多くの論争が生じている」
- 「習慣的な思考がそのまま心の性格となる。魂は思考によって染められるからだ」
- 「善き人とは何かを議論することに、これ以上時間を浪費するな。善き人になれ」
- 「魂は思考の色に染まる」
- 「存在するすべてのものは、いわば未来に起こるものの種である」
- 「ありのままの自分として見られることに満足せよ」
- 「人生のすべての行いを、最後の行いであるかのように実行せよ」
- 「死は、生と同じく自然の秘密である」
- 「自分自身と調和して生きる者は、宇宙とも調和して生きる」
- 「人に起こるすべてのことは、その人が乗り越えられる力を持っていることばかりである」
- 「地から生じたものは再び地に帰り、天に由来するものはその故郷へと飛び去る」
- 「永遠に読み続けている者ほど怠惰で、真に無知な者はいないかもしれない」
- 「人生そのものは善でも悪でもなく、ただ善と悪が存在する場である」
- 「始めよ。始めることは仕事の半分だ。半分がまだ残っているなら、それを再び始めよ。そうすれば終わるだろう」
- 「人は自らまっすぐであるべきであり、他者によって支えられてまっすぐであってはならない」
- 「機会が訪れたら前進せよ。他人がそれに気づくかどうかを気にして振り返るな…たとえ小さな成功であっても、それに満足し、それが些細なことではないと考えよ」
- 「これから覚えておくべき規則は、何かがあなたを苦々しい気持ちにさせようとするときにこう考えることだ。『これは不幸だ』ではなく、『これを立派に耐えることができるのは幸運だ』と」
- 「貧困は犯罪の母である」
- 「すべての物事が変化によって起こることを常に観察せよ。そして、宇宙の本質は、存在するものを変化させ、それと似た新しいものを作り出すことを何よりも愛していると考える習慣を身につけよ」
- 「死ぬという行為も、人生の行為の一つである」
- 「怒りの原因よりも、その結果のほうがどれほど深刻であることか」
- 「過度に怒りを覚えたときは、人間の人生がいかに短いかを思い出せ」
- 「人間は互いのために存在している」
- 「人の真の本質を理解するには、その人の心を観察し、追い求めるものと避けるものを見極めなければならない」
- 「過去を振り返ってみよ。移り変わる帝国が興り、そして滅びた様子を見れば、未来もまた予見できる」
- 「教育を受けていない天性の才能は、教育だけで天性の才能を欠く場合よりも、栄光や美徳に人を導くことが多い」
- 「すべてのものは永遠に似た形を持ち、その周期の中で再び巡り来る」
- 「宇宙は変化そのものだ。我々の人生は、思考がそれに与える形で成り立っている」
- 「理解力における適性はしばしば遺伝するが、理性と想像力に由来する天才は稀である」
- 「自分の運命が置かれた環境に順応し、運命が共に生きることを定めた仲間を心から愛せ」
- 「起こるすべてのことは、あるべき形で起こる。そして、注意深く観察すれば、それが真実であると気づくだろう」
- 「怒りは不誠実であることはできない」
- 「自分にとって困難に思えることだからといって、それを他の誰にも成し遂げられないと思ってはならない」
- 「持っていないものに心を奪われるのではなく、すでに持っているものに心を向けよ」
- 「自分の心を支配する力はあるが、外部の出来事を支配する力はない。それを理解すれば、力を見いだすだろう」
- 「人々の行動の意図をできる限り見極め、それが何を目指しているのかを常に探る習慣を持て。そしてこの習慣をより意義深いものにするため、まず自分自身に対してこれを実践せよ」
- 「宇宙の秩序と個人の秩序は、共通する根本原理の異なる表現と現れにすぎない」
- 「いかなる美しいものも、その美しさはそれ自体から生じ、外に何も求めない。称賛はその一部ではなく、称賛によって良くも悪くもならない」
- 「未来に心を乱されるな。もしそれに向き合わなければならないときは、今日現在に対して理性で武装しているのと同じ武器でそれに立ち向かえばよい」
- 「人の価値はその志を超えることはない」
- 「人生で観察するすべてを体系的かつ真実に探求する能力ほど、心を広げる力を持つものはない」
- 「模倣を控えることが、最善の復讐である」
- 「人生の目的は、多数派の側に立つことではなく、自分が狂気の一員となるのを避けることだ」
- 「永遠に手元に残る唯一の富は、あなたが他者に与えた富である」
- 「時間とは出来事が流れていく一種の川のようなものであり、その流れは激しい。何かが目の前に現れるや否や流され、別のものがその場所を占め、そしてそれもまた流されていく」
- 「高潔な人間は、自分より高い理想によって自分を比較し評価する。一方、卑しい人間は、自分より低い基準によってそうする。前者は向上心を生み出し、後者は野心を生むが、野心は俗物的な人間が目指す方法である」
- 「人が恐れるべきは死ではなく、生きることを始めないことである」
- 「人生のあらゆる行為を最後のものとして行えば、自らを安らぎへと導けるだろう」
- 「人は誰もが他人よりも自分自身を愛しているのに、なぜ自分に対する自分の意見よりも他人の意見を重視するのだろうかと、私はしばしば不思議に思う」
- 「自分の力がその課題に及ばないからといって、それが人間の能力を超えていると思ってはならない。もしそれが人間の能力の範囲内にあるなら、自分にもできると信じよ」
- 「人が最も静かで平穏な隠れ場所を見つけられるのは、自らの魂の中である」
- 「幸福に生きることは、魂の内なる力である」
- 「賢者にとって人生は問題であり、愚者にとって人生は解答である」
- 「隣人が何を言い、何をし、何を考えているかを気にしない人は、どれほどの時間を節約できることか」
- 「内面を見よ。善の泉は内にあり、掘り続ければ、それはいつでも湧き出てくるだろう」
- 「正しくないことはするな。真実でないことは言うな」
- 「運命が結びつけたものを受け入れ、運命が引き合わせた人々を愛せ。ただし、心を込めてそれを行え」
- 「私たちは、馬が走り、蜂が蜜を作り、葡萄の木が季節ごとに実を結ぶように、何も考えずに自然に他者に善を行うべきである」
- 「宇宙は変化そのものであり、人生は解釈である」
- 「死は感覚の印象からの解放であり、私たちを操る欲望からの解放であり、心の迷いからの解放であり、肉体の厳しい奉仕からの解放である」
- 「朝目覚めたとき、生きていることがどれほど貴重な特権であるかを思え。息をし、考え、楽しみ、愛することができるということを」
- 「生きるという技術は、踊りというよりもむしろ格闘に似ている」
- 「巣箱にとって良くないものは、蜂にとっても良くない」
- 「喪失とは変化にほかならず、変化は自然の喜びである」
- 「最良の復讐は、害を与えた者とは異なる人間であることだ」
- 「自分自身に満足し、変化を望むな。また、最期の日を恐れることも、それを待ち望むこともするな」
- 「人が生きられる場所ならば、そこでは良く生きることもできる」
- 「死を軽蔑するな。それを受け入れよ。自然が他のすべてと同じようにそれを定めているのだから」
- 「自然が耐えられるように作られていない出来事は、人には決して起こらない」
- 「人々に見せ、知らせよ。あるべき生き方をしている本物の人間を」
- 「幸福な人生を作るのに必要なものはごくわずかである。それはすべて、自分自身の中にあり、自分の考え方にかかっている」
- 「毎日はそれぞれ独自の贈り物をもたらしてくれる」
- 「普遍的な自然が、どの人にもどの時にも与えるものは、その時その人にとって最善のものである」
- 「人生のあらゆる行為を、最後の行為であるかのように行え」
- 「明日は無意味であり、今日は遅すぎる。善は昨日のうちに生きられた」
- 「傷つけられたという感覚を拒絶すれば、その傷自体が消える」
- 「私たちの人生は、私たちの思考が形作るものである」