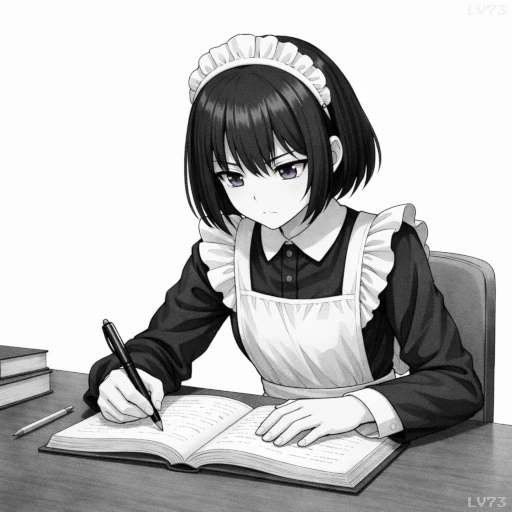「常磐津を学んでいた人が、やがて書物を読む人となり、三味線を奏でる音も、貝(ほら貝)を吹く音へと変わる」

- 1830年9月20日~1859年11月21日
- 日本(江戸時代・長州藩)出身
- 思想家、教育者、尊王攘夷運動家
原文
「常磐津を学ぶ人、変じて書を読む人となり、三味線を引く声、換りて貝を吹く声となる」
現代語訳
「常磐津を学んでいた人が、やがて書物を読む人となり、三味線を奏でる音も、貝(ほら貝)を吹く音へと変わる」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、吉田松陰が時代の変革と人の転身について象徴的に語ったものである。常磐津(ときわづ)とは江戸時代の浄瑠璃音楽の一種であり、娯楽や芸道を意味するが、これに親しんでいた人々が、やがて学問や武に志す者へと変わり、三味線の優雅な音も、戦いや覚悟を象徴する貝の音へと変わっていくという、激動の時代を表現している。これは、平和な時代から非常の時代への転換に応じて、人もまた変わるべきであるという松陰の認識を示している。
現代においても、この考えは重い意味を持つ。平時には文化や芸術に親しむことが大切であっても、有事や激変の時代には、現実に応じた行動や心構えへの切り替えが求められる。吉田松陰は、時勢に応じて己を変革し、必要とされる役割を果たす覚悟を持つべきだと教えているのである。
例えば、社会の平穏が破られるとき、芸術家や知識人がただ悠長に過ごすのではなく、社会的な責任を自覚して声を上げたり行動したりする必要がある。吉田松陰は、時代の要請に応じて、優雅さを捨ててもなお正しい行動を取るべきであると、厳しくも力強く訴えているのである。
「吉田松陰」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!