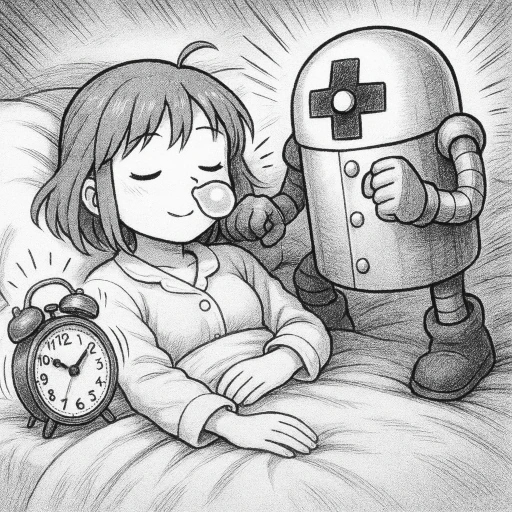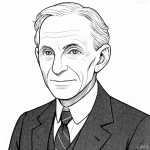「十年の短さを嘆くのは、夏の一時しか生きない蝉に、長寿の椿のようになれと言うようなものであり、百年の長さを誇るのは、長寿の椿を短命の蝉にさせようとするようなものである」

- 1830年9月20日~1859年11月21日
- 日本(江戸時代・長州藩)出身
- 思想家、教育者、尊王攘夷運動家
原文
「十歳を以て短しとするは、蟪蛄をして霊椿たらしめんと欲するなり。百歳を以て長しとするは、霊椿をして蟪蛄たらしめんと欲するなり」
現代語訳
「十年の短さを嘆くのは、夏の一時しか生きない蝉に、長寿の椿のようになれと言うようなものであり、百年の長さを誇るのは、長寿の椿を短命の蝉にさせようとするようなものである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、吉田松陰が寿命や時間の価値についての本質を説いたものである。蟪蛄(けいこ)は夏にだけ生きる蝉を指し、霊椿(れいちん)は長寿を象徴する樹木を指す。自然にはそれぞれに定められた寿命や役割があり、短いことを嘆いたり、長いことを誇ったりするのは無意味であるという深い認識を表している。幕末の動乱期にあって、限られた命をどう生きるかを問う松陰の思想がよく表れている。
現代においても、この考え方は非常に示唆に富む。寿命や時間の長短にこだわるのではなく、それぞれに与えられた時間をいかに充実して生きるかが重要であるという教訓である。長生きすること自体が目的ではなく、限られた時間の中でどれだけ意味ある生を全うできるかが問われている。
例えば、若くして偉大な業績を残した人々や、短い生涯で深い感化を周囲に与えた人物がいるように、生きた年数ではなく、生き方こそが価値を決めるのである。このように、吉田松陰は時間に対する執着を超え、使命に忠実な生き方を示唆している。
「吉田松陰」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!