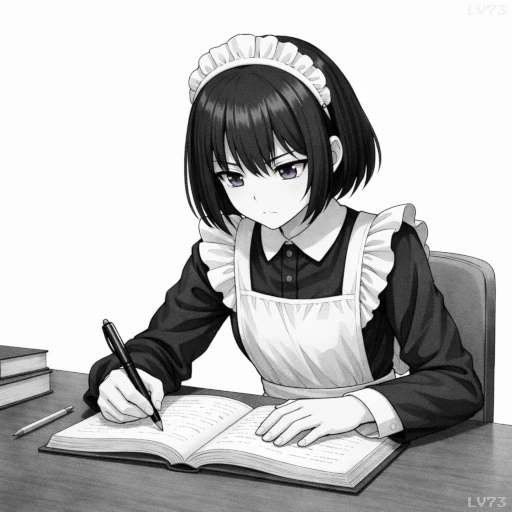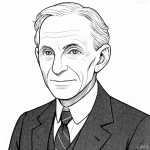「読書の心得としては、まず自分の心を空っぽにし、胸の中にあらかじめ意見を持たず、自らの心を書物の中に入り込ませて、その書物の道理がどうであるかを素直に見て、書物の意図を受け取るべきである」

- 1830年9月20日~1859年11月21日
- 日本(江戸時代・長州藩)出身
- 思想家、教育者、尊王攘夷運動家
原文
「凡そ読書の法は吾が心を虚しくし、胸中に一種の意見を構へず、吾が心を書の中へ推し入れて、書の道理如何と見、其の意を迎へ来るべし」
現代語訳
「読書の心得としては、まず自分の心を空っぽにし、胸の中にあらかじめ意見を持たず、自らの心を書物の中に入り込ませて、その書物の道理がどうであるかを素直に見て、書物の意図を受け取るべきである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、吉田松陰が真摯な読書態度の重要性を説いたものである。読書に臨む際に先入観や自説を立ててしまうと、書物の真意を素直に受け取ることができなくなる。だからこそ、心を虚しくして、書物の理に自分の心を向き合わせ、真意を受け取る努力をせよと説いている。幕末の動乱期に、多様な学問や思想を吸収する必要があった松陰の、誠実な知の姿勢がよく表れている。
現代においても、この教えはきわめて重要である。情報があふれる時代にあって、自分の考えに合う情報だけを受け取ろうとする「バイアス」に陥る危険は大きい。しかし、吉田松陰の教えに従えば、先入観を捨てて書物と対話することで、新たな真理に触れることができる。読書とは自己の主張を補強するためにするのではなく、自己を新たに磨き上げるためにするべきであるという根本姿勢を改めて認識させられる。
例えば、異なる価値観を持つ本を読むときにも、最初から否定的な構えを取らず、まずはその立場に自分を置いて考え抜くことが求められる。吉田松陰は、学びにおいては常に謙虚であり、書物に心を向けることこそが真の読書であると力強く教えているのである。
「吉田松陰」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!