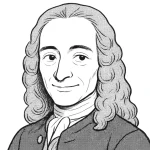「人々が吝嗇(けち)と呼ぶ人物を嫌うのは、彼から何も得られないからに過ぎない」

- 1694年11月21日~1778年5月30日(83歳没)
- フランス出身
- 哲学者、文学者、歴史家
英文
“Men hate the individual whom they call avaricious only because nothing can be gained from him.”
日本語訳
「人々が吝嗇(けち)と呼ぶ人物を嫌うのは、彼から何も得られないからに過ぎない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
ヴォルテールは、他人の「吝嗇」や「けち」を非難する態度が、実はその人物から利益を得られないことへの不満に過ぎないと指摘している。この名言には、人々が他人を「吝嗇」と呼ぶとき、それが本当に相手の性格への批判なのか、それとも利益を得られないことへの不満からくる偏見なのかを考えさせる視点が含まれている。ヴォルテールは、人間関係における利害の動機と、それが個人に対する評価や感情にどのように影響を与えるかについて、皮肉を交えて示唆している。
現代においても、この言葉は人が他人を評価する際の動機についての洞察を与えている。たとえば、金銭的な援助や支援を提供しない人に対して「けち」というレッテルを貼ることがあるが、それは必ずしもその人の実際の性格を表しているわけではなく、単に期待が満たされなかったことへの反応であることが多い。また、見返りが得られない関係において、人は相手に対して批判的になりがちであり、無意識に損得感情が人間関係に影響していることがある。ヴォルテールの言葉は、私たちが他者を判断する際、その評価が利害に基づく偏見ではないかを問い直す視点を提供している。
この名言は、他人の性格や行動を判断する際に、自分の期待や利害が評価に影響していないかを見つめ直す重要性を教えている。相手から何かを得られないからといって、その人の価値を低く見るのではなく、相手の本来の人柄を見極める姿勢が大切である。ヴォルテールの言葉は、人間関係における利害を超えた真の理解を持つことが、公平な評価と健全な関係を築くために必要であると教えている。
「ヴォルテール」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!