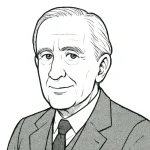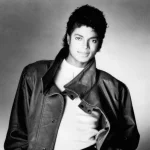「私はなりたかった——いや、なるべきだった——第二のレンブラントに」

- 1802年2月26日~1885年5月22日
- フランス出身
- 作家、詩人、劇作家
英文
“I would have liked to be – indeed, I should have been – a second Rembrandt.”
日本語訳
「私はなりたかった——いや、なるべきだった——第二のレンブラントに」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、ユゴーが持っていた芸術への情熱や高い理想、自らの創作への強い志向を表している。 ヴィクトル・ユゴーは詩人であり作家であったが、彼の内面には他の芸術分野、特に絵画に対する憧れがあった。レンブラントは、光と影を巧みに使って人間の内面や感情を描き出した偉大な画家であり、ユゴーはそのような深い表現力を自分の芸術にも取り入れたいという理想を抱いていた。自分もレンブラントのように人間の真髄を表現する存在でありたかったと感じているが、実現し得なかったことへの惜しみや諦めも表れている。
ユゴーの視点は、芸術家が持つ表現力や人間性の深みへの探求が、自分の人生や作品の中で達成したいものであるという認識に基づいている。 レンブラントのように、人生や人間の本質を捉え、それを作品に昇華することは、彼にとって究極の目標であった。たとえば、文学で言葉を用いて感情や内面を描き出すのと同様に、ユゴーは絵画の分野においても深い表現を求めたが、レンブラントのような伝説的な画家になることは自らには叶わなかったと感じている。この発言には、自己の創作活動に対する情熱や追求の深さ、そして理想と現実の狭間に立つ芸術家としての苦悩が含まれている。
この名言は、現代においても芸術や自己実現の追求における理想と現実のギャップについて考えさせられる示唆を提供している。 自らの理想や憧れがあっても、それがすべて実現するわけではない。しかし、ユゴーの言葉は、その憧れや理想が芸術活動の推進力となり、自己の成長や作品の深化に寄与することを教えてくれる。
「ユゴー」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!