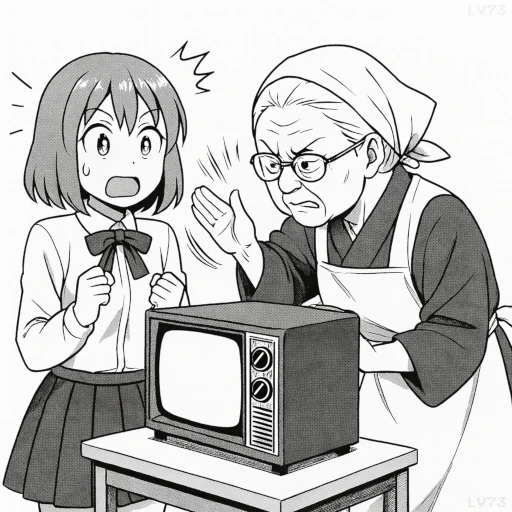「ゆえに、敵がどこを守るべきか分からない状況を作り出す将軍が攻撃に長けており、敵がどこを攻めるべきか分からない状況を作り出す将軍が防御に長けている」

- 紀元前544年~紀元前496年
- 中国出身
- 軍事戦略家、軍師
英文
“Hence that general is skilful in attack whose opponent does not know what to defend; and he is skilful in defense whose opponent does not know what to attack.”
日本語訳
「ゆえに、敵がどこを守るべきか分からない状況を作り出す将軍が攻撃に長けており、敵がどこを攻めるべきか分からない状況を作り出す将軍が防御に長けている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、戦争における不確実性を活用する戦略の重要性を説いている。優れた攻撃とは、敵にどの地点が狙われているかを悟らせずに混乱させることであり、優れた防御とは、敵にどこを攻撃すればよいかを判断させないことである。敵の注意を分散させたり惑わせることで、自軍の計画を効果的に進めることが可能となる。
孫子の時代、戦争は情報戦の側面が強く、敵が自軍の意図を予測できないようにすることが勝敗を分ける重要な要素であった。例えば、陽動作戦を行うことで敵の防御を分散させ、本来狙いたい地点を攻撃しやすくする戦術が用いられた。また、防御側がその拠点や配置を動的に変更することで、敵の攻撃を無効化する技術も同様に重要であった。不確実性を利用することで、敵の意思決定を妨害し、主導権を握る戦略が、この名言の核心である。
現代では、この名言はビジネスや競争、交渉の場面においても応用できる。たとえば、企業が自社の動きを予測されにくい形で新製品を開発したり、市場での動きを曖昧にすることで競合他社の対応を遅らせることができる。また、防御的な戦略としては、自社の弱点を隠すか、あえて目立たせて敵を誘導する技術もある。予測不可能性がもたらす優位性は、競争の中で大きな力となる。この名言は、敵を混乱させることで主導権を握る知恵を示す普遍的な教訓といえる。
「孫子」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!