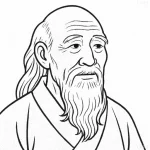「自分が無知であるという事実のほかには、私は何も知らない」

- 紀元前470年頃~紀元前399年
- 古代ギリシャのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者
英文
“I know nothing except the fact of my ignorance.”
日本語訳
「自分が無知であるという事実のほかには、私は何も知らない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、ソクラテスの「無知の知」の哲学を最も簡潔に表現した一文である。彼は、自分が真理を知っているとは決して言わず、むしろ知らないことを認めることこそが真の知識への出発点であると考えた。この言葉は、知的誠実さと謙虚さがいかに重要であるかを示している。
この考えは、デルフォイの神託において「ソクラテスが最も賢い」とされたことに端を発する。多くの人々は自らの無知に気づかずに語るが、ソクラテスは自分の無知を自覚している点で、むしろ他者よりも知的に優れていると理解した。ここで言う「知らない」という自覚は、真理を追求し続ける意志の証でもある。
現代においても、この名言は学問、ビジネス、日常生活を問わず、成長と学びの基本姿勢を説く重要な教訓である。知っていると思い込むことが思考を止める一方で、「知らない」という自覚は新たな視点と進歩をもたらす。この言葉は、真の知者は常に学び続ける者であるという普遍的な真理を私たちに教えてくれる。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「ソクラテス」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い