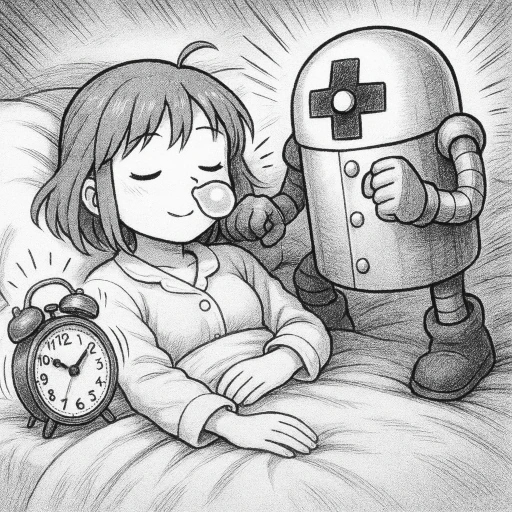「美しさとは、短命の専制である」

- 紀元前470年頃~紀元前399年
- 古代ギリシャのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者
英文
“Beauty is a short-lived tyranny.”
日本語訳
「美しさとは、短命の専制である」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、美が人々に与える強力な支配力と、それがいかに儚いものであるかを鋭く指摘している。ソクラテスは、外見の美しさが一時的に他者を魅了し、理性や判断を曇らせる力を持つことを認めつつも、その影響が永続するものではないと考えた。美は若さや肉体の一部であり、時間とともに必ず衰える運命にある。
この発想は、ソクラテスが重視した内面的な徳や知恵こそが真に価値あるものだという思想と深く結びついている。彼はプラトンの対話篇『饗宴』などにおいて、身体的な美を出発点として、より高次の精神的・哲学的な美へと向かう愛の道筋を語った。つまり、外見に惑わされることなく、魂の美しさを求めることが人間の本質的な成長であるとしたのである。
現代においてもこの名言は、外見重視の社会に対する痛烈な警告として機能する。広告やSNSなどで強調される美の価値は、しばしば人間関係や自己評価を歪める。だが、それに支配されることは一時的な「専制」に過ぎず、やがてその力は失われる。この言葉は、見た目の魅力よりも、人格や知性といった永続的な価値を重視する生き方の必要性を私たちに思い出させてくれる。
「ソクラテス」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!