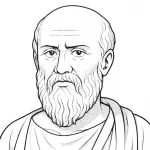「絵に描くと実物に比べて見劣りするもの――なでしこ、菖蒲、桜。そして、物語の中で美しいとたたえられている男や女の姿」

- 966年頃~1025年頃(諸説あり)
- 日本出身
- 作家、随筆家
原文
「絵に描き劣りするもの なでしこ。菖蒲。桜。物語にめでたしと言ひたる男、女のかたち」
現代語訳
「絵に描くと実物に比べて見劣りするもの――なでしこ、菖蒲、桜。そして、物語の中で美しいとたたえられている男や女の姿」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は『枕草子』の「絵に描き劣りするもの」の段に見られる一節であり、実物の美しさや魅力を絵や言葉で完全に表現できないという感覚を示している。清少納言は、なでしこや菖蒲、桜といった花々を挙げ、さらに物語で美しいとされる男女の姿も、描かれた絵では実物に及ばないと述べている。ここには、現実の生命力や気配を芸術に移し替えることの限界への洞察がうかがえる。
平安時代は、絵巻物や物語文学が盛んに作られた時代であった。しかし、どれほど巧緻な絵や詞であっても、実際の自然や人の美しさを完全に再現することはできないという認識があった。この視点は、当時の宮廷人が現実の「生きた美」を何よりも尊重していたことを物語っている。
現代においても、この感覚は共通する。写真や映像が発達した今日でさえ、実際に見る桜や、直接出会う人の表情には、メディアでは伝えきれない魅力がある。この一文は、リアルな体験の価値と、表現の限界を意識させ、現実に触れることの意義を改めて教えてくれるのである。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「清少納言」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い