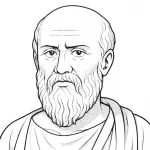「まずは書の手習いをなさいませ。次に琴(きん)の御琴を、人より一層上手に弾けるようになろうと思いなさい。そして、『古今和歌集』二十巻をすべて暗記なさることを、学問の中心になさるのです」

- 966年頃~1025年頃(諸説あり)
- 日本出身
- 作家、随筆家
原文
「ひとつには御手をならひ給へ。つぎにはきんの御琴を、人よりことに弾きまさらんとおぼせ。さては古今の歌二十巻をみなうかべさせ給ふを御学問にはせさせ給へ」
現代語訳
「まずは書の手習いをなさいませ。次に琴(きん)の御琴を、人より一層上手に弾けるようになろうと思いなさい。そして、『古今和歌集』二十巻をすべて暗記なさることを、学問の中心になさるのです」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この一節は、『枕草子』の中でも当時の理想的な教養とたしなみを端的に示す文章である。清少納言は、理想の女性が身につけるべき教養として、まず「書の手習い」、次に「琴の演奏」、さらに『古今和歌集』の全巻暗記を挙げている。この三つはいずれも、平安貴族社会における美意識と高い文化水準を象徴する教養であった。
背景には、平安時代の宮廷文化における「才色兼備」の価値観がある。女性は、容姿だけでなく、優雅な書、音楽の才、和歌の素養を備えることで、社会的評価や恋愛においても優位に立てた。この一文には、ただ学問を修めるのではなく、美しさと芸術性を兼ね備えた教養を理想とする時代精神が鮮明に表れている。
現代においても、この感覚は共通する。知識やスキルを身につけることは、単なる実用を超え、人格を磨き、他者に魅力を与える文化的価値を持つ。この一文は、千年前の教養観を伝えると同時に、学びや芸術を通じて人間性を高める意義を改めて考えさせる名句である。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「清少納言」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い