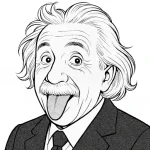「気の毒に思えるもの……二人の恋人を持っていて、あちらこちらと振り回されている男」

- 966年頃~1025年頃(諸説あり)
- 日本出身
- 作家、随筆家
原文
「くるしげなるもの・・・・・・思ふ人ふたりもちて、こなたかなたふすべらるる男」
現代語訳
「気の毒に思えるもの……二人の恋人を持っていて、あちらこちらと振り回されている男」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は『枕草子』の「くるしげなるもの」の段に含まれる一節であり、恋愛における人間模様の滑稽さと哀れさを鋭く描いている。ここでの「くるしげなるもの」とは、「見ていて気の毒に思えるもの」という意味である。清少納言は、二人の女性の間で板挟みになり、右往左往する男性を例に挙げている。恋愛は平安時代の宮廷社会において重要な関心事であり、複数の女性との関係を持つことは珍しくなかったが、それゆえに嫉妬や駆け引きによる葛藤が生じることも多かった。
この背景には、当時の婚姻制度である通い婚の慣習がある。男性は複数の女性を訪ねることが可能であったが、その結果、相手方の女性やその家族の感情に振り回されることになりやすかった。こうした状況は、宮廷文化の中でしばしば話題や笑いの種となり、一方で清少納言はその人間臭い弱さや不器用さに対する冷静な観察を記しているのである。
現代においても、この感覚は共感できる。複数の関係を同時に維持しようとする人が、スケジュールや感情の調整に苦しみ、周囲に同情される光景は少なくない。この一文は、恋愛における欲望と現実の不一致、そしてそれに伴う人間の滑稽さを千年前と同じく描き出しており、時代を超えた普遍的なテーマを示しているのである。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「清少納言」の前後の名言へ
関連するタグのコンテンツ
恋
申し込む
0 Comments
最も古い