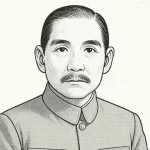「人の心は丸くても、どこかに一本芯を持っていなければならない。あまりに丸いだけでは、かえって転びやすいものだ」

- 1836年1月3日~1867年12月10日
- 日本(江戸時代・土佐藩)出身
- 志士、政治活動家、実業家
原文
「丸くとも一かどあれや人心 あまりまろきはころびやすきぞ」
現代語訳
「人の心は丸くても、どこかに一本芯を持っていなければならない。あまりに丸いだけでは、かえって転びやすいものだ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、人間は柔和であっても、自分なりの信念や誇りを持たなければならないという教えを示している。坂本龍馬が生きた幕末は、協調や融和だけでは乗り切れない、信念をもって行動することが求められる時代であった。龍馬は、ただ調和を重んじるだけの優しさでは、時に流され、志を失う危険があることを見抜いていたのである。
現代でも、人間関係において協調性は重要視されるが、自分の意見や信念を持たない者は、容易に周囲に振り回される危険がある。たとえば、職場や社会の中で誰にでも合わせようとするだけでは、かえって自分を見失い、大きな失敗を招くことがある。この龍馬の言葉は、調和と自己主張のバランスの重要性を今に伝えている。
この名言は、心は穏やかでありながら、しっかりとした自分の軸を持つべきであるという普遍的な生き方の指針を示している。坂本龍馬自身も、多くの人と円滑な関係を築きながらも、決して譲れない志を胸に抱いて行動していた。その柔軟さと芯の強さが、彼を時代を動かす存在へと押し上げたのである。
「坂本龍馬」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!