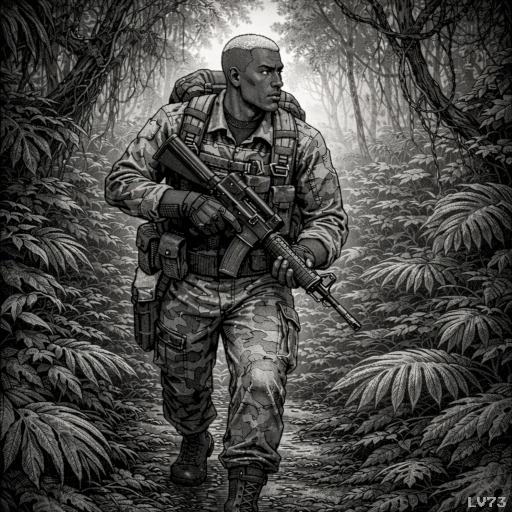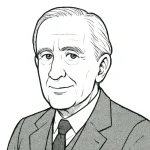「私は英語がひどく苦手だった。この科目には我慢がならなかった。スペルを間違えたかどうかを気にするのはばかげていると思えたからだ。英語の綴りは単なる人間の慣習にすぎず、現実の何かや自然の何かとは全く関係がないのだから」

- 1918年5月11日~1988年2月15日(69歳没)
- アメリカ合衆国出身
- 理論物理学者
英文
“I was terrible in English. I couldn’t stand the subject. It seemed to me ridiculous to worry about whether you spelled something wrong or not, because English spelling is just a human convention – it has nothing to do with anything real, anything from nature.”
日本語訳
「私は英語がひどく苦手だった。この科目には我慢がならなかった。スペルを間違えたかどうかを気にするのはばかげていると思えたからだ。英語の綴りは単なる人間の慣習にすぎず、現実の何かや自然の何かとは全く関係がないのだから」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、ファインマンの合理主義的な性格と自然科学への志向をよく表している。彼にとって重要なのは、自然の法則や現実と結びついた知識であり、人間が恣意的に決めた規則――たとえば英語の綴り――には意味を見いだしにくかったのである。
背景として、ファインマンは学生時代から数学や物理の才能を発揮した一方で、言語や文学といった分野には関心が薄かった。彼は自然に根ざした真理の探究こそが価値ある営みだと考え、人間社会の慣習的な規則に煩わしさを覚えた。
現代においても、この姿勢は教育に一石を投じる。記憶や形式に偏った学習よりも、本質的な理解や自然との結びつきを重視する学びが重要であることを示している。ファインマンの言葉は、学びの価値を「人間の慣習」ではなく「自然との関連性」に置く視点を提供している。
「リチャード・P・ファインマン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!