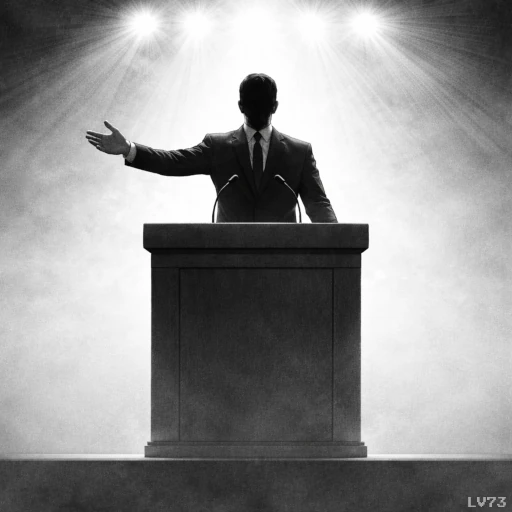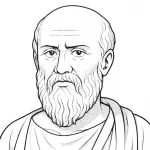「新しい種類の音楽の導入は国家全体を危うくするため避けられねばならない。音楽の様式が乱れるときには、常に重要な政治的制度にも影響を与えるからである」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“For the introduction of a new kind of music must be shunned as imperiling the whole state; since styles of music are never disturbed without affecting the most important political institutions.”
日本語訳
「新しい種類の音楽の導入は国家全体を危うくするため避けられねばならない。音楽の様式が乱れるときには、常に重要な政治的制度にも影響を与えるからである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、音楽が社会や政治に与える影響の大きさを強調している。プラトンは、音楽は単なる芸術の一形態ではなく、人間の精神や社会の秩序に深く関わっていると考えていた。彼の哲学では、音楽は魂に直接働きかけ、人々の道徳や行動に影響を与える力を持つため、その変化が社会全体に及ぼす影響を慎重に考慮する必要があるとされた。音楽の変化は文化や人間性に影響を与え、それがひいては政治的な安定や制度に波及することがあるというのが、プラトンの主張である。
プラトンは『国家』の中で、理想の国家においては教育や文化が調和の取れた秩序を保つべきだと述べている。音楽は、感情や倫理観に影響を与えるため、社会の規範や価値観を変えてしまう可能性があると考えた。たとえば、音楽が過度に感情的で激しいものになると、人々の行動も同じように情緒的で制御不能になり、社会全体の秩序が乱れることを懸念した。音楽は単に娯楽ではなく、社会の道徳や政治的安定に直結する要素であるため、慎重に扱われるべきだという考え方が背景にある。
この名言は、文化と政治の相互作用についても考察を促す。音楽や芸術は、しばしば社会変革や革命の象徴として機能してきた。たとえば、1960年代のロック音楽は、若者の反体制運動や社会的な変革を象徴するものだった。また、歴史的に見ると、音楽の様式の変化が人々の価値観や政治的な意識に影響を与えた例は数多く存在する。プラトンは、音楽が人々の精神にどのように影響を与えるかを深く理解していたため、音楽の力を軽視せず、その変化が社会全体に与える影響を警戒していた。文化的な変化が政治的な変革を引き起こす可能性を考えることは、今でも重要なテーマである。
現代においても、音楽は社会や政治に大きな影響を与える力を持っている。ポピュラー音楽は、時に社会的なメッセージを伝え、人々を結びつけたり、変革を促したりする。たとえば、社会的不公正に対する抗議の歌や、平和や環境保護を訴える音楽が広く支持されることがある。音楽は人々の感情を揺さぶり、集団意識を形成する手段となり得る。音楽が持つ影響力を理解し、それが社会的な変化や政治的な動向にどう関わるかを考えることが必要である。
「プラトン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!