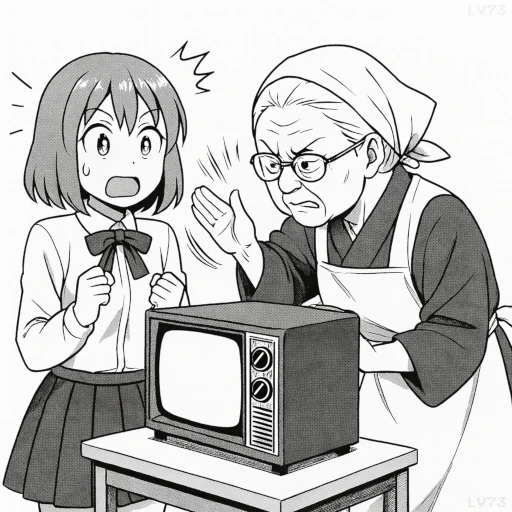「狡猾さは…知恵を低俗に真似たものに過ぎない」

- 紀元前427年~紀元前347年
- 古代ギリシアのアテナイ(アテネ)出身
- 哲学者、学者、アカデメイア(アカデミー)創設者
英文
“Cunning… is but the low mimic of wisdom”
日本語訳
「狡猾さは…知恵を低俗に真似たものに過ぎない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、狡猾さと真の知恵との違いを強調する。プラトンは、狡猾さは表面的な利口さや策謀に過ぎず、真に深い理解や道徳的な洞察を伴う知恵とは別物であると考えていた。狡猾な人は、短期的な利益を得るために策略を用いたり、他人を操ろうとしたりするが、それは知恵とは異なる。知恵は倫理的な基盤と深い洞察に根ざしており、持続的で高潔な目的を持っているのに対して、狡猾さは自己利益を追求するために使われる表面的な知性である。
プラトンの時代、知恵は哲学者たちにとって最も高貴な美徳とされていた。知恵は、単に知識を持つだけでなく、その知識を正しく活用し、社会全体に貢献することを意味していた。対照的に、狡猾さはしばしば自分の利益のために他人を利用するような行動に結びつく。狡猾さは他者の信頼を損なうことが多く、社会的な調和を乱す。そのため、プラトンは狡猾さを知恵の模倣として軽蔑し、真の知恵とは異なるものと位置づけた。
現代社会においても、この名言はさまざまな場面で応用できる。例えば、ビジネスの世界では、短期的な利益を得るために他人を出し抜いたり、倫理的に問題のある手段を使う人もいる。しかし、そうした行動は長続きせず、最終的には信頼や評判を失うことが多い。真のリーダーシップや成功は、狡猾さではなく、誠実さと知恵に基づいて築かれるべきである。知恵を持つ人は、自分の利益だけでなく、他者の幸福や社会全体の利益を考慮する。そのため、知恵は永続的な影響を与え、人々から尊敬されるが、狡猾さは一時的な成功しかもたらさない。
「プラトン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!