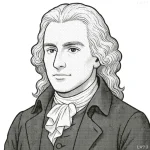「良い音楽を演奏すると人々は聴かないが、悪い音楽を演奏すると人々は話をしない」

- 1854年10月16日~1900年11月30日
- アイルランド出身
- 作家、詩人、劇作家
英文
“If one plays good music, people don’t listen and if one plays bad music people don’t talk.”
日本語訳
「良い音楽を演奏すると人々は聴かないが、悪い音楽を演奏すると人々は話をしない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
オスカー・ワイルドはこの名言で、音楽に対する人々の矛盾した反応を皮肉交じりに表現している。良い音楽は美しく自然に人々の耳に溶け込み、心地よい背景音のように捉えられるため、必ずしも意識的に「聴かれる」わけではない。しかし、悪い音楽が流れると、不快感が人々の注意を引き、むしろ会話が止まり、その不調和が意識に上ってくる。ワイルドの言葉は、心地よいものが時に当たり前として扱われ、逆に不快なものが特別な注意を引くという逆説的な心理を示している。
この名言は、現代においても芸術や美的経験への感受性について考えさせる。良い芸術や音楽は、あまりにも自然に私たちの感覚に溶け込むため、しばしば意識的な鑑賞を避けられがちである。逆に、違和感や不快感を伴うものは、通常の流れを妨げ、特別な注意を引く。例えば、心地よいデザインや建築は意識されずに「当たり前」として受け入れられることが多いが、違和感のあるデザインは人々に気づかれることが多い。ワイルドの言葉は、美しいものが自然と私たちの心に馴染む一方で、不快なものは目立つ存在となるという心理的な現象を示している。
また、この名言は、注意と感受性の選択性についても触れている。人は心地よいものに対してはリラックスし、意識的に鑑賞しなくても満たされるが、不快なものには敏感に反応し、気を取られることが多い。ワイルドはこの言葉を通じて、美しさや質の高いものが持つ自然な魅力と、それが人々の意識から逃れやすい特徴を皮肉っている。この名言は、日常にある美しさにもっと意識を向けることや、注意を払うべき価値のあるものを見逃さないようにすることの意義を再考させてくれるものである。
「オスカー・ワイルド」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!