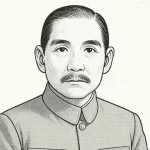「もし芸術作品が豊かで生命力に満ち、完結しているならば、芸術的感性を持つ者はその美を見出し、倫理を重んじる者はその道徳的教訓を見出すだろう。臆病者には恐怖を与え、心が汚れた者には自身の恥を見せるだろう」

- 1854年10月16日~1900年11月30日
- アイルランド出身
- 作家、詩人、劇作家
英文
“If a work of art is rich and vital and complete, those who have artistic instincts will see its beauty, and those to whom ethics appeal more strongly than aesthetics will see its moral lesson. It will fill the cowardly with terror, and the unclean will see in it their own shame.”
日本語訳
「もし芸術作品が豊かで生命力に満ち、完結しているならば、芸術的感性を持つ者はその美を見出し、倫理を重んじる者はその道徳的教訓を見出すだろう。臆病者には恐怖を与え、心が汚れた者には自身の恥を見せるだろう」
出典
出典不詳(編集中)
解説
オスカー・ワイルドはこの名言で、真に優れた芸術作品の多面的な力と、それを受け取る人々の感受性による解釈の違いを説いている。芸術が単なる美や娯楽のためのものにとどまらず、鑑賞する人々の内面を映し出し、多様な反応を引き起こすことを表現しているのだ。ワイルドが生きた19世紀末のヴィクトリア朝時代には、芸術に対する価値観が大きく分かれており、一部の人々は芸術を道徳的な教育の手段と見なしたが、ワイルドはそれを超えて、芸術が人間の心の奥深くに触れる力を持つと考えた。
この名言は、現代においても共感を呼ぶものである。真に優れた作品は、観る者に多様な影響を与え、各自の価値観や人生観に応じて異なる解釈を引き出す。たとえば、一つの絵画や映画が、ある人には美しいと映り、別の人にはその中に隠された社会問題や人間性の闇が感じられることがある。ワイルドの言葉は、芸術が鑑賞者の感受性や価値観に依存して多面的に作用することを示している。
さらに、この言葉は芸術が「鏡」の役割を果たすことも指摘している。鑑賞者が作品を通じて自らの恐れや罪悪感、理想や価値観と向き合うことで、作品は単なる観賞物を超え、自己理解や道徳的な内省をもたらすものである。たとえば、現代アートにおける社会的テーマや、文学作品の倫理的葛藤が、鑑賞者に自らの価値観を問い直すきっかけを与えることがある。このように、ワイルドは芸術を通じて、鑑賞者が自身と向き合う場を提供するものとして捉え、その深い力を称賛しているのである。
「オスカー・ワイルド」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!