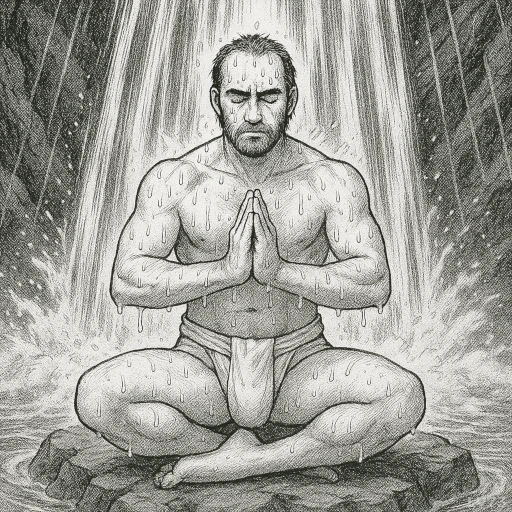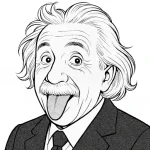「おおよそつまらぬ人間というものは、大きなことを望みながら小さなことを怠り、難しいことを心配するばかりで簡単にできることをしない。そのため、結局は大きなことを成し遂げることができない」

- 1787年9月4日~1856年11月17日
- 日本出身
- 経世論、農政家、思想家、実践的儒学者
原文
「凡そ小人の常、大なる事を欲して小なる事を怠り、出来難き事を憂ひて出来易き事を勤めず。夫故、終に大なる事をなす能はず」
現代語訳
「おおよそつまらぬ人間というものは、大きなことを望みながら小さなことを怠り、難しいことを心配するばかりで簡単にできることをしない。そのため、結局は大きなことを成し遂げることができない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、理想や目標ばかりを語りながら、日々の努力や実行を怠る者への戒めである。二宮尊徳が重視したのは、積小為大(小を積んで大を為す)という実践的な思想であり、この名言はそれを象徴している。大志を抱くことは重要だが、それに向けて着実に歩を進めなければ意味がない。「小なる事を怠り」とは、日常の掃除や挨拶、帳簿付けといった基本的な行動であり、「出来易き事を勤めず」とは、誰にでもできる小さな一歩を蔑ろにする態度を指す。
尊徳の生きた江戸時代後期は、飢饉や財政難で困窮する農村が多く、彼はそれらを農政・道徳・実践によって立て直した人物である。彼の改革は、小さな田畑の再耕から始まり、村人一人一人の行動の改善を通じて地域全体を変革した。つまり、「大なる事」は「小なる事」の集積によって初めて達成されるという思想が、彼の人生と行動によって裏打ちされている。
現代においても、例えば起業家が「世界を変えたい」と語りながら、毎日の顧客対応や会計処理を怠るようでは成功は遠い。学生が「難関大学に入りたい」と思いながら、毎日の学習をさぼるのと同じである。本当に大きな成果を望むなら、まず目の前にある一つ一つの課題に真剣に向き合うことが重要であると、この名言は教えている。
「二宮尊徳」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!