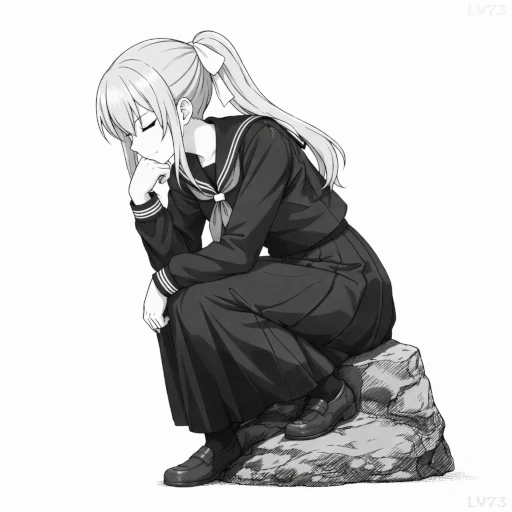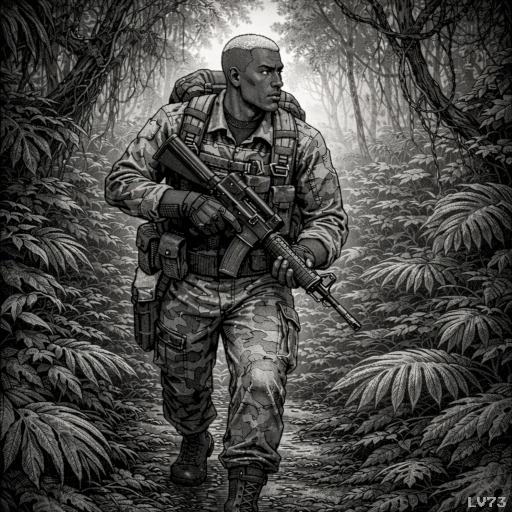「人間が卑しいと見なす動物的な本能の道は、天が定めた自然の道である。人間が尊いとする人の道は、天理にかなってはいるが、人の手による作為の道であり、自然そのものではない」

- 1787年9月4日~1856年11月17日
- 日本出身
- 経世論、農政家、思想家、実践的儒学者
原文
「人を賤む所の畜道は天理自然の道なり。尊む所の人道は、天理に順ふといへども、又、作為の道にして、自然にあらず」
現代語訳
「人間が卑しいと見なす動物的な本能の道は、天が定めた自然の道である。人間が尊いとする人の道は、天理にかなってはいるが、人の手による作為の道であり、自然そのものではない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、自然と人為(人の作った道徳や秩序)の本質的な違いを説いている。「畜道」とは、動物のように本能に従って生きる生き方であり、それは「賤しむ所」、つまり人間社会では下等とされるが、実は天(自然)の理に最も忠実な生き方であるとされる。一方で「人道」とは、人間が秩序や道徳の名の下に築いた行動規範であり、たしかに「天理に順ふ(順応している)」ようでありながら、それは人為的な作法や制度にすぎず、本来的な自然ではないという視点がここに示されている。
尊徳は、実利と道徳の両立を説いた現実主義の思想家であり、人間社会の秩序を否定するのではなく、それが「作為」であることを正直に認識せよと語っている。つまり、「人道」を守ることは大切であるが、それをあたかも自然の真理であるかのように絶対視すべきではないという戒めが含まれている。これは、自然の力や現実の力学を無視した理想論や道徳主義への警告と捉えることができる。
現代でも、法律や道徳が「絶対的な正しさ」とされる場面は多いが、それらはすべて人間の手によって設計された社会的制度であり、絶対的な自然の法則ではない。たとえば、労働や家族の在り方、教育制度なども「人道」として尊ばれるが、それらが時代とともに変化するのは、それらが自然ではなく作為の道だからである。この名言は、人間の理想と自然の現実とのずれを冷静に見つめる視点を与えてくれるものであり、道徳に酔うことなく地に足のついた判断を促している。
「二宮尊徳」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!