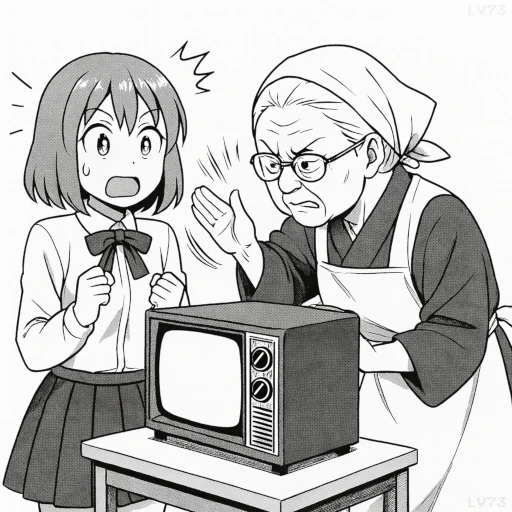「人間を研究するには何か波瀾がある時を択ばないと一向結果が出て来ない」
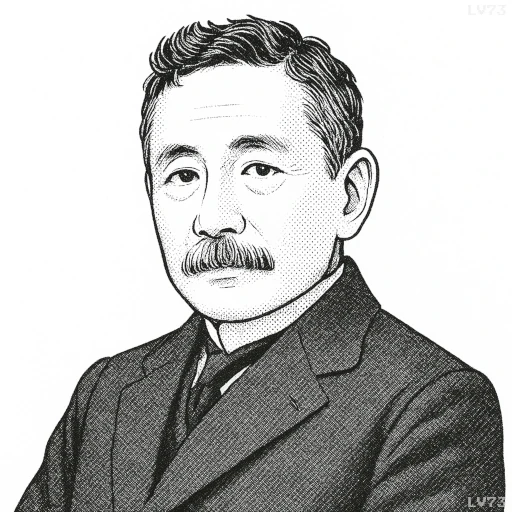
- 1867年2月9日~1916年12月9日(49歳没)
- 日本出身
- 小説家、評論家、英文学者
原文
「人間を研究するには何か波瀾がある時を択ばないと一向結果が出て来ない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、人間の本質を知るためには、平穏な日常ではなく、何らかの波瀾や困難が起きている状況を選ばなければ、真の姿は見えてこないという洞察を示している。波瀾とは、予期せぬ事件や試練、対立など、人の感情や行動が大きく揺さぶられる出来事を指す。
漱石の時代、人間観察は文学や思想の重要な営みであり、特に平常心では隠れている感情や性質が、困難や危機の場面で初めて露わになるという認識は、彼の作品にも色濃く反映されている。静かな日常では、理性や礼儀が人間の本心を覆い隠してしまうため、観察だけでは限界があると考えられていた。
現代においても、この洞察は災害時の人間行動、組織の危機対応、極限状態での心理研究などにそのまま当てはまる。ストレスや困難に直面したときこそ、その人の価値観や本性が明らかになる。漱石のこの言葉は、人間研究における「平時より有事」という視点の重要性を端的に表している。
「夏目漱石」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!