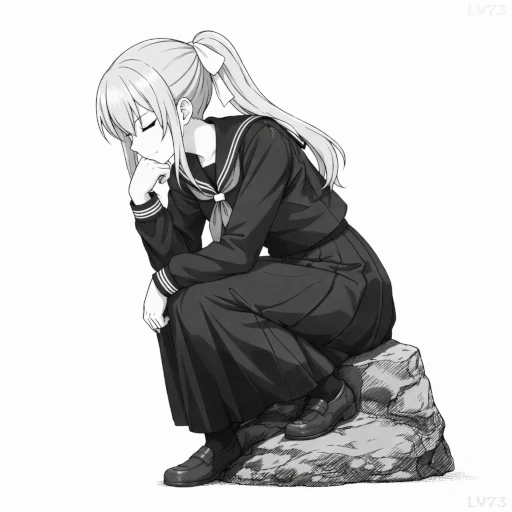「音楽という観念が音楽自体を消すのである」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「音楽という観念が音楽自体を消すのである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が芸術に対する観念化の危険性を鋭く指摘したものである。音楽という純粋な体験そのものではなく、音楽についての観念や理論、固定されたイメージに囚われることによって、本来の音楽の生々しい感動が失われてしまうという警鐘が鳴らされている。ここでは、概念が生の芸術体験を死滅させるという本質的な問題が語られている。
三島は、芸術や美に対して、生きた感覚と直接的な経験を重視していた。彼は、芸術が制度化され、知識や教養として消費されることに強い違和感を持っており、芸術とは理屈ではなく、感じるものであるという立場を鮮明にしていた。この言葉は、三島自身が求めた芸術の原初的な力と、それを損なう文明化への批判を象徴している。
現代においても、この指摘は重要である。たとえば、音楽を理論やジャンル分け、批評によって消費する傾向が強まる中で、本来感動すべき音楽が、観念のフィルターによって無感動なものになってしまう危険は依然として存在する。三島のこの言葉は、芸術の真の力は生きた感受性によってしか味わえないという真理を突きつけ、理屈よりもまず感動を大切にせよと力強く訴えているのである。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!