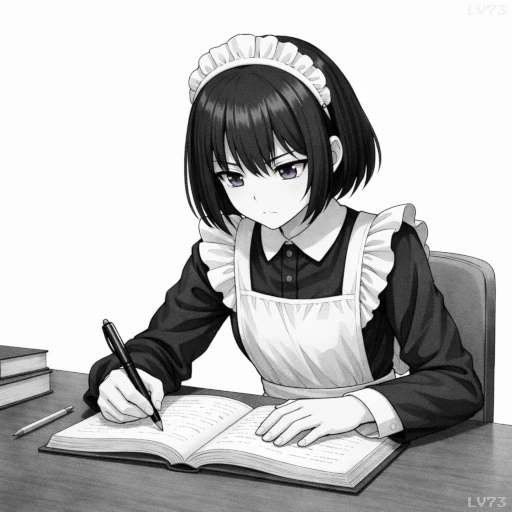「芸術が純粋であればあるほどその分野をこえて他の分野と交流しお互に高めあうものである」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「芸術が純粋であればあるほどその分野をこえて他の分野と交流しお互に高めあうものである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が芸術における純粋性と普遍性の関係を鮮やかに語ったものである。芸術が真に純粋であれば、ジャンルの枠組みにとらわれず、他の分野と自然に交わりながら互いに刺激し合い、高め合う力を持つという認識が示されている。ここでは、純粋さこそが閉鎖ではなく開放と連帯を生む源泉であるという思想が語られている。
三島は、自らが小説、戯曲、評論、さらには武道など多彩な領域にわたって活動する中で、本物の芸術精神は境界を越える普遍性を備えていると確信していた。ジャンルに固執し内向きになる芸術は、むしろ純粋さを失い、真に純粋な芸術は異なる分野と響き合い、さらに豊かな高みへと昇華していくと考えた。この言葉は、三島が持っていた芸術に対する高い理想と広い視野を象徴している。
現代においても、この洞察は重要な意味を持つ。たとえば、文学、音楽、絵画、映画など異なる表現領域が相互に影響を与え、豊かな創造の連鎖を生んでいることは明らかである。三島のこの言葉は、純粋であることを恐れず、他者と交わり高め合うことこそが芸術の本来の姿であると、静かに、しかし力強く教えているのである。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!