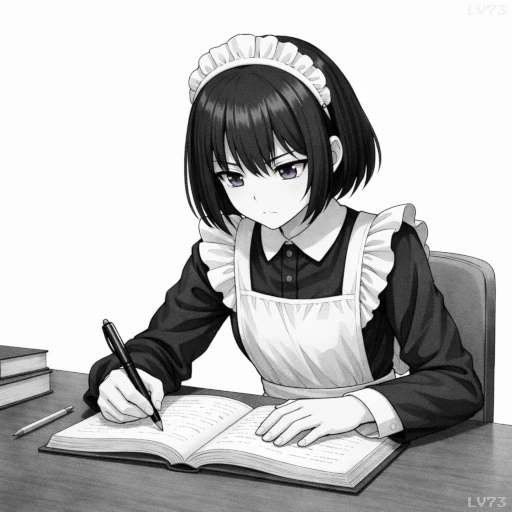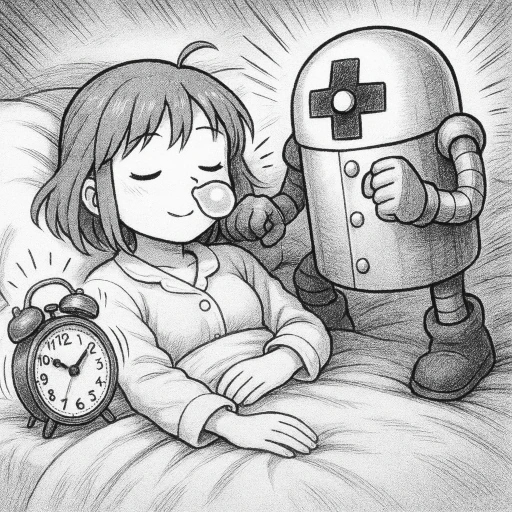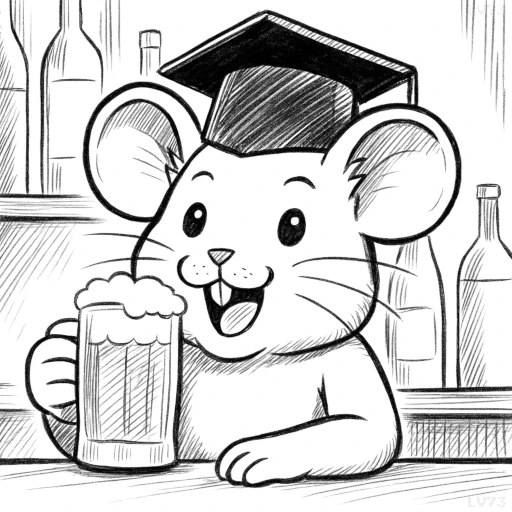「老人は時が酩酊を含むことを学ぶ。学んだときはすでに、酩酊に足るほどの酒は失われている」

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
原文
「老人は時が酩酊を含むことを学ぶ。学んだときはすでに、酩酊に足るほどの酒は失われている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、三島由紀夫が時間と老いに対する認識の皮肉な遅れを鋭く捉えたものである。若いころには気づかずに通り過ぎていた時間の陶酔性や豊かさを、老人になってようやく理解するが、そのときにはもはや十分に酔えるだけの時間も、情熱も失われてしまっているという哀感が語られている。ここでは、人生の取り返しのつかなさと、時間の本質への遅すぎる目覚めが表現されている。
三島は、若さが持つ無自覚な豊かさと、老いがもたらす痛切な認識とのギャップを冷徹に見つめていた。つまり、本当の価値は、失われてはじめてその重さに気づくということである。この言葉は、三島が持っていた人生の不可逆性と、取り返しのきかないものへの鋭い哀惜を象徴している。
現代においても、この考え方は深く共感を呼ぶ。たとえば、若いころには無駄に思えた時間や感情が、後になってかけがえのないものだったと気づくことは誰しも経験する。三島のこの言葉は、人生の陶酔は一度きりであり、それに気づくときにはすでに手遅れであるという、静かでありながらも力強い真理を私たちに伝えているのである。
「三島由紀夫」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!