三島由紀夫

- 1925年1月14日~1970年11月25日
- 日本出身
- 小説家、劇作家、評論家、政治活動家
人物像と評価
三島由紀夫は、戦後日本を代表する作家・劇作家・思想家であり、華麗な文体と深い美学をもって文学と行動を結びつけた人物である。
代表作には『金閣寺』『仮面の告白』『豊饒の海』四部作などがあり、生と死、美と滅びを主題とする作品で国際的にも高く評価された。
文壇のみならず、自衛隊体験を経て民兵組織「楯の会」を結成し、天皇制と武士道を掲げて現代日本の精神的空洞を批判した。
1970年、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地にて決起の演説後に割腹自殺を遂げたその行動は、国内外に大きな衝撃を与えた。
天才的作家であると同時に、過激な思想家として賛否を呼び、今なお文学・思想の両面で論争と関心の対象であり続けている。
「いいね」
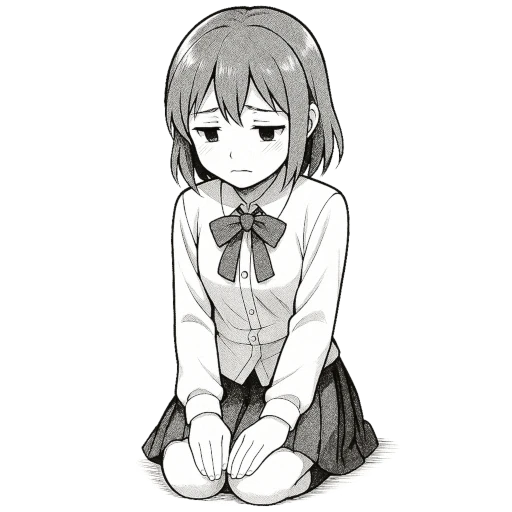
「いいね」が足りてない…
引用
- 「愛から嫉妬が生まれるように、嫉妬から愛が生まれることもある」
- 「『愛している』という経文の読誦は、無限の繰り返しのうちに、読み手自身の心に何かの変質をもたらすものだ」
- 「愛情なんぞに比べれば、憎悪のほうがずっと力強く人間を動かしているんだからね」
- 「愛するということにかけては、女性こそ専門かで、男性は永遠の素人である」
- 「愛というものは共有物の性質をもっていて所有の限界があいまいなばかりに多くの不幸を惹き起すのであるらしい」
- 「愛とは、暇と心と莫大なエネルギーとを要するものです」
- 「愛の奥処には、寸分たがわず相手に似たいという不可能な熱望が流れていはしないだろうか?」
- 「愛の背理は、待たれているものは必ず来ず、望んだものは必ず得られず、しかも来ないこと得られぬことの原因が、正に待つこと望むこと自体にあるという構造を持っている」
- 「愛は絶望からしか生まれない。精神対自然、こういう了解不可能なものへの精神の運動が愛なのだ」
- 「愛は断じて理解ではない」
- 「愛はみんな怖しいんですよ、愛には法則がありませんから」
- 「悪魔の発明は神の衛生学だ」
- 「明日を怖れている快楽などは、贋物でもあり、恥ずべきものではないだろうか」
- 「新しさが『発見』であるとするならば、発見ほど既存を強く意識させるものはない筈だ」
- 「あらゆる英雄主義を滑稽なものとみなすシニシズムには、必ず肉体的劣等感の影がある」
- 「あらゆる改革者には深い絶望がつきまとう。しかし、改革者は絶望を言わないのである」
- 「あらゆる芸術ジャンルは、近代後期、すなわち浪漫主義のあとでは、お互いに気まずくなり、別居し、離婚した」
- 「あらゆる批判と警戒の冷水も、真の陶冶されたる熱情を昻めこそすれ、決してもみ消してしまうものではない」
- 「ある女は心で、ある女は肉体で、ある女は脂肪で夫を裏切るのである」
- 「或る種の瞬間の脆い純粋な美の印象は、凡庸な形容にしか身を委さないものである」
- 「或る小説がそこに存在するおかげで、どれだけ多くの人々が告白を免かれていることであろうか」
- 「生きてるあいだだけでも、二本足でしっかり地面を踏んでいるもんだ」
- 「生きる意志の欠如と楽天主義との、世にも怠惰な結びつきが人間というものだ」
- 「生きるということは、運命の見地に立てば、まるきり詐欺にかけられているようなものだった」
- 「いくら『文武両道』などと云ってみても、本当の文武両道が成立つのは、死の瞬間にしかないだろう」
- 「意志とは、宿命の残り滓ではないだろうか」
- 「偉大な戯曲がそうであるように、偉大な文学も亦、独白に他ならぬ」
- 「今の世の中で本当の恋を証拠立てるには、きっと足りないんだわ、そのために死んだだけでは」
- 「動いていない人間の顔って、何て醜いんだろう」
- 「ウソも遠くからは美しく見える」
- 「美しい身なりをして、美しい顔で町を歩くことは、一種の都市美化運動だ」
- 「美しい者になろうという男の意志は、同じことをねがう女の意志とはちがって、必ず『死への意志』なのだ」
- 「裏切る心配のない見えない神様などを信じてもつまりませんわ」
- 「運命はその重大な主題を、実につまらない小さいものにおしかぶせている場合があります」
- 「多くの感じやすさは、自分が他人に感じるほどのことを、他人は自分に感じないという認識で軽癒する」
- 「お節介は人生の衛生術の一つです」
- 「男が女より強いのは、腕力と知性だけで、腕力も知性もない男は、女にまさるところは一つもない」
- 「男には屢々見るが女にはきわめて稀なのが偽悪者である」
- 「男の虚栄心は、虚栄心がないように見せかけることである」
- 「男の嫉妬の本当のギリギリのところは、体面を傷つけられた怒りだと断言してもよろしい」
- 「衰えることが病であれば、衰えることの根本原因である肉体こそ病だった」
- 「およそ自慢のなかで、喧嘩自慢ほど罪のないものはない」
- 「音楽という観念が音楽自体を消すのである」
- 「音楽は夢に似ている。と同時に、夢とは反対のもの、一段とたしかな覚醒の状態にも似ている」
- 「女が男にだまされることなんぞ、一度だって起こりはいたしません」
- 「女方こそ、夢と現実との不倫の交わりから生れた子なのである」
- 「女の美しさが、男の一番醜い欲望とじかにつながっている、ということほど、女にとって侮辱はないわ」
- 「女の貞淑というものは、時たま良人のかけてくれるやさしい言葉や行いへの報いではなくて、良人の本質に直に結びついたものであるべきだ」
- 「女はあらゆる価値を感性の泥沼に引きずり下ろしてしまう」
- 「女は自分以外のものにはなれないのである。というより実にお手軽に『自分自身』になりきるのだ」
- 「確信がないという確信はいちばん動かしがたいものを持っている」
- 「悲しいことに、われわれは、西欧を批評するというその批評の道具をさえ、西欧から教わったのである」
- 「悲しみとは精神的なものであり、笑いとは知的なものであります」
- 「金でたのしみが買えないと思っているのは、センチメンタルな金持だけです」
- 「金のためだって!そんな美しい目的のためには文学なんて勿体ない」
- 「神が人間の悲しみに無縁であると感ずるのは若さのもつ酷薄であろう」
- 「神は人間の最後の言いのがれであり、逆説とは、もしかすると神への捷径だ」
- 「空井戸を中心にしたすてきな理想的な家庭」
- 「変り者と理想家とは、一つの貨幣の両面であることが多い」
- 「傷つきやすい人間ほど、複雑な鎖帷子を織るものだ。そして往々この鎖帷子が自分の肌を傷つけてしまう」
- 「傷を負った人間は間に合わせの繃帯が必ずしも清潔であることを要求しない」
- 「欺瞞のほうがお伽噺よりも、人間を賢くするものだ」
- 「逆説はその場のがれにこそなれ、本当の言いのがれにはなりえない」
- 「強大な知力は世界を再構成するが、感受性は強大になればなるほど、世界の混沌を自分の裡に受容しなければならなくなる」
- 「虚栄心を軽蔑してはならない。世の中には壮烈きわまる虚栄心もあるのである」
- 「キリストが独創的だったのは、彼の生活のためではなく、磔刑という運命のためだ」
- 「近代が発明したもろもろの幻影のうちで、『社会』というやつはもっとも人間的な幻影だ」
- 「近代の唯一の武器は皮肉(シニスム)だ」
- 「近代ヒューマニズムを完全に克服する最初の文学はSFではないか」
- 「空虚な目標であれ、目標をめざして努力する過程にしか人間の幸福が存在しない」
- 「崩れたもの、形のないもの、盲いたもの、・・・・・・それは何だと思う。それこそは精神のすがただ」
- 「苦痛の明晰さには、何か魂に有益なものがある」
- 「芸術が純粋であればあるほどその分野をこえて他の分野と交流しお互に高めあうものである」
- 「芸術家というのは自然の変種です」
- 「芸術家の値打の分れ目は、死んだあとに書かれる追悼文の面白さで決る」
- 「芸術家は創造にだけ携わるのではない。破壊にも携わるのだ」
- 「芸術家は、ペリカンが自分の血で子を養うと云われるように、自分の血で作品の存在性をあがなう」
- 「芸術作品の感動がわれわれにあのように強く生を意識させるのは、それが死の感動だからではあるまいか」
- 「芸術作品の形成がそもそも死と闘い死に抵抗する営為なのである」
- 「芸術というのは巨大な夕焼です。一時代のすべての佳いものの燔祭です」
- 「芸術とは物言わぬものをして物言わしめる腹話術に他ならぬ。この意味でまた、芸術とは比喩であるのである」
- 「芸術とは私にとって私の自我の他者である」
- 「芸術によって解決可能な事柄は存在しない」
- 「芸術はすべて何らかの意味で、その扱っている素材に対する批評である」
- 「芸術は認識の冷たさと行為の熱さの中間に位し、この二つのものの媒介者であろう」
- 「軽蔑とは、女の男に対する永遠の批評なのであります」
- 「決して人に欺されないことを信条にする自尊心は、十重二十重の垣を身のまわりにめぐらす」
- 「結晶した悪は、白い錠剤のように美しい」
- 「決定されているが故に僕らの可能性は無限であり、止められているが故に僕らの飛翔は永遠である」
- 「潔癖さというものは、欲望の命ずる一種のわがままだ」
- 「衒気のなかでいちばんいやなものが無智を衒うことだ」
- 「健康な青年にとって、おそらく一等緊急な必要は『死』の思想だ」
- 「現状維持というのは、つねに醜悪な思想であり、また、現状破壊というのは、つねに飢え渇いた貧しい思想である」
- 「建設よりも破壊のほうが、ずっと自分の力の証拠を目のあたり見せてくれるものだった」
- 「現代社会のもっとも有効な力は、知力である」
- 「現代では何かスキャンダルを餌にして太らない光栄というものはほとんどありません」
- 「現代の人間社会は、血に飢えている」
- 「幻滅に対して、もっと強い幻滅が、効力のある薬餌になる場合もあろう」
- 「恋と犬とはどっちが早く駈けるでしょう。さてどっちが早く汚れるでしょう」
- 「行為に行為たる性質を力強く保証するような、それだけの価値ある目的や思想が現代に存在するか?」
- 「好奇心には道徳がないのである。もしかするとそれは人間のもちうるもっとも不徳な欲望かもしれない」
- 「行動は一瞬に火花のように炸裂しながら、長い人生を要約するふしぎな力を持っている」
- 「幸福がつかのまだという哲学は、不幸な人間も幸福な人間もどちらも好い気持にさせる力を持っている」
- 「幸福って、何も感じないことなのよ。幸福って、もっと鈍感なものなのよ」
- 「告白癖のある友人ほどうるさいものはない」
- 「個性などというものは、はじめは醜い、ぶざまな格好をしているものだ」
- 「骨肉の情愛というものは、一度その道を曲げられると、おそろしい憎悪に変わってしまう」
- 「孤独が今日の青年の置かれた状況であって、青年の役割はそこにしかない」
- 「この世界には不可能という巨きな封印が貼られている」
- 「この世で最も怖ろしい孤独は、道徳的孤独である」
- 「この世には人間の信頼にまさる化け物はないのだ」
- 「この世の絶頂の幸せが来たとき、その幸福の只中でなくては動かぬ思案があるのです」
- 「この世のもっとも純粋なよろこびは、他人のよろこびを見ることだ」
- 「この世は不完全な人間の陽画(ポジティブ)に充ちている」
- 「コムプレックスとは、作家が首吊りに使う踏台なのである」
- 「今日、伝統という言葉は、ほとんど一種のスキャンダルに化した」
- 「今夜が最後と思えば、話なんていくらだってあります」
- 「作品というものは作者の身幅に合った衣裳であってはならない」
- 「作家の芸術的潔癖が、直ちに文明批評につながることは、現代日本の作家の宿命でさえある」
- 「作家は一度は、時代とベッドを共にした経験をもたねばならず、その記憶に鼓舞される必要があるようだ」
- 「作家は末期の瞬間に自己自身になりきった沈黙を味わうがために一生を語りつづけ喋りつづける」
- 「殺人者は造物主の裏。その偉大は共通、その歓喜と憂鬱は共通である」
- 「淋しさというものは人間の放つ臭気の一種だよ」
- 「自意識が強いから愛せないなんて子供じみた世迷い言で、愛さないから自意識がだぶついてくるだけのことです」
- 「仕事に熱中している男は美しく見えるとよく云われるが、もともと美しくもない男が仕事に熱中したって何になるだろう」
- 「自殺とは錬金術のように、生という鉛から死という黄金を作り出そうとねがう徒なのぞみであろうか」
- 「思春期にある潔癖感は、多く自分を不潔だと考えることから生れてくる」
- 「詩人とは、自分の青春に殉ずるものである。青春の形骸を一生引きずってゆくものである」
- 「姿勢を崩さなければ見えない真実がこの世にはあることを、私とて知らぬではない」
- 「死の観念はやはり私の仕事のもっとも甘美な母である」
- 「芝居の世界は実に魅力があるけれど、一方、おそろしい毒素を持っている」
- 「自分の我意に対して、それを否定する力のあることを実感するほど、自我形成に役立つものはない」
- 「自分の顔と折合いをつけながら、だんだんに年をとってゆくのは賢明な方法である」
- 「自分の死の分量を明確に見極めた人が、これからの世界で本当に勇気を持った人間になるだろう」
- 「自分のメチエの限界をよく知り、決してそれについて夢を見ない作家は、果して幸福だろうか」
- 「自分の持たないものの悪口は言いやすい」
- 「詩もなく、至福もなしに!これがもっとも大切だ。生きることの秘訣はそこにしかない」
- 「秀才バカというやつは、バカ病の中でも最も難症で、しかも世間にめずらしくありません」
- 「十代の時代ほど誠実そのもの顔をしたがるくせに、自分に対してウソをついている時代はない」
- 「羞恥心のない知性は、羞恥心のない肉体よりも一そう醜い」
- 「守勢に立つ側の辛さ、追われる者の辛さからは、容易ならぬ狡知が生れる」
- 「純粋で美しい者は、そもそも人間の敵なのだということを忘れてはいけない」
- 「小説家が苦悩の代表者のような顔をするのは変だ」
- 「小説家と外科医にはセンチメンタリズムは禁物だ」
- 「小説家における文体とは、世界解釈の意志であり鍵なのである」
- 「小説家の心は広大で、飛行場もあれば、中央停車場もある」
- 「小説家を尊敬するなかれ」
- 「小説の世界では、上手であることが第一の正義である」
- 「小説は書いたところで完結して、それきり自分の手を離れてしまうが、芝居は書き了えたところからはじまる」
- 「少年期と青年期の堺のナルシシズムは、自分のために何をでも利用する。世界の滅亡をでも利用する」
- 「少年というものは独楽なのだ」
- 「処女にだけ似つかわしい種類の淫蕩さというものがある。それは成熟した女の淫蕩さとはことかわり、微風のように人を酔わせる」
- 「女性は抽象精神とは無縁の徒である」
- 「新人の辛さは『待たされる』辛さである」
- 「人生が車の運転と同様に、慎重一点張りで成功するなどと思われてたまるものか」
- 「人生では知らないことだけが役に立つので、知ってしまったことは役にも立たない」
- 「人生という邪教、それは飛切りの邪教だわ」
- 「人生のいちばんはじめから、人間はずいぶんいろんなものを諦らめる。生れて来て何を最初に教わるって、それは『諦らめる』ことよ」
- 「人生のさかりには、無理と思われるものもすべて叶い、覚束なく見えるものもすべて成るのだよ」
- 「人生は音楽ではない。最上のクライマックスで、巧い具合に終わってくれないのが人生というものである」
- 「真の矜恃はたけだけしくない。それは若笹のように小心だ」
- 「真の芸術家は招かれざる客の嘆きを繰り返すべきではあるまい。彼はむしろ自ら客を招くべきであろう」
- 「すぐれた芸術作品はすべて自然の一部をなし、新らしく創られた自然に他ならない」
- 「すべてのスポーツには、少量のアルコールのように、少量のセンチメンタリズムが含まれている」
- 「すべての人の上に厚意が落ちかかる日があるように、すべての人の上に悪意が落ちかかる日があるものだ」
- 「生活よりも高次なものとして考えられた文学のみが、生活の真の意味を明かしてくれるのだ」
- 「清潔なものは必ず汚され、白いシャツは必ず鼠色になる」
- 「政治とは他人の憎悪を理解する能力なんだよ。この世を動かしている百千百万の憎悪の歯車を利用して、それで世間を動かすことなんだよ」
- 「青春以後の芸術家の半生は青春の意味を訊ねることに費やされる」
- 「青春が無意識に生きることの莫大な浪費。収穫を思わぬその一時期」
- 「青春の特権といえば、一言を以てすれば、無知の特権であろう」
- 「青春の一つの滴のしたたり、それがただちに結晶して、不死の水晶にならねばならぬ」
- 「精神と肉体とは決して問答できないのだ。精神は問うことができるだけだ」
- 「精神の想像力とは疑問を想像する力なんだ」
- 「精神は、・・・・・・まあいわば、零を無限に集積して一に達しようとする衝動だといえるだろう」
- 「精神を凌駕することのできるのは習慣という怪物だけなのだ」
- 「性と解放と牢獄との三つのパラドックスを総合するには芸術しかない」
- 「生に煩わされず、生に蝕まれない鉄壁の青春。あらゆる時の侵蝕に耐える青春」
- 「青年にとって反抗は生で、忠実は死だ」
- 「青年の冒険を、人格的表徴とくっつけて考える誤解ほど、ばかばかしいものはない」
- 「青年の、暴力を伴わない礼儀正しさはいやらしい。それは礼儀を伴わない暴力よりももっと悪い」
- 「生への媚態なしにわれわれは生きえぬのだろうか」
- 「世界がなかなか崩壊しないということこそ、その表面をスケーターのように滑走して生きては死んでゆく人間にとっては、ゆるがせにできない問題だった」
- 「世間が若い者に求める役割は、欺され易い誠実な聴き手ということで、それ以上の何ものでもない」
- 「世間は決して若者に才智を求めはしないが、同時に、あんまり均衡のとれた若さというものに出会うと、頭から疑ってかかる傾きがある」
- 「絶望から人はむやみと死ぬものではない」
- 「全然愛していないということが、情熱の純粋さの保証になる場合があるのだ」
- 「戦争中に死んでいれば、私は全く無意識の、自足的なエロスの内に死ぬことができたのだ」
- 「戦争は決して私たちに精神の傷を与えはしなかった。のみならず私たちの皮膚を強靱にした。面の皮もだが、おしなべて私たちの皮膚だけを強靱にした。傷つかぬ魂が強靱な皮膚に包まれているのである。不死身に似ている」
- 「想像力というものは、多くは不満から生れるものである。あるいは、退屈から生れるものである」
- 「存在よりもさきに精髄が、現実よりもさきに夢幻が、現前よりもさきに予兆が、はっきりと、より強い本質を匂わせて、現れ漂っているような状態、それこそは女だった」
- 「退屈な人間は地球の屑屋に売り払うことだって平気でするのだ」
- 「大体、時代というものは、自分のすぐ前の時代には敵意を抱き、もう一つ前の時代には親しみを抱く傾きがある」
- 「怠惰の言訳としてしか言葉を使わぬ人間がいるものだ」
- 「頽廃した純潔は、世の凡ゆる頽廃のうちでも、いちばん悪質の頽廃だ」
- 「高飛車な物言いをするとき、女はいちばん誇りを失くしているんです」
- 「ただ耐えること、しかも矜恃を以て耐えること、それも亦、ヒロイズムだった」
- 「楽しみというものは死とおんなじで、世界の果てからわれわれを呼んでいる」
- 「足るを知る人間なんか誰一人いないのが社会で、それでこそ社会は生成発展するのである」
- 「誰も愛さないから、誰からも傷を負わない」
- 「誰も死に打ち克つことができないとすれば、勝利の栄光とは、純現世的な栄光の極致にすぎない」
- 「男性操縦術の最高の秘訣は、男のセンチメンタリズムをギュッとにぎることだ」
- 「耽溺という過程を経なければ獲得できない或る種の勇気があるものである」
- 「知識人の顔というのは何と醜いのだろう!」
- 「知識人の唯一の長所は自意識であり、自分の滑稽さぐらいは弁えていなくてはならぬ」
- 「ちっぽけな希望に妥協して、この世界が、その希望の形のままに見えて来たらおしまいだ」
- 「血も花も、枯れやすく変質しやすい点でよく似ている」
- 「ちょうど年寄りの盆栽趣味のように、美というものは洗練されるについて、一種の畸型を求めるようになる」
- 「直感というものは人との交渉によってしか養われぬものだった。それは本来想像力とは無縁のものだった」
- 「追憶は『現在』のもっとも清純な証なのだ」
- 「貞女とは、多くのばあい、世間の評判であり、その世間をカサに着た女の鎧であります」
- 「典型的な青年は、青春の犠牲になる。十分に生きることは、生の犠牲になることなのだ」
- 「どうしたら若いうちに死ねるだろう、それもなるたけ苦しまずに」
- 「同志は、言葉によってではなく、深く、ひそやかに、目を見交わすことによって得られるのにちがいない」
- 「どうでもいいことは流行に従うべきで、流行とは、『どうでもいいものだ』ともいえましょう」
- 「道徳的感覚というものは、一国民が永年にわたって作り出す自然の芸術品のようなものであろう」
- 「道徳は、習慣からの逃避もみとめないが、同時に、習慣への逃避も、それ以上にみとめていないのだ」
- 「時々、窓のなかは舞台に似ている」
- 「時の流れは、崇高なものを、なしくずしに、滑稽なものに変えていく」
- 「独創性は真の普遍性の海のなかでしか発見されぬ真珠である」
- 「どこの社会にも、誰が見ても不適任者と思われる人が、そのくせ恰かも運命的にそこに居据っているのを見るものだ」
- 「年をとらせるのは肉体じゃなくって、もしかしたら心かもしれないの。心のわずらいと衰えが、内側から体に反映して、みにくい皺やしみを作ってゆくのかもしれないの」
- 「飛ぶ人間を世間はゆるすことができない」
- 「とり交わしすぎた恋文の魔力はお互がいの魂を老いさせる」
- 「トルストイがどんなに天才だろうと、暇がなければ『戦争と平和』なんて読めたものではない」
- 「どんな浅薄な流行でも、それがおわるとき、人々は自分の青春と熱狂の一部分を、その流行と一緒に、時間の墓穴へ埋めてしまう」
- 「どんな人間にもおのおののドラマがあり、人に言えぬ秘密があり、それぞれの特殊事情がある」
- 「治りたがらない病人などには本当の病人の資格がない」
- 「何かを拒絶することは又、その拒絶のほうへ向って自分がいくらか譲歩することでもある」
- 「何事かの放棄による所有、それこそは青年の知らぬ所有の秘訣だ」
- 「ナルシスは、その並々ならぬ誇りのために、却って不出来な鏡を愛する場合がある」
- 「西も東もわからぬ子どもに、『どっちへ行ってもいいよ』と言えば、迷い児がふえるだけのことである」
- 「人間性に、忘却と、それに伴う過去の美化がなかったとしたら、人間はどうして生に耐えることができるであろう」
- 「人間と世界に対する嫌悪の中には必ず陶酔がひそむ」
- 「人間には憎んだり、戦ったり、勝ったり、そういう原始的な感情がどうしても必要なんだ」
- 「人間の感情の振幅を無限に拡大すれば、それは自然の感情になり、ついには摂理になる」
- 「人間の情熱は、一旦その法則に従って動き出したら、誰もそれを止めることはできない」
- 「人間の道徳とは、実に単純な問題、行為の二者択一の問題なのです。善悪や正不正は選択後の問題にすぎません」
- 「人間は安楽を百パーセント好きになれない動物なのです。特に男は」
- 「人間は結局、前以て自分を選ぶものだ」
- 「人間は自分より永生きする家畜は愛さないものだ。愛されることの条件は、生命の短かさだった」
- 「人間を統治するのは簡単なことで、人間の内部の虚無と空白を統括すればそれですむのだ」
- 「認識の目から見れば、世界は永久に不変であり、そうして永久に変貌するんだ」
- 「認識は生の耐えがたさがそのまま人間の武器になったものだが、それで以て耐えがたさは少しも軽減されない」
- 「年少であることは何という厳しい恩寵であろう」
- 「能は、いつも劇の終ったところからはじまる」
- 「莫迦げ切った目的のために死ぬことが出来るのも若さの一つの特権である」
- 「初恋に勝って人生に失敗するのはよくある例で、初恋は破れる方がいいという説もある」
- 「花作りというものにはみんな復讐の匂いがする」
- 「母親に母の日を忘れさすこと、これ親孝行の最たるものといえようか」
- 「微笑とは、決して人間を容認しないという最後のしるし、弓なりの唇が放つ見えない吹矢だ」
- 「必要から生れたものには、必要の苦さが伴う」
- 「美ということだけを思いつめると、人間はこの世で最も暗黒な思想にしらずしらずぶつかるのである」
- 「ひどい暮しをしながら、生きているだけでも仕合せだと思うなんて、奴隷の考えね」
- 「人並な安楽な暮しをして、生きているのが仕合せだと思っているのは、動物の感じ方ね」
- 「人のおどろく顔を見るというたのしみは、たのしみの極致を行くものである」
- 「人は最後の一念によって生を引く」
- 「美とは到達できない此岸なのだ」
- 「美とは人間における自然、人間的条件の下に置かれた自然なんだ」
- 「人を悪徳に誘惑しようと思う者は、大ていその人の善いほうの性質を百パーセント利用しようとします」
- 「美の廃址を見るのも怖いが、廃址にありありと残る美を見るのも怖い」
- 「美は秀麗な奔馬である」
- 「美は鶴のように甲高く鳴く。その声が天地に谺してたちまち消える」
- 「秘密というものはたのしいもので、悩みであろうが喜びであろうが、同じ色に塗りたくってしまいます」
- 「表現だけが現実に現実らしさを与えることができるし、リアリティーは現実の中にはなく表現の中にだけある」
- 「不安こそ、われわれが若さから竊みうるこよない宝だ」
- 「不安自体はすこしも病気ではないが、『不安をおそれる』という状態は病的である」
- 「『武』とは花と散ることであり、『文』とは不朽の花を育てることだ」
- 「不良化とは、稚心を去る暴力手段である」
- 「文学に対する情熱は大抵春機発動期に生れてくるはしかのようなものである」
- 「文学の真の新らしさは読者自身をも新らしくするものではあるまいか」
- 「文学は、どんなに夢にあふれ、又、読む人の心に夢を誘い出そうとも、第一歩は、必ず作者自身の夢が破れたところに出発している」
- 「文化とは、雑多な諸現象に統一的な美意識に基づく『名』を与えることなのだ」
- 「忘却の早さと、何ごとも重大視しない情感の浅さこそ、人間の最初の老いの兆だ」
- 「法律とは、人生を一瞬の詩に変えてしまおうとする欲求を、不断に妨げている何ものかの集積だ」
- 「僕らは嘗て在ったもの凡てを肯定する。そこに僕らの革命がはじまるのだ」
- 「本当の危険とは、生きているというそのことの他にはありゃしない」
- 「本当の美とは人を黙らせるものであります」
- 「まかりまちがえばいつでも被告になりうる人間、それこそは唯一種類の現実性のある人間だった」
- 「窓の外から眺める他人の不幸は、窓の中で見るそれよりも美しい」
- 「守る側の人間は、どんなに強力な武器を用意していても、いつか倒される運命にあるのだ」
- 「夢想は人の考えているように精神の作用であるのではない。それはむしろ精神からの逃避である」
- 「夢想は私の飛翔を、一度だって妨げはしなかった」
- 「無秩序が文学に愛されるのは、文学そのものが秩序の化身だからだ」
- 「もろもろの記憶のなかでは、時を経るにつれて、夢と現実とは等価のものになっていく」
- 「優雅、文化、人間の考える美的なもの、そういうものすべての実相は不毛な無機的なものなんだ」
- 「夢とちがって、現実は何という可塑性を欠いた素材であろう」
- 「陽気な女の花見より、悲しんでいる女の花見のほうが美しい」
- 「余計者たるに悩むことは、人間たるに悩むことと同然である」
- 「余人にはわかるまい。無感覚というものが強烈な痛みに似ていることを」
- 「世の中って、真面目にしたことは大てい失敗するし、不真面目にしたことはうまく行く」
- 「恋愛では手放しの献身が手放しの己惚れと結びついている場合が決して少なくない」
- 「老人はいやでも政治的であることを強いられる」
- 「老人は時が酩酊を含むことを学ぶ。学んだときはすでに、酩酊に足るほどの酒は失われている」
- 「老夫妻の間の友情のようなものは、友情のもっとも美しい芸術品である」
- 「若い男の肌はつやつやしていて気味がわるい」
- 「若い世代は、代々、その特有な時代病を看板にして次々と登場して来たのだった」
- 「若いやつの死だけが、豪勢で、贅沢なのさ。だって残りの一生を一どきに使っちゃうんだものな」
- 「我が国の芸術界は完成と未完成の二つしか評語を知らない」
- 「若さが幸福を求めるなどというのは衰退である」
- 「われわれが思想と呼んでいるものは、事前に生れるのではなく、事後に生れるのである」
- 「我々が深部に於て用意されている大きな変革に気附くまでには時間がかかる」
- 「われわれが住んでいる時代は政治が歴史を風化してゆくまれな時代である」
- 「われわれが文明の利便として電気洗濯機を利用することと、水爆を設計した精神とは無縁ではない」
- 「われわれが未来を怖れるのは、概して過去の堆積に照らして怖れるのである」
- 「われわれの古典文学では、紅葉や桜は、血潮や死のメタフォアである」
- 「われわれは言葉が現実を蝕むその腐食作用を利用して作品を作るのである」
- 「われわれは人生を自分のものにしてしまうと、好奇心も恐怖もおどろきも喜びも忘れてしまう」
- 「われわれは美の縁のところで賢明に立ちどまること以外に、美を保ち、それから受ける快楽を保つ方法を知らない」