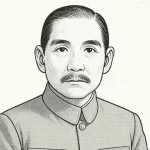「日ごろ部下の言うことをよく聞く人のところでは比較的人が育っている。それに対して、あまり耳を傾けない人の下では人が育ちにくい。そういう傾向があるように思われる」
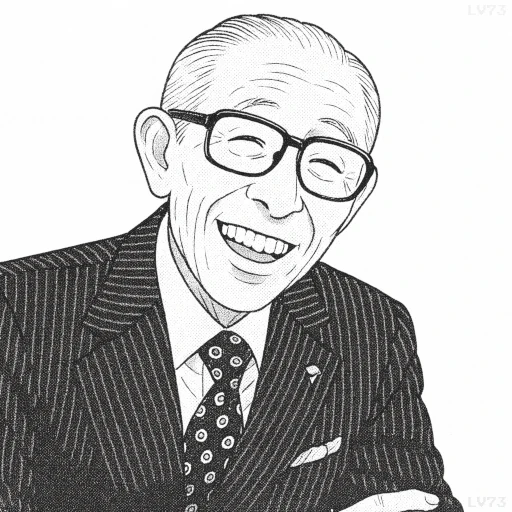
- 1894年11月27日~1989年4月27日(94歳没)
- 日本出身
- 実業家、発明家、パナソニック(松下電器産業)創業者、「経営の神様」
原文
「日ごろ部下の言うことをよく聞く人のところでは比較的人が育っている。それに対して、あまり耳を傾けない人の下では人が育ちにくい。そういう傾向があるように思われる」
出典
人事万華鏡
解説
この言葉は、部下の成長と上司の姿勢との関係について、実感に基づく観察を語っている。指示や命令だけで組織を動かすのではなく、日々の中で部下の声に耳を傾け、真剣に受け止める姿勢が、部下の主体性や成長意欲を引き出すという原理が示されている。逆に、部下の意見を軽んじたり、聞く耳を持たない態度は、組織の活力を損ね、人材の成長を妨げる要因となる。
松下幸之助は、「人間尊重」の経営哲学を掲げており、誰もが何らかの可能性を持っているという信念をもって人材と向き合っていた。そのためには、上に立つ者が謙虚に耳を傾け、部下の考えや疑問に真摯に対応することが不可欠であると考えた。そのような姿勢が、部下に自信と責任感をもたらし、自ら考えて動く力を育てていくのである。
現代の組織論においても、「傾聴」はリーダーシップの中核的な能力とされている。オープンな対話を通じて部下の意見を取り入れることで、現場の課題が浮き彫りになり、意思決定の質も向上する。また、聞かれているという実感は、働く人にとって大きな励みとなり、チーム全体の信頼関係を築く土台となる。人を育てるということは、まずその人の声を真摯に受け止めるところから始まる。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「松下幸之助」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い