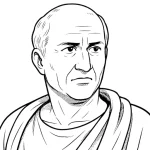「どんなに信じがたいことでも、雄弁によって納得させることができる」

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
英文
”Nothing is so unbelievable that oratory cannot make it acceptable.”
日本語訳
「どんなに信じがたいことでも、雄弁によって納得させることができる」
解説
この言葉は、雄弁術(oratory)が持つ強大な説得力と、人の思考や信念に対する影響力の深さを示すキケロの修辞学的洞察を表す格言である。彼は、理性や真実に基づいているかどうかにかかわらず、言葉の巧みな使い方によって、人々を感情的に揺さぶり、最も信じがたい主張でさえも「もっともらしく」受け入れさせることができると認識していた。つまり、雄弁の力は単なる伝達ではなく、現実の認識そのものを作り出す可能性を持つという警告が含まれている。
この考えは、キケロが『弁論家について(De Oratore)』や『話し方について(Orator)』で展開した、雄弁の本質と責任についての議論と一致する。彼は、優れた弁論家は説得の技術だけでなく、倫理的判断(ethos)と真理への忠誠を伴っていなければならないと強調した。この格言には、言葉の力がいかに人間の判断を操作しうるかという現実に対する畏れと、それゆえに誠実さが必要だという倫理的警鐘が含まれている。
現代においてもこの格言は、政治的レトリック、広告、メディア、プロパガンダの世界においてきわめて重要な意味を持つ。事実に基づかない情報であっても、巧みな言葉や演出によって世論が動かされることがある現代社会では、言葉の「受け手」にも批判的思考が求められる。キケロのこの言葉は、雄弁が人々を善へ導く手段にも、誤導する道具にもなりうることを示す、時代を超えた修辞と倫理の警句である。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「キケロ」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い