マルクス・トゥッリウス・キケロ

- 紀元前106年1月3日~紀元前43年12月7日
- ローマ共和国出身
- 政治家、弁護士、哲学者、雄弁家
人物像と評価
マルクス・トゥッリウス・キケロは、紀元前1世紀のローマ共和政末期を代表する政治家・弁論家・哲学者であり、ラテン文学とローマ法思想に計り知れない影響を与えた人物である。
平民出身ながら弁論術と知性によって政界で頭角を現し、コンスル(執政官)としてカティリナの陰謀を鎮圧するなど、共和政の擁護者として行動した。
政治家としては実践と道徳の一致を重視し、著作においてはストア派やプラトン哲学をラテン語で紹介し、後のヨーロッパ思想の礎を築いた。
一方で、権力闘争の激化するローマにおいては中庸的立場が災いし、最終的にはアントニウスらにより暗殺された。
言論と理性を重んじる古代の良識として、近代以降の法思想や共和主義にも深い影響を与えている。
「いいね」
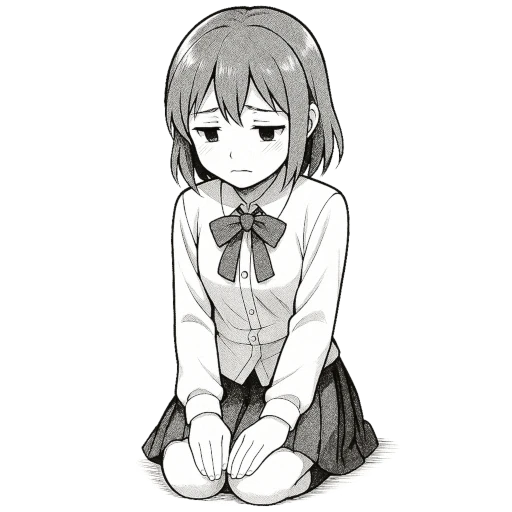
「いいね」が足りない…
引用
- 「正当な理由なく始められた戦争は不正である。復讐または防衛のための戦争だけが正当とされる」
- 「似た者同士は親しくなる」
- 「私はこれを付け加える。教育を受けていない理性の才のほうが、天賦の才能のない教育よりもしばしば人を栄光と徳へと導いてきた」
- 「いかなる偉大な者も、いくらかの神的霊感なしに偉大となった者はいない」
- 「偽りは真実にあまりにも近いため、賢者であってもその狭き境界において自らを信用しないほうがよい」
- 「敵はすでに門内にいる。私たちが戦うべきは、自らの贅沢、自らの愚かさ、自らの犯罪性である」
- 「我々の性格は、人種や遺伝の産物というよりも、自然が我々の習慣を形づくり、我々が養われ生きる環境によってつくられる」
- 「自分の生まれる前に何が起こったかを知らぬ者は、永遠に子どものままである」
- 「教育を受けぬ天賦の才のほうが、天賦の才なき教育よりもしばしば栄光と徳を成し遂げてきた」
- 「自由とは、法律によって許されたことを行う力の中にある」
- 「真の高貴さは、恐れから解き放たれている」
- 「記憶はあらゆるものの宝庫であり、守護者である」
- 「自分にとって価値ある者であった分だけ、他人にとっても価値ある者となるだろう」
- 「許されていることが、常に名誉あることとは限らない」
- 「婚姻を成立させるのは同居ではなく、合意である」
- 「愛とは、美に触発されて友情を結ぼうとする試みである」
- 「無知なおしゃべりよりも、口をつぐんだ知識のほうが好ましい」
- 「憎しみとは、根深くなった怒りである」
- 「それでは自由とは何か。それは、自らの望むままに生きる力である」
- 「おお、哀れな人間よ。おまえが哀れなのは、そのありさまだけでなく、自らがいかに哀れかを知らぬことによっても哀れなのだ」
- 「摂理が人間に授けた賜物のうち、子どもほどに愛しいものが他にあろうか」
- 「ある人から誠実さの評判を奪えば、その人が賢く抜け目ないほどに、より憎まれ、より信用されなくなる」
- 「簡潔さこそが、元老院議員であれ弁論家であれ、言葉にとって最良の推奨である」
- 「若者に老人の分別があるのを称賛するように、老人に若者の心を保つのもまた喜ばしい。これを守る者は、肉体は老いても、精神まで老いることはない」
- 「倹約は大いなる収入である」
- 「偉大なことが成し遂げられるのは、筋力や速さ、身体の器用さによってではなく、熟慮と人格の力、そして判断によってである」
- 「法律は、その趣旨が保たれるように、寛大な解釈で読むべきである」
- 「誓われもせず隠された憎しみは、公然とされた憎しみよりも恐れるべきである」
- 「悲しみに髪をかきむしるのは愚かである。あたかも、禿げることで悲しみが和らぐかのように」
- 「精神が肉体よりも強い限りにおいて、精神に生じる病は、肉体に生じるそれよりも深刻である」
- 「正義とは人に害を加えぬことであり、礼節とは人を不快にさせぬことである」
- 「死者の命は、生者の記憶の中に宿る」
- 「友情を取り去ってしまえば、人生にどれほどの甘美さが残るというのか。人生から友情を奪うことは、世界から太陽を奪うことに等しい。真の友は、血縁よりも尊ばれるべき存在である」
- 「名誉は、徳の報いである」
- 「この全宇宙を、神々と人間が共に属する一つの国家として捉えねばならない」
- 「沈黙は会話における偉大な技術の一つである」
- 「たとえ冗談であっても、友を傷つけてはならない」
- 「時は人の思惑を打ち砕き、自然を確証する」
- 「始める前に、慎重に計画せよ」
- 「我々は賞賛への強い欲求によって動かされており、人が優れていればいるほど、よりいっそう栄光に駆り立てられる。栄光を軽蔑する内容の書を著す哲学者たちすら、その書物に自らの名を記すのだ」
- 「人はなぜ気づかぬのか――倹約がどれほどの収入に匹敵するかということに」
- 「恐怖は、義務を教える永続的な教師とはなり得ない」
- 「忠実ほど高貴であり、敬うに値するものはない。誠実と真実こそ、人間の心に備わる最も神聖な美徳である」
- 「老年とは人生の冠にして、我らの劇の最終幕である」
- 「偽りとは、真実の模倣にすぎない」
- 「ときには何もしない時間を持てない人は、真に自由な人とは言えない」
- 「目は、見張りのように身体の最も高い位置を占めている」
- 「火が水に投げ込まれて冷やされ、消え去るように、潔白で最も高潔な人物に対する虚偽の告発もまた、泡立ち、すぐに消散し、天と海の脅威すらも空しく終わる――本人は微動だにせずに立ち続けている」
- 「人の魂が不滅であると信じることにおいて、もし私が誤っているのだとしても、私は喜んでその誤りに身をゆだねる。生きているかぎり、私に喜びを与えてくれるこの誤りを誰にも取り上げられたくはない」
- 「乱れた精神においては、乱れた身体と同様に、健全な健康はあり得ない」
- 「すべての肉体において個々の魂とともに遍在する超魂(Supersoul)を見、魂も超魂も決して滅びることがないと理解する者こそ、真に見る者である」
- 「真の栄光は根を張り、広がっていく。すべての偽りの見せかけは花のように地に落ち、偽物は長くは続かない」
- 「人民の安全こそが、最高の法である」
- 「誠実なやりとりにおいて大切なのは、自分が何を言ったかや考えたかではなく、何を意図していたかである」
- 「栄光は徳の影のように、それに従って現れる」
- 「誰にでも誤りはある。しかし、その誤りに固執するのは愚か者だけである」
- 「涙はすぐに乾く――とりわけ、それが他人の不幸のために流されたものであればなおさらである」
- 「顔つきは魂の肖像であり、目はその意志を映し出すものである」
- 「人が高貴であればあるほど、他者の劣悪さを疑うことが難しくなる」
- 「不可能なことを行う義務には、拘束力はない」
- 「勇敢なる者として生きよ。そしてもし運命が逆風を吹かせるなら、その打撃を勇気ある心で迎え撃て」
- 「民の幸福こそが、最も偉大な法である」
- 「老年における助言は愚かである。旅の終わりに近づいているというのに、道中のための荷を増やすことほど馬鹿げたことがあるだろうか」
- 「すべてにおいて、真実は模倣や写しを凌駕する」
- 「人々は、倹約がいかに大きな収入であるかを理解していない」
- 「自信とは、心が偉大で高貴な道に乗り出す際に、確かな希望と自己への信頼をもって抱く感情である」
- 「自然は消滅を嫌う」
- 「誤るのはすべての人間の性である。しかし、誤りに固執するのは愚か者だけである」
- 「自分より優れた者がいると信じた詩人や雄弁家など、かつて存在したためしはない」
- 「他人の欠点には気づくが、自らの欠点は忘れる――それこそ愚か者の特有の性質である」
- 「成長する若き世代を教え導く者ほど高貴な職務が、国家にとってより価値ある仕事が、ほかにあろうか」
- 「軽薄さは生まれつきのものであり、うぬぼれは教育によって身につく」
- 「最後の日がもたらすのは、私たちの消滅ではなく、場所の移り変わりである」
- 「自然は私たちの心に、真理を見たいという飽くなき渇望を植えつけた」
- 「私が存在しなくなるこれからの長い時間の方が、いまという短い現在よりも私に深い影響を及ぼす――それでいて、この現在は果てしなく感じられる」
- 「法律を知るとは、その文言を暗記することではなく、その全体の力と意味を理解することである」
- 「平和とは、静けさの中にある自由である」
- 「本のない家は、魂のない身体のようなものである」
- 「雄弁さと慎みを兼ね備えて語る弁論家には、大いなる敬意を抱かざるを得ない」
- 「戦争の筋(すじ)は無限の金である」
- 「法の最良の解釈者は慣習である」
- 「人は誰しも過ちを犯す。しかし、その過ちに固執するのは愚か者だけである」
- 「教える者の権威は、しばしば学ぼうとする者にとっての障害となる」
- 「友とは、いわばもう一人の自分である」
- 「正義とは、すべての人にその当然の権利を与える、確固たる不変の意思である」
- 「ある意味、奴隷状態は死に等しいと私は考える」
- 「過ぎ去った苦難の記憶は、甘美である」
- 「自由は、計り知れぬ価値を持つ財産である」
- 「感謝は最も偉大な徳であるばかりか、すべての徳の母でもある」
- 「戦時には、法は沈黙する」
- 「本のない部屋は、魂のない身体のようなものである」
- 「自分自身よりもよい助言を与えられる者は、他にいない」
- 「宇宙の探究と理解は、それに続く実際的な成果がなければ、どこか不完全で欠けたものとなるだろう」
- 「習慣の力は偉大である。それは我々に疲労を耐えさせ、傷や痛みを軽んじることを教える」
- 「生まれによって高貴となる者よりも、学びによって高貴となる者のほうが多い」
- 「ある者の弁護を断ることは、場合によっては許されるかもしれない。しかし、弁護を引き受けながらなお怠慢であることは、まさに犯罪に等しい」
- 「法の教えは次の三つに要約される――誠実に生きること、他人に害を与えないこと、そしてすべての人にその当然の権利を与えること」
- 「自然法によれば、他人の損害や被害によって誰かが富を得るのは、公平に反する」
- 「誰にでも降りかかる不運に対して、自分だけが不幸だと嘆く権利はない」
- 「善を労苦をもって追えば、労苦は去り、善は残る。悪を快楽をもって追えば、快楽は去り、悪が残る」
- 「知らぬことを知らぬと認めるのを、私は恥とは思わない」
- 「疑わしい場合には、より寛大な解釈を常に優先すべきである」
- 「簡潔さは雄弁の大きな魅力である」
- 「汝のものは我がもの、我がものはすべて汝のもの」
- 「すでに多くを負っている相手に、さらに恩義を重ねることをいとわぬのは、高貴さのあらわれである」
- 「憎しみとは、落ち着いて根を張った怒りである」
- 「自分自身より賢明な助言を与えられる者は、誰もいない」
- 「それを思うことを恥じないのなら、それを口にすることも恥じるべきではない」
- 「すべての苦痛は激しいか軽いかのいずれかである。軽ければ容易に耐えられるし、激しければ確実に長くは続かない」
- 「弁論家は、自らの主張が弱いときに最も激しく語るものである」
- 「賢者は理性によって学び、凡人は経験によって学び、愚者は必要に迫られて学び、野獣は本能によって動く」
- 「どんなに馬鹿げたことでも、それをすでに語った哲学者が必ずいるものだ」
- 「正しく定義された哲学とは、単に知恵への愛である」
- 「他人の不幸に流す涙は、すぐに乾くものだ」
- 「自分のためなら決してしないようなことを、どれほど多く友のためにはしていることか」
- 「法が多くなるほど、正義は少なくなる」
- 「沈黙は必ずしも肯定を意味しないが、否定でもない」
- 「最高の地位を目指しているのなら、たとえ二番目、三番目にとどまっても、それは立派なことだ」
- 「失敗したことほど、鮮明に目立ち、しっかりと記憶に刻まれるものはない」
- 「命あるかぎり、希望はある」
- 「決して度を超してはならない。節度を導き手とせよ」
- 「行政官は法の執行者であり、裁判官はその解釈者であり、我々すべては法の僕である。そうしてこそ、我々は自由でいられるのだ」
- 「帝国と自由」
- 「自然が人類に授けた贈り物のうち、子どもほど甘美なものが男にとって他にあるだろうか」
- 「友情の原則とは、互いに同情し合い、相手に欠けているものを補い合い、常に友愛と誠実な言葉をもって互いの利益を図ることである」
- 「すべてにおいて、最大の快楽のすぐ後には飽和がやって来る」
- 「庭と書斎があれば、人は必要なものすべてを手にしている」
- 「何という醜い獣、猿よ。そしてなんと我々に似ていることか」
- 「どれほど堅固に守られていようとも、金で落とせぬものはない」
- 「名誉なき能力は、無益である」
- 「すべての人の評判は、その人自身の家庭から生まれる」
- 「老年の収穫とは、過去に得た恵みの記憶と、その豊かさにある」
- 「たとえ最上のものを追い求めるとしても、その過程は穏やかで落ち着いたものであるべきだ」
- 「人は自らの持てるものを活かすべきであり、取り組むすべてのことには全力を尽くすべきである」
- 「誰もが自分の持つ山羊や羊の数は言えるのに、友人の数は言えない」
- 「徳とは、自然と節度と理性に即した、心の習慣である」
- 「生きることは、考えることだ」
- 「真理の探求に没頭するあまり、現実生活における必要な義務をおろそかにすべきではない。というのも、徳に真の価値と称賛を与えるのは、行動にほかならないからだ」
- 「他人の運に感嘆することはあっても、自分の運命に不満を覚えるほどではない」
- 「不正な平和であっても、正義の戦争に勝る」
- 「年寄りが金を埋めた場所を忘れたなんて話は聞いたことがない!老人は自分に関心のあることは覚えているのだ――裁判の日取りや、借金の相手や貸した相手の名前はしっかりと」
- 「どんなに信じがたいことでも、雄弁によって納得させることができる」
- 「長く老いて生きたいと思うなら、早めに老年の心を持つべきである」
- 「人に最もふさわしいのは、その人自身の気質と性格である」
- 「有罪の者を罰しそこねるほうが、無実の者を罰するよりましである」
- 「理性を使えぬ者だけが、激情に頼るのだ」
- 「戦争の時には、法は沈黙する」
- 「地位が高くなるほど、人はより謙虚に歩むべきである」
- 「友情は幸福をより大きくし、不幸を和らげる。それは、喜びを二倍にし、悲しみを半分にするからである」
- 「勇気ある者はまた、信念にも満ちている」
- 「人は喜びを忘れ、苦しみを覚えている」
- 「戦争が正当化されうる唯一の理由は、我々が無事に平和に生きるためである」
- 「敵に対して怒るべきだと言い、それを偉大で男らしいことと考える者たちの声に耳を貸してはならない。最も称賛に値し、最も高貴で偉大な魂を示すものは、寛容と許しの心である」
- 「国家にとっての死は、人間にとっての死ほど自然なものではない。人間にとって死は必要であるばかりか、しばしば望ましいことすらあるのだから」
- 「知恵の役割とは、善と悪を見分けることである」
- 「自由とは、人が自ら望むことを行う自然の力であり、それは力や法によって妨げられない限りにおいて成立する」
- 「最も大きな快楽は、嫌悪と紙一重のところにある」
- 「民衆ほど当てにならぬものはなく、人の意図ほど不明瞭なものもなく、選挙制度ほど欺きに満ちたものもない」
- 「共和政においては、次の原則が守られるべきである――多数派が支配的な権力を持ってはならない」
- 「困難が大きいほど、栄光もまた大きい」
- 「正義を伴わぬ知識は、知恵というよりも狡猾さと呼ばれるべきである」
- 「向こう見ずは若者のもの、慎重さは老年のもの」
- 「心の養いは、身体の食物と同じくらい必要である」