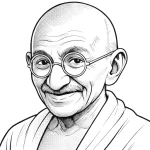「不寛容は、自らの主張に対する信頼の欠如を露呈するものである」
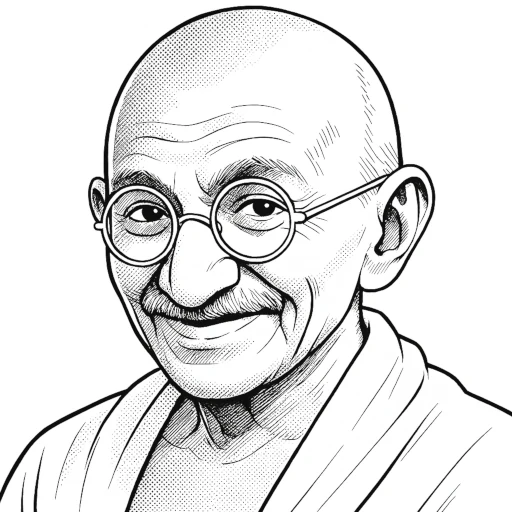
- 1869年10月2日~1948年1月30日
- イギリス領インド帝国出身
- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者
英文
“Intolerance betrays want of faith in one’s cause.”
日本語訳
「不寛容は、自らの主張に対する信頼の欠如を露呈するものである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、ガンディーが信念と態度の関係性を鋭く見抜いていたことを示すものである。彼は、不寛容――つまり異なる意見や存在を受け入れられない姿勢――は、しばしば自らの立場に自信がないことの表れだと考えていた。真に正しいと信じる主張であれば、対話や忍耐をもって堂々と向き合えるはずであり、強引な排除や抑圧はむしろその内にある不安や弱さを示す行為に他ならない。
この見解は、ガンディーの非暴力と対話に基づく運動哲学とも一致している。彼は、信念に基づく行動とは、敵意を持たず、誠実に説得し続ける力であるべきとし、暴力的手段や敵対的態度は道徳的優位を損なう行為と見なした。そのため、真の信念は寛容さと冷静さをともなって表現されるべきであり、怒りや排除はその信念の脆弱性を逆に暴露してしまうという警告が込められている。
現代においても、この名言は政治的・社会的な分断や過激な主張の中にある根源的な不安定さを見抜く視点を与えてくれる。意見の違いに直面したとき、不寛容に陥るのではなく、自らの立場を深め、対話を重ねることこそが、信念を強める道である。ガンディーのこの言葉は、本当に強い信念とは、他者の存在を脅かすことなく、自立して輝くものであるという真理を語っている。
「ガンディー」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!