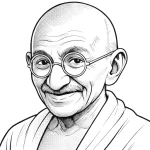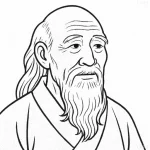「祈りにおいては、言葉のない心のほうが、心のない言葉よりもまさっている」
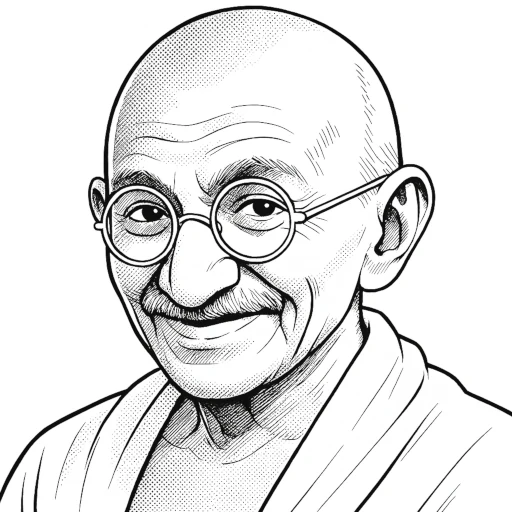
- 1869年10月2日~1948年1月30日
- イギリス領インド帝国出身
- 弁護士、宗教家、社会活動家、政治指導者
英文
“In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.”
日本語訳
「祈りにおいては、言葉のない心のほうが、心のない言葉よりもまさっている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、ガンディーが祈りの本質を形式ではなく、誠実な内面に求めていたことを端的に表している。彼は、祈りとは単に定められた言葉を唱えることではなく、心から湧き出る真摯な思いの表現であるべきだと考えていた。そのため、言葉が足りなくても、真実な心が込められていれば、それは真の祈りであるという価値観がこの言葉に込められている。
この思想は、ガンディーの信仰実践にもよく表れている。彼は日々の祈りを大切にしながらも、形式にとらわれるのではなく、心の深い集中と道徳的誠実さを重視した。これは、祈りが神との対話であると同時に、自己の良心と向き合うための静かな時間であるという理解に基づいている。
現代においてもこの名言は、宗教的実践が形式的になりがちな中で、内面的な誠実さの重要性を思い出させてくれる。ガンディーのこの言葉は、本質的な信仰とは、どれだけ心を込めて祈るかという「姿勢」にあるという、時代を超えた霊的真理を静かに語っている。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「ガンディー」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い