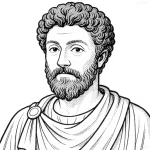「真の称賛はしばしば卑しき者にも与えられるが、偽りの称賛は強き者にしか与えられない」

- 紀元前1年頃~紀元65年
- ローマ帝国出身
- 哲学者、政治家、劇作家、倫理思想家
英文
“True praise comes often even to the lowly; false praise only to the strong.”
日本語訳
「真の称賛はしばしば卑しき者にも与えられるが、偽りの称賛は強き者にしか与えられない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、称賛の性質とその背後にある人間関係の力学を見抜いたセネカの鋭い観察を示している。真の称賛とは、徳や努力に基づいて自然に湧き起こる敬意であり、身分や権力に関係なく、誠実な人間に対して広く与えられる。対して、偽りの称賛――つまりお世辞やへつらいは、利益や恐れから動機づけられるものであり、力を持つ者にしか向けられないという、痛烈な社会批判が込められている。
セネカは、権力と取り巻く人間たちの関係をよく知る人物であった。皇帝ネロの顧問でありながら、権威の周囲に集まる虚飾と阿諛の危険を深く憂慮していた。この名言は、力を持つ者が受ける賞賛には、しばしば真実が欠けており、それは恐怖や打算によって作られた空虚なものにすぎないという洞察を表している。一方で、真に価値ある行為は、地位にかかわらず認められることがあるという希望もまた含まれている。
現代社会でも、権力者や著名人が受ける称賛が常に真実に基づくものとは限らない。セネカのこの言葉は、どのような称賛が本物であり、どのような称賛が利害に満ちた偽物であるかを見極める知性と倫理が必要であることを教えてくれる。真の価値は、評価される相手の地位ではなく、評価の背後にある誠実さに宿るという哲学的真理が、この名言には静かに込められている。
「セネカ」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!