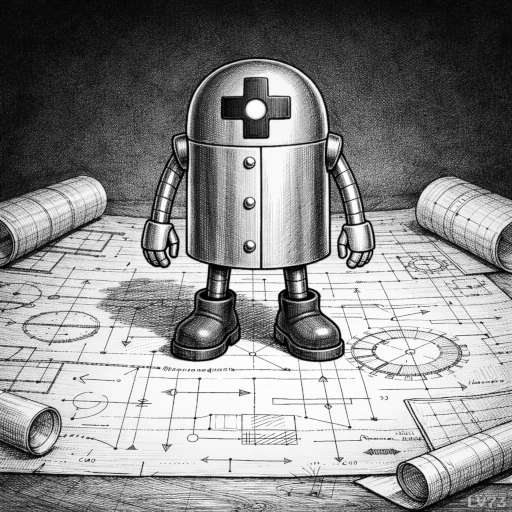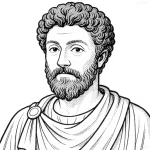「科学の歴史は、異なる文脈で発展した二つの技術や二つの思想を結びつけ、新たな真理を追求することで実りある成果が生まれた例に満ちている」

- 1904年4月22日~1967年2月18日
- アメリカ合衆国出身
- 理論物理学者、科学行政官、教育者
英文
“The history of science is rich in example of the fruitfulness of bringing two sets of techniques, two sets of ideas, developed in separate contexts for the pursuit of new truth, into touch with one another.”
日本語訳
「科学の歴史は、異なる文脈で発展した二つの技術や二つの思想を結びつけ、新たな真理を追求することで実りある成果が生まれた例に満ちている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、異分野の知の融合が科学の進歩においていかに重要であるかを示している。オッペンハイマーは、物理学者としてだけでなく、哲学、文学、東洋思想など多様な知識を横断してきた人物であり、学際的な視点の価値を深く理解していた。彼がここで強調しているのは、個別の技術や理論の完成度だけでなく、それらを組み合わせることで新たな洞察が生まれるという「化学反応」のような知的現象である。
科学史を振り返れば、力学と天文学の融合がニュートンの万有引力理論を生み、電気と磁気の統合がマクスウェルの方程式に結実したように、分野横断的な接触が革新の源泉となってきた。オッペンハイマー自身も、量子力学と核物理学の接点に立ち、理論と応用の境界を越えた視野によって原爆開発という人類史的転換に関わった。
この言葉は、現代にも強く響く。AIと医療、気候科学と経済、哲学と情報科学など、複数の知的領域が交差するところに未来の突破口がある。オッペンハイマーのこの発言は、固定化された専門性を超えて、知の接続を恐れずに追求せよという呼びかけであり、科学の創造性と進歩の本質を見抜いた名言である。
「オッペンハイマー」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!