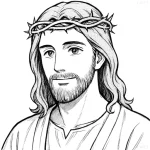「見よ、私は戸口に立ってたたいている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のもとに入り、彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう」

- 紀元前6年から紀元前4年頃~紀元後30年頃もしくは33年頃
- ユダヤ(現在のイスラエル・パレスチナ)出身
- 宗教指導者、伝道者
英文
“Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.”
日本語訳
「見よ、私は戸口に立ってたたいている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のもとに入り、彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、イエス・キリストがすべての人に向けて、信仰と関係を築く機会を与えていることを象徴している。イエスは「戸口に立ってたたく」ことで、各人の心の中へ入る準備ができていることを伝えており、その入り口を開くかどうかは、聞く者自身に委ねられている。イエスが人々と「共に食事をする」と述べているのは、ただ単に物理的な行為を指すのではなく、信仰を通じた深い交わりや親密な関係を意味している。この言葉は、心を開き、神との関係を築こうとする姿勢があれば、イエスはどのような者にも親しく接し、彼らを迎え入れることを約束している。
この教えは、現代においても多くの人々に対して深い示唆を与えるものである。人々は日々の生活の中で、多忙や不安、孤独に苛まれ、自分の心を閉ざしてしまうことが多いが、この言葉は「聞く耳を持ち、心を開くこと」の重要性を教えている。例えば、人生の困難に直面しているとき、信仰や内面的な成長に向き合うことによって、心の安定や希望が得られることがある。この教えは、私たちが日常の喧騒を少し離れ、自分の内なる声や信仰の導きに耳を傾けるよう促している。たとえば、忙しさに流されることなく、瞑想や祈りの時間を持つことは、この言葉を実践する一つの方法である。こうして心の「戸口」を開くことで、日常生活においてもより深い充実感や平安を得られる。
さらに、この教えは、人間関係やコミュニティとのつながりを築くための指針にもなる。イエスが共に食事をするという行為は、他者との絆や親密な関係を重視する姿勢を表している。私たちは他者との関わりの中で、自分の心を開き、理解と共感を深めることで、より豊かな関係を築くことができる。例えば、新しい出会いや友情においても、自分から心を開き、相手を受け入れることで、信頼が深まる。このようにして、「戸口に立ってたたく」というイエスの教えは、信仰と共に人間関係においても大切な「心を開く」姿勢を養い、豊かな人生を築くための道を示しているのである。
「イエス・キリスト」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!