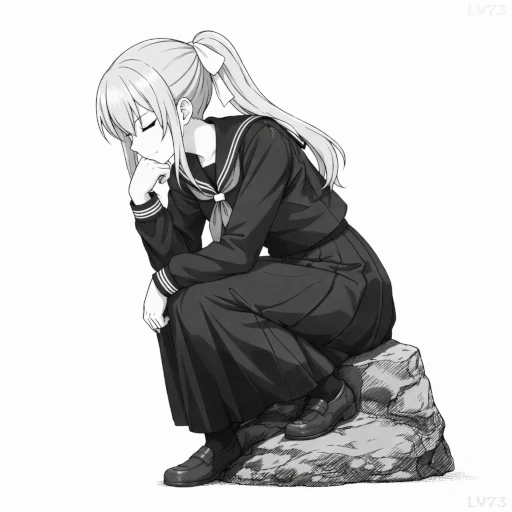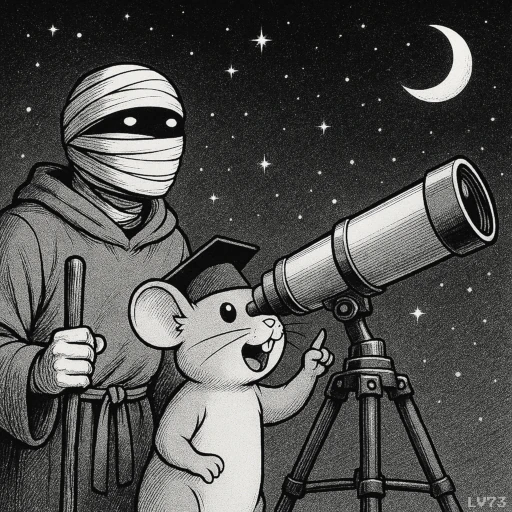「対なるものは全体であり、同時に全体ではない。調和するものは不調和でもあり、一致するものは対立している。すべてのものから一が生まれ、一からすべてのものが生まれる」
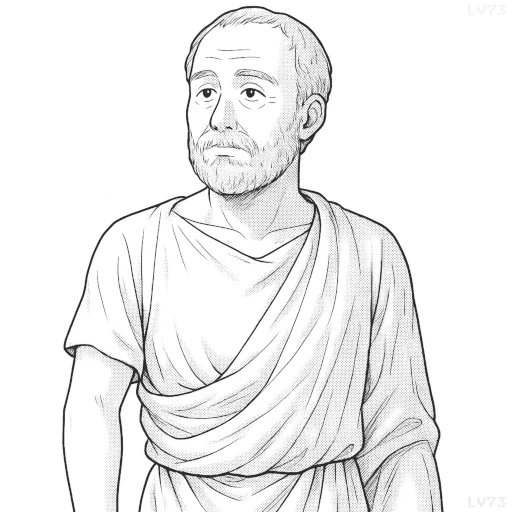
- 紀元前540年頃~紀元前480年頃
- 古代ギリシャ出身
- 哲学者
英文
“Couples are wholes and not wholes, what agrees disagrees, the concordant is discordant. From all things one and from one all things.”
日本語訳
「対なるものは全体であり、同時に全体ではない。調和するものは不調和でもあり、一致するものは対立している。すべてのものから一が生まれ、一からすべてのものが生まれる」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、ヘラクレイトス哲学の中核をなす対立と統一、分裂と統合の弁証法的世界観を鮮やかに示している。彼は、すべての存在は相反する力の緊張の中で成り立っており、完全な統一も恒常的な分裂も存在しないと考えた。「対なるものは全体であり、同時に全体ではない」という逆説は、相反するものが同時に真であるという動的な存在論を語っている。
さらに、「調和するものは不調和でもあり」とは、真の調和とは差異や矛盾を含んだ状態であることを意味する。これは、音楽の和声のように、異なる音が緊張を保ちつつ調和を生む構造とも重なる。そして、「すべてのものから一が生まれ、一からすべてのものが生まれる」という循環的な命題は、多様性と統一性の相互依存的な関係を指し示しており、ヘラクレイトスが説いたロゴス(理法)の概念にも通じる。
現代においてもこの名言は、矛盾や対立を否定するのではなく、それを内包した統一を志向する思考の重要性を教えてくれる。たとえば、文化・思想・人間関係の場面でも、異なる立場や意見の中にこそ、新しい価値や真理が生まれるという視点は、寛容と創造性の基礎となる。この言葉は、世界の成り立ちを固定的に見るのではなく、流動しつつ結び合う全体性として捉える哲学的な態度を示している。
「ヘラクレイトス」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!