ヘラクレイトス
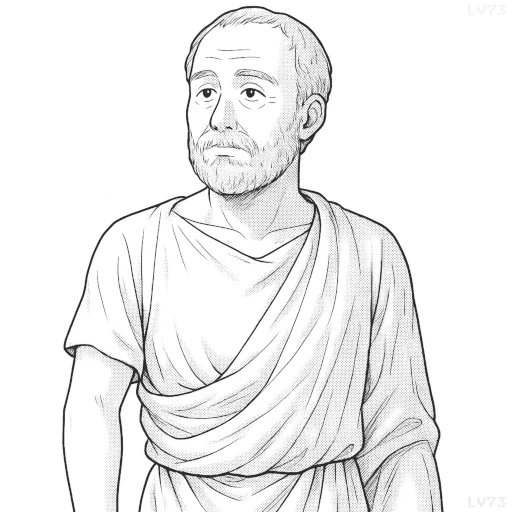
- 紀元前540年頃~紀元前480年頃
- 古代ギリシャ出身
- 哲学者
人物像と評価
ヘラクレイトス(Heraclitus)は、古代ギリシアの哲学者であり、万物の流転(パンタ・レイ)の思想によって知られる存在論の先駆者である。
彼は、あらゆる存在は絶えず変化し続けると主張し、「同じ川に二度入ることはできない」という言葉で象徴される流動的な世界観を提示した。
彼の中心概念は「ロゴス(理法・言葉)」であり、万物に内在する秩序や調和を示すものであった。
ヘラクレイトスは、対立の統一という弁証法的視点を持ち、「争いこそが万物の父」と述べ、対立するものが調和を生むという原理を唱えた。
この思想は後のストア派やヘーゲル哲学に強い影響を与えた。
その一方で、難解かつ断片的な著述により「暗い人(オブスキューロス)」と呼ばれ、同時代や後世の哲学者から批判を受けた。
しかし、彼の思想は変化・矛盾・調和というテーマにおいて極めて深遠であり、今日でも哲学史において独自の輝きを放っている。
名言
- 「上への道と下への道は同じである」
- 「良い人格は一週間や一か月で形づくられるものではない。少しずつ、日々の積み重ねによってつくられる。良い人格を育てるには、長期にわたる忍耐強い努力が必要である」
- 「思いがけないことを期待しなければ、それを見出すことはできない。それは探したり跡をたどったりして到達できるものではない」
- 「人の性格はその人自身の守護神である」
- 「多くを学んでも理解を教えることにはならない」
- 「私たちの嫉妬は、私たちが嫉妬する相手の幸福よりも常に長く続く」
- 「同じ川に二度足を踏み入れることはできない」
- 「人の心の欲望に抗うのは難しい。なぜなら、それが欲するものはすべて、魂の代償を払って手に入れるからである」
- 「人の性格はその人の運命である」
- 「自然はみずからを隠すのが常である」
- 「変化だけが不変である」
- 「変化のほかに永続するものはない」
- 「神は昼と夜、冬と夏、戦争と平和、飽きと飢えである」
- 「大きな成果には大きな野心が必要である」
- 「神にとってはすべてが美しく、善であり、正しい。しかし人間は、あるものを不正とし、別のものを正しいと考える」
- 「私は図書館と司書によって形づくられた人間であり、ギリシャ語の教授や詩人たちの助けはほとんどなかった」
- 「正義は嘘をでっちあげる者や偽証をする者を必ず追いつき、裁く」
- 「変化を除いて、永続するものは何もない」
- 「最も優れた人々は、ただ一つの目的――人間としての永遠の名声――のためにすべてを捨てる。しかし大多数の人々は、家畜のようにひたすら食べて満足している」
- 「対立は調和をもたらす。不和の中から最も美しい調和が生まれる」
- 「魂が未熟であれば、人にとって目や耳は頼りにならぬ証人である」
- 「眠っている者でさえ、宇宙の営みにおいて働き手であり、協力者である」
- 「太陽は毎日新しい」
- 「同じことを何度も繰り返すのは、単なる退屈ではない。それは自分が行動を支配するのではなく、行動に支配されているということだ」
- 「いくら無知を隠そうとしても、酒を酌み交わす夜にはたちまち露呈する」
- 「繁栄に出会う者は、同時に危険にも出会う」
- 「人は遊ぶ子どものような真剣さを得たとき、最も自分自身に近づく」
- 「性格は運命である」
- 「偏狭な信念は神聖なる病である」
- 「対なるものは全体であり、同時に全体ではない。調和するものは不調和でもあり、一致するものは対立している。すべてのものから一が生まれ、一からすべてのものが生まれる」
- 「目は耳よりも正確な証人である」
- 「意図的な暴力は、火よりも速やかに消し止めるべきである」
- 「世界を知ろうと望む者は、その具体的な細部を学ばねばならない」
- 「隠れた調和は、目に見える調和よりも優れている」