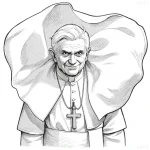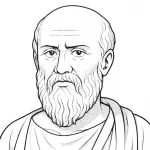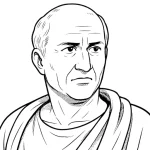「抜け目ない者が賢明な者として扱われることほど、国家に害をなすものはない」

- 1561年1月22日~1626年4月9日
- イングランド出身
- 哲学者、神学者、法学者、政治家、貴族
英文
“Nothing doth more hurt in a state than that cunning men pass for wise.”
日本語訳
「抜け目ない者が賢明な者として扱われることほど、国家に害をなすものはない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
フランシス・ベーコンのこの言葉は、狡猾な者と本当に賢明な者が混同されることが、社会や国家に重大な害をもたらすという警告を示している。彼は、狡猾さが賢明さとして評価されると、利己的で短期的な利益を追求する者が権力や影響力を持ち、国家や社会全体の長期的な利益が損なわれる危険性があると考えた。この言葉は、真の知恵と利己的な狡猾さの違いを見分けることの重要性を訴えている。
狡猾な者は、自分の利益や権力を守るために計算高く行動し、他人の利益や倫理観を犠牲にしてでも目先の成果を追求する。しかし、彼らのような人物が賢明な者として認められると、社会全体の道徳や倫理が失われ、正直で誠実な人々が軽視される風潮が広がりかねない。国家や組織において、賢明さと狡猾さが混同されると、社会の価値観や信頼性が損なわれ、長期的な繁栄が難しくなるのである。
現代においても、ベーコンの言葉は非常に示唆に富んでいる。政治やビジネスの世界で、短期的な利益や個人の成功のために倫理を犠牲にする行動が、時に「賢明」だと誤解されることがある。しかし、真の賢明さは、倫理観や公正さを基盤にして、社会全体の長期的な利益を考慮することにある。ベーコンの言葉は、真の知恵と狡猾さの違いを見極め、短期的な利益ではなく、持続的な正義と倫理を重視することの重要性を教えている。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?
「ベーコン」の前後の名言へ
申し込む
0 Comments
最も古い