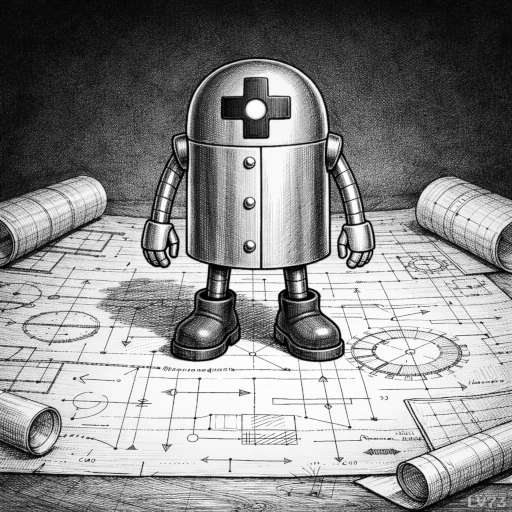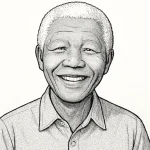「私は今日、ある意味で新しい言語で話さざるを得ないと感じている。軍事に生涯を捧げてきた私にとっては、決して使いたくなかった言語である。その新しい言語とは、原子戦争の言語である」

- 1890年10月14日~1969年3月28日
- アメリカ合衆国出身
- 第34代アメリカ合衆国大統領、軍人、政治家
英文
“I feel impelled to speak today in a language that in a sense is new—one which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare.”
日本語訳
「私は今日、ある意味で新しい言語で話さざるを得ないと感じている。軍事に生涯を捧げてきた私にとっては、決して使いたくなかった言語である。その新しい言語とは、原子戦争の言語である」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この言葉は、1953年1月17日にドワイト・D・アイゼンハワーがアメリカ合衆国大統領として就任して間もなく語ったものである。第二次世界大戦の英雄であり、NATOの初代最高司令官でもあった彼が、「原子戦争の言語」に言及することは、単なる修辞ではなく、深刻な決意と警鐘であった。軍人としての経歴をもつ者が、あえて軍事の枠を超えた破壊の可能性に言及することは、当時の国際情勢、特に冷戦の緊張を如実に物語っている。
この名言が放たれた1950年代初頭は、アメリカとソ連の間で核兵器の開発と配備が加速していた時代である。核兵器は従来の戦争とは異なり、全人類の存続に関わる問題であった。アイゼンハワーは、軍事のプロフェッショナルとしての立場から、核の使用が軍事戦略の一部となることへの強い危機感を抱いていた。それゆえに、使いたくなかった「言語」で語らざるを得ない現実に、深い苦悩がにじむ。
現代においても、核の脅威は依然として存在し続けている。北朝鮮の核開発、ロシアとNATOの対立、イラン核問題などがその具体例である。アイゼンハワーの言葉は、軍人ですら口にしたくなかった核戦争の現実が、いかに深刻かを示す歴史的証言であり、平和と理性による外交の必要性を今なお私たちに訴えかけている。
「アイゼンハワー」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!