ジッドゥ・クリシュナムルティ
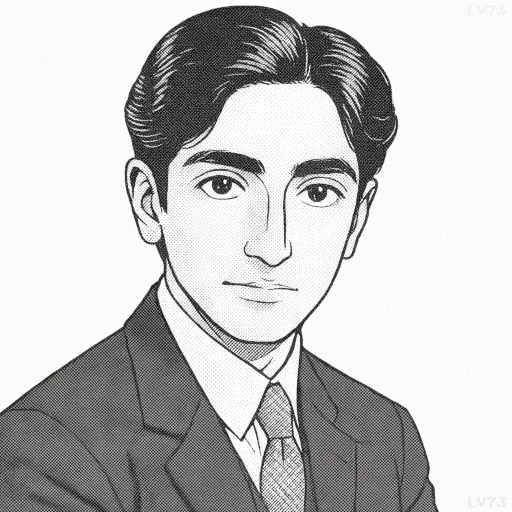
- 1895年5月11日~1986年2月17日(90歳没)
- インド出身
- 思想家、精神的指導者
人物像と評価
ジッドゥ・クリシュナムルティ(Jiddu Krishnamurti)は、インド出身の思想家・精神的教師であり、20世紀を代表する非伝統的な哲学者である。
彼はいかなる宗教・宗派・国家にも属さず、権威や組織に依存しない「自己探求」の重要性を説いた。
彼の功績は、宗教的・哲学的思考を超えて、日常的な意識と心の自由の追求を促したことにある。
神智学協会により「世界教師」として育てられたが、青年期にそれを拒否し、すべての権威や教義を否定。
以後、生涯にわたり講演・対話・執筆を通じて、「観察」「思考の構造」「自己」「恐れ」「時間」「真理とは何か」などを探求した。
批評的には、彼の思想は明確な体系や教義を持たないため抽象的・難解とされることがある一方、その純粋性ゆえに自由思想の極致と評価される。
また、物理学者デヴィッド・ボームとの対話など、科学と哲学の接点でも注目された。
彼は「真理は道なき土地である」という言葉で、すべての精神的依存からの脱却を訴え、人間の内面の革命を強調した。
その教えは、現代においても宗教や心理学、教育、倫理の分野に深い影響を与え続けている。
名言
- 「私たちが自然との関係をほとんど持たないというのは奇妙である。昆虫や跳ねるカエル、丘の間でつがいを呼ぶフクロウとの関わりがない。私たちは地上のすべての生き物に対する感情を抱いていないように思われる」
- 「昨日のすべてに死ぬことで、あなたの心は常に新鮮で、常に若く、無垢で、生気と情熱に満ちている」
- 「心が未知を知ることはできないという自らの無力さの真実を、心は見抜けるだろうか。確かに、もし私が心が未知を知ることはできないと明確に見るなら、そこには絶対的な静けさがある」
- 「信念を絶えず主張することは、恐れの表れである」
- 「私は世界であることをしようとしており、それを揺るぎない集中力で行うつもりである。私が自らを関わらせている本質的なことはただ一つ、人間を解放することである。私は人間をあらゆる檻やあらゆる恐れから解放したいのであり、宗教や新しい宗派を創設することでも、新しい理論や新しい哲学を打ち立てることでもない」
- 「人生とは関係であり、生きることは関係である。もしあなたと私が自らの周りに壁を築き、ときおりその壁越しに覗くだけなら、私たちは生きることができない。無意識のうちに、深いところで、その壁の下で、私たちはつながっている」
- 「真理とは道なき大地である」
- 「伝統は私たちの安心となるが、心が安心の中にあるとき、それは衰退している」
- 「必要なのは、逃避や支配、抑圧、あるいは他のいかなる抵抗でもなく、恐れを理解することである。それは恐れを観察し、それについて学び、それに直接触れることを意味する。私たちが学ぶべきは恐れから逃れる方法ではなく、恐れそのものである」
- 「瞑想には驚くほど覚醒した心が求められる。それは、あらゆる断片化が止んだ人生の全体性の理解である」
- 「自分自身の中に全世界がある。そして、もし見ることと学ぶことを知っているなら、扉はそこにあり、鍵はあなたの手の中にある。この地上の誰も、扉や鍵をあなたに与えることはできない。与えられるのはあなただけである」
- 「自らをインド人、ムスリム、キリスト教徒、ヨーロッパ人、あるいはその他の何かと呼ぶとき、あなたは暴力的である。なぜそれが暴力なのか分かるだろうか。それは自分を人類全体から切り離しているからである。信念や国籍、伝統によって自らを分離するとき、それは暴力を生み出す」
- 「もし私たちが幸福を他者や社会、環境に依存するなら、それらは私たちにとって不可欠なものとなる。私たちはそれにしがみつき、それらが変化することを激しく拒む。なぜなら、私たちは心理的な安心と快適さのためにそれに依存しているからである」
- 「私たちは皆、有名になりたいと願うが、何かになりたいと望んだ瞬間に、私たちはもはや自由ではなくなる」
- 「安らぎを求めて、私たちはたいてい人生の中で葛藤の最小限な静かな隅を見つけ、そしてその隠遁から踏み出すことを恐れる」
- 「私たちは皆、教育と環境によって、自己の利益と安心を求め、自分のために闘うように訓練されてきた。心地よい言葉でそれを覆い隠してはいるが、私たちは搾取と貪欲な恐れに基づいた体制の中で、様々な職業に就くための教育を受けてきた」
- 「たとえ海外で教育を受け、偉大な科学者や政治家になったとしても、もし寺院に行かなかったり、言われてきた普通のことをしなかったりすれば、何か悪いことが起きるのではないかという密かな恐れを常に抱いている。そのために人は従うのである。従う心には何が起こるのか。どうか調べてほしい」
- 「欲望という幕を通して聞くなら、あなたは明らかに自分自身の声を聞いているのであり、自分の欲望を聞いているのである」
- 「真理を引き下ろすことはできない。むしろ、個人が努力してそれに登らねばならない。山頂を谷に持ってくることはできない。もし山頂に至りたいなら、谷を通り、険しい坂を登り、危険な断崖を恐れずに進まねばならない」
- 「答えを求める欲望からの自由こそが、問題を理解するために不可欠である」
- 「自分が何であるかを変えようとせずに理解し始めるなら、そのとき自分は変容を遂げる」
- 「人は未知を恐れるのではない。恐れているのは、既知のものが終わることである」
- 「木を描いたり絵にしたりするとき、木を模倣するのではない。それをそのまま正確に写すのは、単なる写真にすぎない。木や花や夕日を自由に描くためには、それがあなたに伝えるもの――その意味、その意義――を感じなければならない」
- 「これが愛である。愛の花開くところ、それが瞑想である」
- 「愛とは沈黙であることに気づいたことはないだろうか。それは誰かの手を握っているときかもしれないし、子どもを慈しむ眼差しで見ているときかもしれないし、夕暮れの美しさを受け入れているときかもしれない。愛には過去も未来もなく、この特別な沈黙の状態もまたそうなのである」
- 「鋭い言葉を使うとき、人を払いのける仕草をするとき、それは暴力である。したがって暴力とは、神や社会や国家の名において行われる組織的な虐殺だけではない。暴力はもっと微妙で、もっと深いところにある」
- 「聞くことが重要となるのは、自分の欲望を投影せずに、それを通して聞いていないときである」
- 「私たちは木の本質を深く見つめることをしない。木に実際に触れ、その確かさやざらついた樹皮を感じ、その一部である音を聞くこともしない。葉を通り抜ける風の音でもなく、朝のそよ風が葉を揺らす音でもなく、幹の音、そして根の静かな音である」
- 「人類は長い歴史を通じて、自らを超え、物質的な福祉を超えた何かを探し求めてきた――それは真理や神、現実、時間を超えた状態と呼ばれるものであり、状況や思考、人間の堕落によって乱されることのないものである」
- 「心にこの特別なもの――愛――を抱き、その深さと喜びと恍惚を感じるとき、あなたにとって世界は変容していることに気づくだろう」
- 「人は誰も関係なしには生きられない。山に籠もり、修道士やサンニャーシーとなり、ひとりで砂漠をさまよったとしても、あなたは関係の中にある。その絶対的事実から逃れることはできない。孤立の中で存在することはできない」
- 「終わりはすべての始まりである。抑え込まれ、隠されたものが、苦痛と喜びの律動を通して解き放たれるのを待っている」
- 「私が自分を理解するとき、私はあなたを理解する。そしてその理解から愛が生まれる」
- 「なぜあなたの心は従うのか。問いかけたことはあるだろうか。自分がある型に従っていることに気づいているだろうか。その型が自分で作ったものであれ、他者によって作られたものであれ、それは問題ではない」
- 「私たちは飼いならされた動物であり、自ら築いた檻の中をぐるぐる回っている――その檻には争いや口論、どうしようもない政治指導者たち、そして私たちの自惚れを利用し、同時に自らの自惚れをも洗練された方法で、あるいはむしろ粗雑に利用する導師たちがいる」
- 「組織化された殺人こそが戦争である。そして私たちは特定の戦争――核戦争であれ、他の種類の戦争であれ――には抗議してきたが、戦争そのものに対しては決して抗議してこなかった」
- 「理解について語るとき、それは必ず心が完全に聞いているときにのみ起こる――その心とは、あなたの心臓、神経、耳であり――そこに全注意を注いでいるときである」
- 「生きるとは、自らにとって何が真実であるかを発見することである。そしてそれは自由があり、自分の内に絶え間ない革命があるときにのみ可能である」
- 「大人になったら自分は何をするのか、と自分に問いかけたことがあるだろうか。おそらく結婚し、気がつけば母や父となり、その後は仕事や台所に縛られ、やがて徐々にしおれていくだろう。それがあなたの人生のすべてなのだろうか」
- 「瞑想とはいかなる体系に従うことでもなく、絶え間ない反復や模倣でもない。瞑想とは集中でもない」
- 「瞑想とは、あらゆるものを部分ではなく全体として、完全な注意をもって見る心の状態である。そして誰もあなたに注意深くあることを教えることはできない。もしある体系が注意の仕方を教えるとしたら、あなたはその体系に注意しているのであって、それは注意ではない」
- 「年齢を重ねるにつれて、心と頭は鈍くなっていく」
- 「恐れを持たない人は攻撃的ではない。いかなる恐れの感覚も持たない人こそ、真に自由で平和な人である」
- 「もし恐れがあるなら、創造的な意味での自発性はあり得ない。この自発性を持つとは、何か独創的なことをすることであり、それを自発的に、自然に、指示されることも、強制されることも、支配されることもなく行うことである。それは、あなたが愛していることをするということである」
- 「瞑想とは、すべての思考と感情に気づくことであり、それが正しいか間違っているかを決して判断せず、ただ観察し、それと共に動くことである。その観察の中で、思考と感情の全体的な動きを理解し始める。そしてこの気づきから静けさが生まれる」
- 「首尾一貫した思考者は、実は無思慮な人間である。なぜなら彼は型に従い、決まり文句を繰り返し、同じ溝の中で考えているからである」
- 「私たちは愛が何であるかを知らない。私たちが知っているのはその症状であり、喜びや苦痛、恐れや不安などである。私たちはその症状を解決しようとするが、それは暗闇の中をさまようこととなる。私たちはこの中で日々と夜を過ごし、それはやがて死によって終わる」
- 「探求の運動は既知から既知へとしか向かうことができず、心ができることは、この運動が決して未知を明らかにすることはないと気づくことである。既知によるいかなる動きも、依然として既知の領域の中にある」
- 「語られていることだけでなく、すべてをどう聞くかを見出すことが重要ではないだろうか――街の騒音、小鳥のさえずり、路面電車の音、落ち着きのない海、夫や妻や友人の声、赤ん坊の泣き声にまで」
- 「私たちが生きると呼んでいるこの絶え間ない闘いの中で、私たちは育てられた社会に従って行動規範を定めようとする。それが共産主義社会であれ、いわゆる自由社会であれ同じである。私たちはヒンドゥー教徒やイスラム教徒、キリスト教徒、あるいは自分が属するものとして、伝統の一部として行動基準を受け入れている」
- 「真理は無限であり、条件づけられず、いかなる道によっても近づくことはできない。それゆえ組織化することはできないし、人々を特定の道へ導いたり強制したりする組織を作るべきでもない。まずそれを理解すれば、信念を組織化することがいかに不可能であるかが分かるだろう」
- 「信念とは純粋に個人的なものであり、それを組織化することはできず、またしてはならない。もしそうすれば、それは死に、固定化し、信条や宗派、宗教となって他者に押し付けられることになる」
- 「神や真理、実在があるかどうかという問いは、書物や司祭、哲学者や救世主によって答えられるものではない。その問いに答えられるのは自分自身だけであり、だからこそ自分自身を知らなければならない。未熟さとは、自分自身をまったく知らないことの中にのみ存在する」
- 「バーナード・ショーの戯曲を読めても、シェイクスピアやヴォルテール、あるいは新しい哲学者を引用できても、自らが知性的でなく、創造的でないのなら、この教育に何の意味があるのか」
- 「恐怖を抱いているならば、あなたは伝統に縛られ、ある指導者やグルに従うことになる。伝統に縛られ、夫や妻を恐れているとき、あなたは個々の人間としての尊厳を失う」
- 「宗教とは、人間の凍りついた思考であり、その上に彼らは寺院を築くのだ」
- 「深く病んだ社会にうまく適応することは、健康の尺度にはならない」
- 「愛こそが欠けている要素である。人間関係には愛情や温かさが不足している。そして私たちがその愛、その優しさ、その寛大さ、その慈悲を関係の中に欠いているがゆえに、大衆的行動へと逃避し、さらなる混乱と苦悩を生み出している」
- 「もし私たちが自然と深く永続する関係を築くことができれば、食欲のために動物を殺すことは決してなく、自分たちの利益のためにサルや犬やモルモットを傷つけたり、生体解剖したりすることも決してないだろう。私たちは傷を癒し、身体を治すための別の方法を見つけるはずである」
- 「若いうちに恐怖のない環境で生きることは本当にとても大切である。多くの人は年を重ねるにつれて怯えるようになり、生きることに恐れを抱き、職を失うことを恐れ、伝統を恐れ、近所の人や妻や夫に何を言われるかを恐れ、死をも恐れるようになる」
- 「私たちが社会と呼んでいる環境は過去の世代によって作られたものであり、それが私たちの貪欲さや所有欲、幻想を維持するのに役立つために、私たちはそれを受け入れている」
- 「だからこそ誰かに完全に、注意深く耳を傾けるとき、あなたは言葉だけでなく、伝えられている感情、その全体を聞いているのであり、一部だけを聞いているのではない」
- 「すべてのイデオロギーは愚かである。それが宗教的であれ政治的であれ、概念的な思考、概念としての言葉こそが、不幸にも人間を分裂させてきたのだ」
- 「教育に終わりはない。本を読み、試験に合格して教育が終わるのではない。生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで、人生全体が学びの過程なのである」
- 「もし私たちが本当に問題を理解することができれば、答えはその中から生まれてくる。なぜなら答えは問題と切り離されたものではないからだ」
- 「心が空であり、静かであり、完全な否定の状態にあるとき――それは空虚でも肯定の反対でもなく、すべての思考が止んだまったく異なる状態である――そのときにのみ、名づけ得ぬものが存在することが可能となる」
- 「私は、真理とは道なき地であり、いかなる道によっても、いかなる宗教によっても、いかなる宗派によっても、それに近づくことはできないと主張する」
- 「私たちのほとんどにとって、他者との関係は経済的あるいは心理的依存に基づいている。この依存が恐怖を生み、所有欲を育て、摩擦や疑念、欲求不満を生じさせる」
- 「私たちは中古の人間である。私たちは教え込まれたものに基づいて生きてきた。それは自分の傾向や性向に導かれたものであるか、あるいは状況や環境によって受け入れざるを得なかったものである。私たちはあらゆる影響の産物であり、自ら発見した新しいもの、独創的で純粋で明晰なものは何もない」
- 「人生は人間関係なしには成り立たない。しかし私たちはそれを個人的で所有的な愛に基づかせることで、苦悩と醜悪さに満ちたものにしてしまった。人は愛しながらも所有せずにいられるだろうか。真の答えは逃避や理想、信念の中にはなく、依存と所有欲の原因を理解することによってのみ見出される」
- 「人生の一部だけでなく、その全体を理解しなければならない。だからこそ本を読み、空を見上げ、歌い、踊り、詩を書き、苦しみ、そして理解する必要がある。それらすべてが人生なのだから」
- 「世界を旅すると、人間の本性がいかに驚くほど同じであるかに気づく。インドであろうとアメリカであろうと、ヨーロッパであろうとオーストラリアであろうと、それは変わらない」