エレノア・ルーズベルト

- 1884年10月11日~1962年11月7日
- アメリカ合衆国出身
- 大統領夫人(ファーストレディ)、人権活動家、外交官、作家
人物像と評価
エレノア・ルーズベルトは、アメリカ合衆国第32代大統領フランクリン・ルーズベルトの妻であり、20世紀を代表する人権活動家・外交官である。
ファーストレディとしての枠を超え、女性の社会参加、公民権、貧困問題に積極的に取り組んだ。
第二次世界大戦後は国連人権委員会の初代議長を務め、「世界人権宣言」の起草に中心的役割を果たした。
率直で行動的な姿勢は高く評価され、「良心の声」とも称された。民主主義と人道主義を体現した女性である。
「いいね」
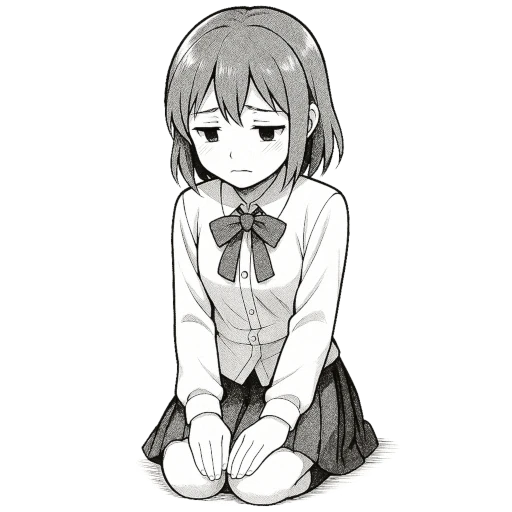
「いいね」が足りてない…
引用
- 「偉大な精神は理念について語り、凡庸な精神は出来事について語り、小さな精神は人について語ります」
- 「自分が重要だと感じたことがなくて本当に嬉しいです、それは人生を複雑にしますから」
- 「私は思いますが、子どもが生まれるときに、母親が妖精の名付け親に最も役に立つ贈り物を頼めるなら、その贈り物は好奇心であるべきです」
- 「もし人生が予測可能であったなら、それはもはや人生ではなく、味気ないものになります」
- 「かつて私の名前を冠したバラが作られて、とても光栄に思いました。でも、そのカタログの説明にはがっかりしました――『花壇には向かないが、壁際には最適』と書かれていたのです」
- 「自伝が役に立つのは、それらを読んで分析することで、自分自身の人生の旅にとって有益な何かを見出せるかもしれない場合だけです」
- 「願うことも計画することも、同じだけのエネルギーを要します」
- 「自分が進んでやろうとしないことを他人に求めるのは、公平ではありません」
- 「理解とは双方向の通り道です」
- 「幸福は目標ではなく、副産物です」
- 「貢献することをやめたとき、人は死に始めるのです」
- 「人とのあらゆる関わりの中で、心から必要とされ、望まれていると感じることこそが、最大の満足を与え、最も永続的な絆を生むのです」
- 「人々が受け入れられるよりも早く慣習を変えようとしてはなりません。それは何もしないという意味ではなく、優先順位に従ってなすべきことを行うということです」
- 「女性の個人としての権利をめぐる闘いは長きにわたるものであり、私たちの誰も、それを損なうようなことを容認してはなりません」
- 「自由はすべての人間に大きな要請を課します。自由には責任が伴います。成長することを望まず、自らの重荷を担おうとしない人にとって、それは恐ろしい見通しなのです」
- 「人の価値を測る真の基準は、その人の人格だけです」
- 「私は人生の多くの年月を反対の立場で過ごしてきましたが、その役割がむしろ気に入っています」
- 「家事があまり得意でないことの唯一の利点は、訪ねてきた人が自分のほうがずっと上手だと感じて、とても満足してくれることです」
- 「人生があまりにも順調すぎるときは注意しなければなりません。なぜなら、やがて誰にでも、富める者にも貧しい者にも訪れる打撃に、備えができていないかもしれないからです」
- 「私の経験では、落ち込んだときに立ち直る最良の方法のひとつは、ほとんどの場合、仕事に取り組むことです」
- 「選挙期間中の妻の振る舞い:常に時間を守ること。人間的に可能な限り話さないこと。パレードカーでは身を引いて、皆が大統領を見られるようにすること」
- 「おそらく自然こそが、不死に対する私たちの最も確かな保証なのです」
- 「あなたの同意なしに、誰もあなたを劣っていると感じさせることはできません」
- 「老いにはそれ自体に十分な歪みがあるのです。それに悪徳という歪みを加えるべきではありません」
- 「考える力のある者なら誰でも、次の戦争について考えるとき、自殺について考えるのと同じように感じるはずです」
- 「野心には容赦がありません。自らの役に立たない才能は、どんなものであれ、軽蔑の対象とするのです」
- 「人は、人生に正直かつ勇敢に向き合うことで、経験を通じて成長します。人格はこのようにして築かれるのです」
- 「未来は、自分の夢の美しさを信じる人々のものです」
- 「家事には、実際的で細かなことがあって、それを本当に理解している男性はまずいません」
- 「『イエス』と言う力を持たない人に、『ノー』と言わせてはなりません」
- 「重大な決定は、しばしば全員が男性で構成された機関で発案され形づくられるか、男性に完全に支配されており、女性が持つ特有の価値ある意見が表に出ることなく脇に追いやられてしまうのです」
- 「愛を与えることは、それ自体がひとつの学びなのです」
- 「憎しみと暴力は世界の一部にとどまることはできず、必ず他のすべての地域に影響を及ぼします」
- 「他人に喜びを与えることでより大きな喜びを得られるのなら、自分が与えられる幸せについて十分に考えるべきです」
- 「やらねばならないことは、たいていの場合、やり遂げることができるのです」
- 「新しい日が来れば、新たな力と新たな考えも生まれます」
- 「恐れていることに繰り返し挑み、成功体験を積み重ねていけば、誰でも恐怖を克服できると私は信じています」
- 「恐怖に真正面から向き合ったすべての経験によって、人は力と勇気と自信を得るのです。そうして自分にこう言えるようになります――『この恐怖を私は乗り越えた。だから次に来るものにも立ち向かえる』と」
- 「俳優たちは、世界中どこにいてもひとつの家族なのです」
- 「功績について言えば、そのときどきで、やるべきことをしただけです」
- 「あなたがしないことも、破壊的な力となり得るのです」
- 「信念を持ちなさい。親切でありなさい。相手が自分の信念を守るのと同じように、あなたも自分の信念を守りなさい。そして彼らと同じだけ懸命に働きなさい」
- 「結局のところ、私たちは自分の人生を形づくり、自分自身を形づくっていくのです。この過程は、死ぬまで終わることはありません。そして私たちの選択は、最終的にはすべて自分の責任なのです」
- 「私たちは、どういうわけか自分が本当はどんな人間なのかを知るようになり、そしてその決断とともに生きていくのだと思います」
- 「たとえ自分の子どもであっても、他人の人生を本当に生きることはできません。あなたが与える影響は、自分自身の人生と、あなたがどんな人間になったかによって生まれるのです」
- 「正義は一方のためだけにあるものではなく、双方のためにあるべきものです」
- 「戦争が最善の解決策だとは、私にはどうしても信じられません。前の戦争に勝者などおらず、次の戦争にも勝者はいないでしょう」
- 「私は夫にこう言ったものです――私に『理解』させられるなら、そのことは国中の人にとっても明確になるはずだと」
- 「家庭の母親は、家事や食事の計画を科学的な職業と見なすべきです」
- 「ときどき私はこう思うのです——私たちは政治においていつか大人になり、意味のあるはっきりとしたことを語るようになるのだろうか。それとも、誰もが同意できるが意味のほとんどない一般論を、これからも語り続けるのだろうかと」
- 「何が訪れようとも受け入れなければなりません。そして唯一大切なのは、それに勇気を持って、自分の持てる力のすべてで向き合うことです」
- 「おそらく人生でもっとも幸福な時期は中年であることが多いでしょう。若き日の熱情は落ち着き、老年の衰えはまだ始まっていないからです。ちょうど、朝や夕方に長く伸びる影が、正午にはほとんど消えてしまうのと同じように」
- 「私はあの年月を、とても非個人的に生きていたと思います。まるで、自分の外側に“大統領夫人”という別の人物を築き上げて、その人として振る舞っていたかのようでした。私は自分自身の深いところに埋もれて、見失われていたのです。ホワイトハウスを離れるまで、私はずっとそのように感じ、そのように働いていました」
- 「歴史、特にヨーロッパの歴史を知っている人なら誰でも、教育や政府が特定の宗教に支配されるという体制が、人々にとって決して幸せなものではないことを認めると思います」
- 「ドレの挿絵入りの聖書は、私の多くの時間を奪いました――そして、おそらく私に多くの悪夢を与えたのだと思います」
- 「あなたは、自分にはできないと思うことをやらなければならないのです」
- 「長く賞賛し続けられるものとは、なぜそれに惹かれるのか自分でもわからないままに賞賛しているものだけです」
- 「心の中で正しいと感じることをしなさい——どうせ批判されるのだから。やっても非難され、やらなくても非難されるのです」
- 「私たちに必要なのは、より多くの休暇ではなく、より深い天職です」
- 「私たちは、相手がまったく気にかけていないかもしれないという恐れから、深く思いやることを恐れてしまうのです」
- 「人間の苦しみを『報復』するのではなく『防ぐ』ために私たちが行動する――そんな繊細な良心を、私たちはいつ持つようになるのでしょうか」
- 「女性はティーバッグのようなものです——熱湯に入れてみなければ、その強さはわかりません」
- 「私は生まれつきの“母親”ではなかったと思います……もし誰かを母のように世話したいと思ったことがあるとすれば、それは父でした」
- 「平和について語るだけでは十分ではありません。それを信じなければならないのです。そして、信じるだけでも不十分であり、それに取り組まなければならないのです」
- 「人の哲学は、言葉ではなく、自分が下す選択によって最もよく表されます……そして私たちの選択は、最終的にはすべて自分自身の責任なのです」
- 「少しだけ物事を単純化することが、理性的な生き方への第一歩になると私は思います」
- 「あなたには個人として存在する権利があるだけでなく、個人である義務さえあることを、常に忘れないでください」
- 「人生は生き抜かねばならず、好奇心は常に持ち続けなければなりません。どんな理由があろうとも、人生に背を向けてはならないのです」
- 「自分自身との友情は何よりも大切です。なぜなら、それがなければ世界中の誰とも真の友情を築くことはできないからです」