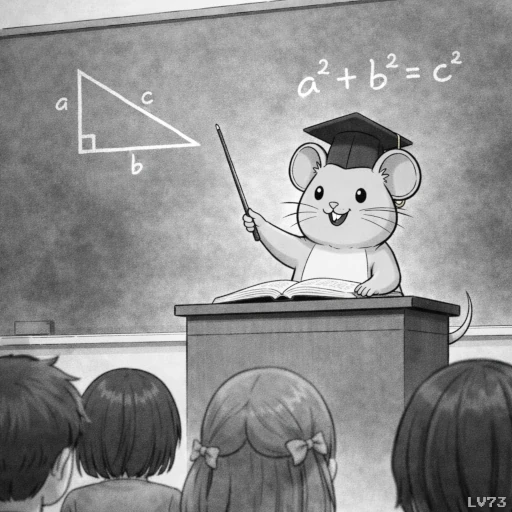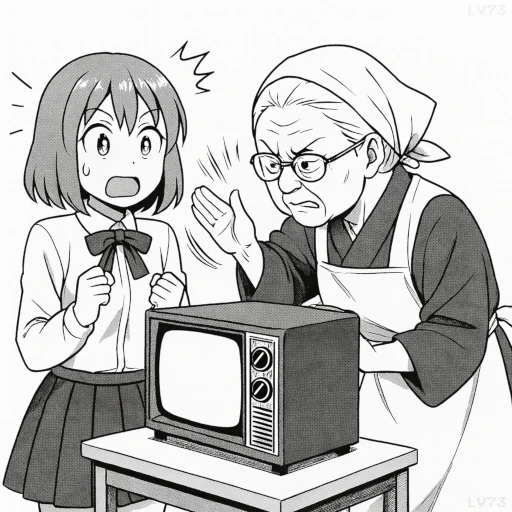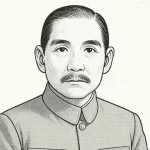「K-12(幼稚園から高校まで)では、ほとんどの人が地元の学校に通う。しかし大学は少し違い、子どもたちは実際に大学を選ぶ。ただ奇妙なのは、大学の評価が、入学してくる学生の質、つまり入学時のSATスコアで決まっているという点である」

- 1955年10月28日~
- アメリカ合衆国出身
- マイクロソフト共同創業者、実業家、慈善活動家
英文
“In K-12, almost everybody goes to local schools. Universities are a bit different because kids actually do pick the university. The bizarre thing, though, is that the merit of university is actually how good the students going in are: the SAT scores of the kids going in.”
日本語訳
「K-12(幼稚園から高校まで)では、ほとんどの人が地元の学校に通う。しかし大学は少し違い、子どもたちは実際に大学を選ぶ。ただ奇妙なのは、大学の評価が、入学してくる学生の質、つまり入学時のSATスコアで決まっているという点である」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、教育機関における評価基準の矛盾を鋭く指摘している。ビル・ゲイツは、K-12では選択肢が限られているのに対し、大学進学時には子どもたちが自ら選択する仕組みがあることを前提としつつ、大学の価値が教育成果ではなく、入学時点での学生の能力によって測られているという構造に疑問を投げかけている。教育機関の本来の役割は学生を成長させることであるはずなのに、それが十分に評価されていないという問題意識がにじんでいるのである。
現代においても、大学ランキングや評価指標の多くは、入学者の学力水準や選抜率に依存しており、教育の質や学生の成長度を正確に測るものではない。ビル・ゲイツはこの発言を通じて、教育機関の価値を「入学者の質」ではなく、「卒業時の成長」や「社会への貢献度」で測るべきだという方向性を示唆している。本当に重要なのは、どれだけ学生を育てたかであるという視点がこの言葉には込められている。
この発言の背景には、ビル・ゲイツが教育改革に強い関心を持ち、成果主義や学力向上を目指す様々な取り組みを支援してきた事実がある。彼は、教育の本質は機会を与え、能力を伸ばすことであり、それを正当に評価しなければならないと考えている。教育制度をより公平で効果的なものに変えていこうとする情熱が、この名言に凝縮されているのである。
「ビル・ゲイツ」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!