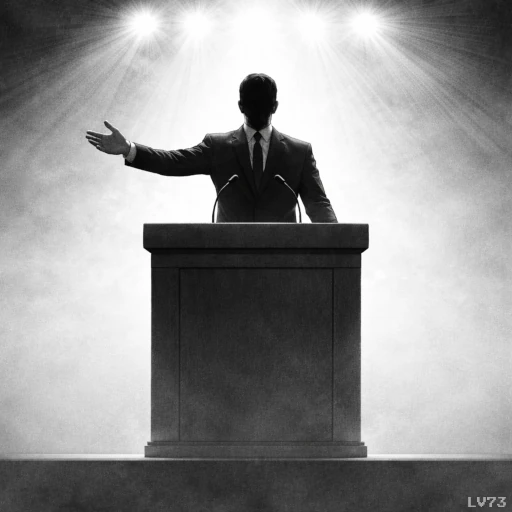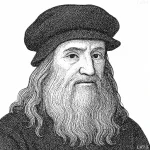「政を司る者は多忙であるため、新たな計画を熟慮し実行に移す手間を進んで負おうとはしない。ゆえに、最良の公共施策とは、事前の英知からではなく、往々にして状況に迫られて採られるものである」

- 1706年1月17日~1790年4月17日
- アメリカ合衆国出身
- 政治家、発明家、科学者、著述家
英文
“Those who govern, having much business on their hands, do not generally like to take the trouble of considering and carrying into execution new projects. The best public measures are therefore seldom adopted from previous wisdom, but forced by the occasion.”
日本語訳
「政を司る者は多忙であるため、新たな計画を熟慮し実行に移す手間を進んで負おうとはしない。ゆえに、最良の公共施策とは、事前の英知からではなく、往々にして状況に迫られて採られるものである」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、政治や行政の現実が理想や計画性よりも、目の前の危機や必要性によって動かされるという冷徹な観察を示している。ベンジャミン・フランクリンは政治実務に深く関わり、為政者が持つ日常的な負担の多さゆえに、革新的な施策には慎重かつ消極的になる傾向があることをよく理解していた。この言葉は、人間の惰性と組織の保守性によって、「最善の策」が非常時にしか実現しないという政治的現実を鋭く描写している。
現代の政策決定においても、しばしば重大な改革や制度変更は、長年の議論や計画からではなく、危機的な状況に追い詰められた結果として実施される。たとえば、自然災害、経済危機、戦争、パンデミックなどが発生して初めて、以前から必要とされていた法整備や制度改革が動き出す。これは、安定期には新しいことを嫌い、混乱期にはようやく知恵を総動員するという、人間社会の構造的問題を浮き彫りにしている。
この名言は、先見性と計画性の欠如が、最終的により高いコストと混乱を招くという警鐘でもある。フランクリンは、賢明な統治とは、危機が訪れる前に行動することにあると考えていたが、現実はそれに反して動くことが多い。この言葉は、真の知恵と指導力とは、「強いられて」ではなく「備えて」実行するものであるという理想を、あえて現実の皮肉を通じて私たちに問いかけている。
「ベンジャミン・フランクリン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!