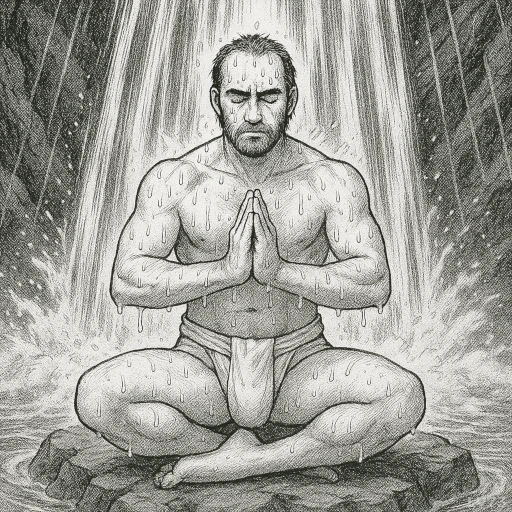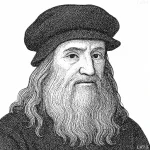「若き頃、私は多くの国を旅した。そして観察したのは、貧しい者に対して公的支援が多くなされるほど、彼ら自身の努力は少なくなり、その結果ますます貧しくなっていくということだった。逆に、支援が少ないほど、彼らは自らの力で努力し、より豊かになっていったということだ」

- 1706年1月17日~1790年4月17日
- アメリカ合衆国出身
- 政治家、発明家、科学者、著述家
英文
“In my youth, I traveled much, and I observed in different countries, that the more public provisions were made for the poor, the less they provided for themselves, and of course became poorer. And, on the contrary, the less was done for them, the more they did for themselves, and became richer.”
日本語訳
「若き頃、私は多くの国を旅した。そして観察したのは、貧しい者に対して公的支援が多くなされるほど、彼ら自身の努力は少なくなり、その結果ますます貧しくなっていくということだった。逆に、支援が少ないほど、彼らは自らの力で努力し、より豊かになっていったということだ」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、自己努力と公的支援との関係についてのフランクリンの経験的な見解を示している。彼は若いころからヨーロッパ各国を巡り、社会制度や人々の生活を観察してきたが、その中で、過度な支援がかえって貧困を固定化し、自己努力の意欲を奪うことがあると感じたのである。この見方は、福祉と自立のバランスの重要性を説いており、単純な支援だけでは貧困の根本的な解決にはならないという警鐘である。
現代の社会保障制度においても、この問題は依然として議論の対象である。生活保護や失業手当が必要な人を支える一方で、長期的な依存が労働意欲や自己改革の機会を奪ってしまう可能性もある。この言葉は、援助は一時的な支えであるべきで、最終的には自助努力によって生活を再建することが望ましいという、自己責任に重きを置いた考え方を反映している。
この名言は、人間の尊厳と主体性は、自らの行動によって築かれるべきだというメッセージでもある。フランクリンは、貧しさに対して慈悲を持ちながらも、依存ではなく、自立を促す社会こそが真に健全であると考えていた。援助の目的は単なる「与えること」ではなく、自らの力で立つための機会と動機を与えることであるという真理が、この言葉に凝縮されている。
「ベンジャミン・フランクリン」の前後の引用
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!