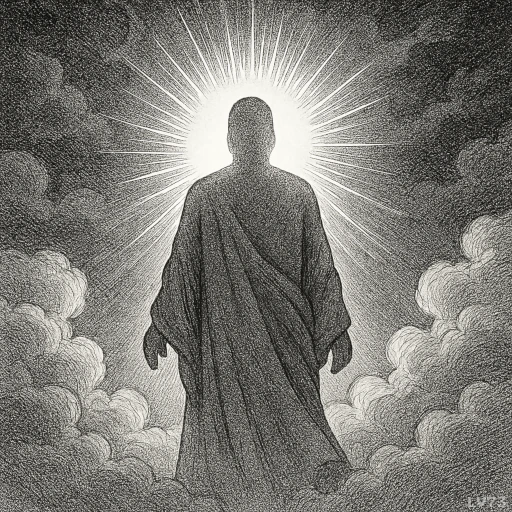「私は、善を報い、悪を罰するという神学上の神を信じていない」

- 1879年3月14日~1955年4月18日
- ドイツ出身
- 物理学者
英文
“I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil.”
日本語訳
「私は、善を報い、悪を罰するという神学上の神を信じていない」
出典
出典不詳(編集中)
解説
アインシュタインはこの言葉で、伝統的な神学の概念に基づく「善を報い、悪を罰する神」を信じていないと述べている。彼は、宇宙や自然の秩序を超越的な存在として敬意を抱きながらも、人間の道徳的な行動に対して個別に報酬や罰を与える人格神という考え方には懐疑的であった。この言葉には、アインシュタインが「神」を個人的な裁定者としてではなく、宇宙の理性や秩序の象徴として捉えていたことが表れている。彼は、神を人間的な判断基準に当てはめるのではなく、自然の背後にある不可解で偉大な法則や秩序として理解していた。
アインシュタインは、科学者として物理学や宇宙の秩序を探求する中で、自然界の神秘的な法則に対して敬意を抱き、そこに「神の存在」を感じていたが、それは個々の人間の行動を裁く人格的な神ではなかった。彼にとって、神とは人間の道徳的な行動に影響を与えるものではなく、宇宙の根本にある秩序そのものであった。この言葉は、アインシュタインが宗教的な信仰と倫理的な価値観を個別に考え、宇宙の真理を探る立場から神を捉えていたことを反映している。
この名言は、現代の宗教観や道徳観においても重要な示唆を提供している。神が人間の善悪に直接関与する存在として理解される一方で、アインシュタインのように神を宇宙の秩序や法則の象徴として捉える考え方も増えている。アインシュタインの言葉は、個々の道徳的判断や行動の責任は私たち自身にあるものであり、超越的な存在に委ねるものではないことを教えている。つまり、道徳的な行動は神や宗教的な報酬を求めるためではなく、社会や他者との調和を考え、自らの倫理観に基づいて行うべきであるというメッセージが含まれている。
感想はコメント欄へ
この名言に触れて、あなたの感想や名言に関する話などを是非コメント欄に書いてみませんか?