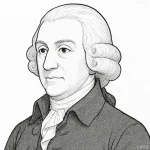「僕は一円の金を貰い、本屋へ本を買いに出かけると、なぜか一円の本を買ったことはなかった。しかし一円出しさえすれば、僕の欲しいと思う本は手にはいるのに違いなかった。僕はたびたび七十銭か八十銭の本を持って来た後、その本を買ったことを後悔していた。それはもちろん本ばかりではなかった。僕はこの心もちの中に中産下級階級を感じている」
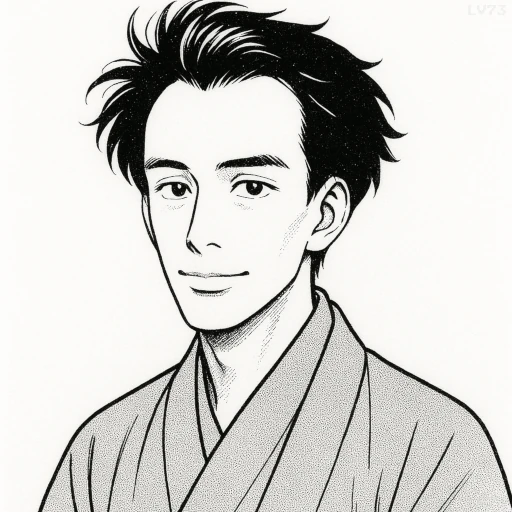
- 1892年3月1日~1927年7月24日
- 日本出身
- 小説家、評論家
原文
「僕は一円の金を貰い、本屋へ本を買いに出かけると、なぜか一円の本を買ったことはなかった。しかし一円出しさえすれば、僕の欲しいと思う本は手にはいるのに違いなかった。僕はたびたび七十銭か八十銭の本を持って来た後、その本を買ったことを後悔していた。それはもちろん本ばかりではなかった。僕はこの心もちの中に中産下級階級を感じている」
出典
出典不詳(編集中)
解説
この名言は、庶民的な金銭感覚と、それによって導かれる選択の中に潜む自己矛盾を鋭く描いている。芥川は、本当に欲しいものが一円で買えると分かっていながら、「全部使ってしまうこと」への無意識の抵抗から、妥協した七十銭や八十銭の選択をしてしまう。そしてその結果に後悔を覚えるという反復的な心のパターンが、この名言に明確に表れている。
ここで重要なのは、芥川がこの心理を単なる個人的な習性ではなく、「中産下級階級」に属する者の心性としてとらえている点である。つまり、完全に欲望を満たすことをためらう自己抑制と、使い切ることへの不安や慎重さは、階級的な感覚に根ざしたものであるという自覚がある。これは、経済的に不安定な生活を背景にした中流以下の人々の精神構造を見事に言語化している。
現代においても、多くの人が「少し余らせる」「本当に欲しいものを諦める」選択を無意識にしてしまうことがある。芥川のこの名言は、消費における内面的な逡巡と階級意識、そして小さな後悔の積み重ねが人間の感情にどれだけ根を下ろしているかを深く示しているのである。それは単なる買い物の話ではなく、自己認識と階級感覚をめぐる鋭利な省察である。
「芥川龍之介」の前後の名言へ
よろしければ評価をお願いします

気に入ったら「いいね」していってね!